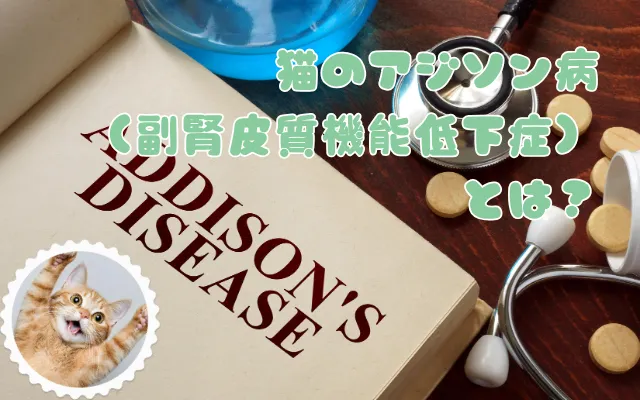「最近なんとなく元気がない」「検査で電解質の異常を指摘された」「原因不明の嘔吐や下痢が続いている」愛猫がそんな状態ならアジソン病かもしれません。
この記事では千歳船橋あむ動物病院の山田獣医師が猫のアジソン病について解説します。
猫のアジソン病(副腎皮質機能低下症)とは?
アジソン病は、副腎という小さな臓器の働きが低下し、体のバランスを保つために不可欠なホルモンや電解質(ナトリウム・カリウムなど)の調整がうまくできなくなる病気です。
猫での発症は非常に稀とされており、その原因もまだはっきりとわかっていません。しかし、自己免疫反応、腫瘍、外傷、臓器の壊死などが関与していると考えられています。
この病気には、電解質に異常が見られる「定型アジソン病」と、異常が見られない「非定型アジソン病」の2つのタイプがあります。
アジソン病(副腎皮質機能低下症)の症状は?
アジソン病に特徴的な症状というものはなく、以下のような、他の病気でも見られる一般的な症状がほとんどです。
- 元気がない、疲れやすい
- 食欲が落ちる
- 嘔吐や下痢を繰り返す
- 体重が減る
特に、ストレスがかかった後に急に症状が悪化する傾向があります。症状がはっきりしないため、診断が難しく、他の病気と間違われやすい点がこの病気の特徴です。重度の場合は入院管理が必要になることもあります(入院期間の中央値:4日)。
猫のアジソン病の検査と診断
アジソン病の診断は、いくつかの検査を組み合わせて慎重に行います。
- ACTH刺激試験:
副腎を刺激するホルモン(ACTH)を注射し、副腎から分泌されるホルモン(コルチゾール)の反応を見る、最も重要な検査です。アジソン病の猫では、コルチゾールの分泌が極端に低くなります。 - 血液検査:
電解質バランス(ナトリウム低下、カリウム上昇)の異常をチェックします。ただし、非定型アジソン病では電解質は正常値です。その他、カルシウム値や血糖値なども確認します。 - 腹部超音波(エコー)検査:
副腎の大きさを測定します。アジソン病では副腎が萎縮して小さくなっていることが多いですが、逆に腫れている場合はリンパ腫などの他の病気も疑います。 - レントゲン検査など:
脱水の状態や、心臓の大きさ、他の病気が隠れていないかなどを評価するために行います。
猫のアジソン病の治療法:生涯にわたるホルモン補充
アジソン病の治療は、不足している副腎皮質ホルモンをお薬で補う「ホルモン補充療法」が基本となり、生涯にわたる投薬が必要です。
状態が悪い場合(副腎クリーゼ)の入院治療
ぐったりして食事がとれないなど、症状が重い場合は入院が必要です。点滴によって脱水と電解質の異常を補正しながら、ホルモン剤の注射を行います。
自宅での治療(内科療法)
状態が安定すれば、飲み薬や注射による自宅での治療に切り替えます。使われるお薬には主に2種類あり、単独または組み合わせて使用します。
- ミネラロコルチコイド(鉱質コルチコイド):
電解質(Na、K)と体内の水分量を調節するホルモンです。- フルドロコルチゾン酢酸エステル(飲み薬)
- ピバル酸デソキシコルチコステロン(DOCP)(注射薬)
- グルココルチコイド(糖質コルチコイド):
代謝、免疫、ストレスへの応答など、体の恒常性を維持するホルモンです。 - プレドニゾロン(飲み薬)
お薬の組み合わせや量は、その子の症状、血液検査の結果、体質、ご家族の負担などを総合的に考慮して調整します。治療方針は途中で変わることもあるため、定期的な血液検査によるモニタリングが非常に大切です。
猫のアジソン病の予後(治療後の見通し)
適切な内科治療によって症状がうまくコントロールできれば、長期にわたり元気に過ごせる可能性が高い病気です。
- 生存期間中央値: 約5.6年(2035日)
- 1年後の生存率: 約76%
一度診断されると生涯治療が必要ですが、しっかりと管理を続けることで、良好な生活の質を維持することが期待できます。
![]() 千歳船橋あむ動物病院 消化器内科・腫瘍内科 主任
千歳船橋あむ動物病院 消化器内科・腫瘍内科 主任
山田拓実先生
治療薬には高価なものもあり、また生涯にわたる投薬が必要になるため、治療費が長期的な負担になることも考えられます。しかし、報告によってはグルココルチコイド単剤でコントロールできている例もあり、猫ちゃんの状態やご家族の状況に合わせて治療内容を柔軟に調整していくことが可能です。
「最近なんとなく元気がない」「検査で電解質の異常を指摘された」「原因不明の嘔吐や下痢が続いている」など、気になることがありましたら、信頼できる獣医師先生にご相談ください。
【獣医師・専門家向け】猫のアジソン病の参考情報
概要と特徴
猫のアジソン病(副腎皮質機能低下症)は、電解質異常の有無により「定型(低Na血症・高K血症を伴う)」と「非定型(電解質異常を伴わない)」に分類されます。発生年齢の中央値は5.7歳(範囲:0.2〜13.8歳)で、性差は認められていません(犬では若齢雌での好発傾向)。犬では非定型から定型へ移行する例が知られていますが、現在の報告では猫においてその移行は見られておらず、また、定型・非定型間での予後に明確な差はないとされています。
臨床検査所見
診断のゴールドスタンダードはACTH刺激試験での低反応(多くの症例でコルチゾールが検出限界以下)です。加えて、内因性ACTHの顕著な上昇(例:1250 pg/mL以上)や、血漿アルドステロン濃度の低下が特徴的な所見として挙げられます。高Ca血症が約31.7%の症例で認められており、一般状態の悪い猫で高Ca血症が見られた場合、鑑別診断の一つとして考慮すべきかもしれません。また、膵外分泌不全(EPI)の併発も報告されており、消化器症状が遷延する場合はTLIの測定やコバラミンの補充も検討が必要です。
画像診断と病理
腹部超音波検査において、副腎の厚さが2.7mm未満の場合にアジソン病が示唆されるという報告もありますが、確定的な基準はありません。ACTH刺激試験で低反応を示しつつ副腎の腫大が認められる場合は、副腎リンパ腫を強く疑う必要があります。剖検例では、T細胞性リンパ球形質細胞性副腎炎、特発性副腎壊死、副腎皮質の萎縮・線維化、そして大細胞性リンパ腫などが報告されています。
治療と予後
治療法別の生存期間中央値(MST)に関する報告では、DOCP投与群で中央値未到達、フルドロコルチゾン酢酸エステル群で4380日、プレドニゾロン単独群で2035日と、統計学的有意差はないものの、臨床的には治療選択によって生存期間に差が出る可能性が示唆されています。症例の臨床症状、電解質バランス、飼い主の経済的・物理的状況に応じて、DOCP、フルドロコルチゾン、プレドニゾロンなどを単独または組み合わせて治療法を選択することが、長期的な管理において重要であると考えられます。
参考
Clinical findings, treatment, and outcomes in cats with naturally occurring hypoadrenocorticism: 41 casesVETERINARY INTERNAL MEDICINE
参考
Clinical features and long-term management of cats with primary hypoadrenocorticism using desoxycorticosterone pivalate and prednisoloneJ Vet Intern Med
参考
Hypercalcaemia in cats: The complexities of calcium regulation and associated clinical challengesJ Feline Med Surg.
参考
犬と猫の内分泌疾患ハンドブック
参考
犬と猫の内分泌代謝疾患