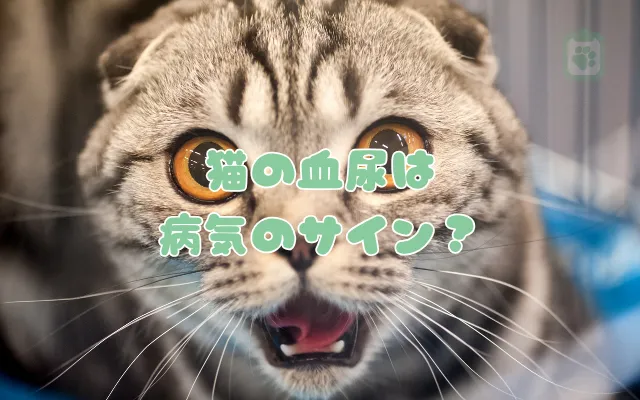愛猫の毎日の尿をチェックしていますか?便と同様に、尿は猫の健康状態を示す重要なバロメーターです。日々のトイレ掃除の際に尿の色や量を確認する習慣をつけ、愛猫の体調変化にいち早く気づけるようにしましょう。
猫の正常な尿は、透明感のある薄い黄色です。しかし、もし次のような変化に気づいたら注意が必要です。
- ✓ なんだか尿が赤い、ピンク色に見える…
- ✓ これって血尿?もしかして病気なの?
- ✓ 猫の血尿にはどんな原因があるの?
尿が赤く見える場合、血尿の可能性が非常に高いです。猫の血尿は、時に命に関わる重大な病気が隠れているサインでもあります。この記事では、飼い主さんが知っておくべき猫の血尿の主な原因と、すぐに動物病院へ行くべき危険なサインについて詳しく解説します。
猫の血尿、原因は?
猫の血尿とは、尿に赤血球が混じって排出される症状を指します。「赤色尿(赤い尿)」に含まれ、原因によって「血尿」と「血色素尿」の2種類に分けられます。それぞれ原因が異なるため、正しく理解することが重要です。
赤血球がそのまま含まれる「血尿」の主な原因
尿に赤血球が混じる「血尿」は、主に腎臓から尿道までの「泌尿器」のどこかで出血が起きているサインです。猫で血尿が見られる場合、以下のような原因が考えられます。
- 膀胱炎や尿路感染症:細菌感染などにより膀胱の粘膜が傷つき出血します。猫の血尿で最も多い原因の一つです。
- 尿路結石症:膀胱や尿道にできた結石が粘膜を傷つけることで出血します。
- 腎臓の病気:腎盂腎炎や腎結石など、腎臓自体の疾患が原因で血尿が出ることがあります。
- 外傷:交通事故や落下事故などで腰の周辺を強く打ち、腎臓や膀胱が損傷して出血するケースです。
- 腫瘍:膀胱や腎臓にできた腫瘍から出血している可能性も考えられます。
これらの原因により、膀胱や腎臓などの泌尿器系から出血が起きていることが多いです。
血液の成分が尿に含まれる「血色素尿」の主な原因
「血色素尿」は、血液中の赤血球が血管内で壊れてしまう溶血により「ヘモグロビン」という成分が尿に混ざったり、心筋や骨格筋が何らかの原因で障害を受けて「ミオグロビン」という成分などが尿に混ざった状態の尿を指します。
赤血球は体中に酸素を運ぶ重要な役割を担っているため、溶血が起こると猫は深刻な貧血状態に陥り、命の危険があります。血色素尿の主な原因には以下のようなものがあります。
- 中毒:タマネギやニラ、ニンニクなどのネギ類を猫が食べてしまうと、その成分が赤血球を破壊し、溶血を引き起こします。
- 感染症:ヘモプラズマ(旧ヘモバルトネラ)などの寄生体が赤血球に寄生することや、猫白血病ウイルスへの感染が原因となることがあります。
ヘモプラズマの感染
ヘモプラズマの感染経路は完全には解明されていませんが、現在ではノミやマダニといった外部寄生虫による吸血や、猫同士の喧嘩による咬み傷、母猫から子猫への垂直感染が主要な経路と考えられています。
猫白血病ウイルス(FeLV)の感染
猫白血病ウイルスは、感染猫との接触によって広がります。唾液にウイルスが含まれるため、「毛づくろい(グルーミング)」「食器の共有」「喧嘩による咬み傷」のほか、「母子感染(垂直感染・母乳感染)」「交尾」などが主な感染経路です。免疫不全状態になり、上記ヘモプラズマのような病原体の感染が成立する可能性があります。
尿が赤いことに加えて元気が無い、ふらつく、歯肉や鼻、肉球が白い・黄色化などあれば溶血による尿の変化である可能性が考えられます。
猫の血尿、危険なサインは?こんなときはすぐ病院へ
猫の血尿は、比較的軽度な原因のこともあれば、緊急治療が必要な危険な状態のサインであることもあります。もし血尿とともに以下の症状が1つでも見られたら、命に関わる可能性があるため、すぐに動物病院を受診してください。
- 落下や事故で負傷している
- 性器から出血がみられる
- 元気がなく、ぐったりしてふらふらしている
- トイレには行くのに尿がほとんど出ていない、または全く出ない
- お腹が張って膨らんでいる
- 口の中(歯茎など)が白や黄色に変色している
- タマネギなどのネギ類を食べたことがわかっている
- 激しく嘔吐する、または何度も吐くそぶりをみせる
特に、「事故にあった」「タマネギを食べた」といった場合は、尿の異常の有無に関わらず、ただちに動物病院へ連れて行く必要があります。
また、「血尿が出ているのに尿量が極端に少ない」「お腹がパンパンに膨らんでいる」という症状は、尿道が結石などで詰まってしまい、尿を排出できなくなる「尿道閉塞」を起こしているサインです。この状態が続くと、腎臓に大きなダメージが加わり「急性腎障害」を併発する可能性が非常に高いです。急性腎障害は、ごく短時間で急激に状態が悪化し、適切な治療を行わないと命を落とすこともある極めて危険な状態です。
病院受診時に持参したいもの
動物病院で血尿の原因を調べるには、尿検査が非常に重要です。もし可能であれば、液体のままの新鮮な尿を採尿して持参しましょう。ただし、猫砂やペットシーツに吸収されてしまった尿では正確な検査はできません。その場合は、無理に尿を持参しようとせず、血尿の色や状態がわかるようにスマートフォンなどで写真を撮っておくと、診察の助けになります。
猫の血尿の主な要因、膀胱炎や尿路結石にならないために
猫の血尿の原因として多くみられるのは、特発性膀胱炎や尿路結石です。これらは日頃の生活習慣を見直すことで、ある程度予防が期待できます。その他として腎・尿管・膀胱・尿道腫瘍、全身性疾患(中毒や血液疾患など)、外傷(転落・交通事故など)も原因となり得ます。
ここでは、血尿の主な原因である「膀胱炎」と「尿路結石」の予防と対策について解説します。
膀胱炎の予防と対策
猫の膀胱炎には、細菌感染が原因の「細菌性膀胱炎」と、ストレスや肥満など複数の要因が絡み合って起こる「特発性膀胱炎(猫下部尿路疾患(FLUTD)のうちの1つ)」があります。
- トイレの環境を常に清潔に保つ
- いつでも新鮮な水が飲めるようにして飲水量を増やす
- バランスの取れた食事管理と体重管理
- ストレスの少ない生活環境を整える
細菌の繁殖を防ぐためにトイレを清潔に保ち、飲水量を増やして尿量を確保することが基本です。おしっこと一緒に細菌を体外へ排出しやすくなります。特発性膀胱炎の原因ははっきりしていませんが、複数の要因が存在することが考えられており、肥満、飲水不足、寒さ、環境の変化によるストレスなどがリスク因子になるといわれています(Buffington et al., 2006a, Defauw et al., 2011, Lund et al., 2016)。特発性膀胱炎の猫の約40-60%は再発を経験するとされており、現状の環境の見直し(ex)プライベートを守れるようなトイレの見直しと設置数の見直し、おもちゃのローテーション、ゆっくり休める場所などの環境エンリッチメントの改善)や食事内容を見直すこと(ex)療法食の使用、ウェットフードの割合を増やすなど)が、膀胱炎の予防と対策につながります。( Buffington et al., 2006b; Westropp et al., 2019; Naarden and Corbee, 2020)
Association between behavioral factors and recurrence rate in cats with feline “idiopathic” cystitis
Marianne Caudron(2025)
尿路結石の予防と対策
尿路結石は、尿中のミネラル成分が結晶化し、石のように固まってしまう病気です。食事に含まれるミネラル成分の過剰摂取や、尿のpHバランスが崩れることが主な原因とされています。猫の尿石症はリン酸アンモニウムマグネシウム結石によるものとシュウ酸カルシウム結石によるものが全結石の割合のほとんどを占めています。(猫の治療ガイド2020、猫の診療指針 Part3)
- 塩分やミネラル(特にマグネシウム)を過剰に摂取させない
→結石の主成分を減らす - 獣医師に相談の上、療法食やサプリメントを活用する
→結石の主成分を減らす、飲水量を増やす、尿pHを調節する
塩分の多い人間の食べ物は絶対に与えないようにしましょう。キャットフードは、獣医師と相談しながら、愛猫の体質に合った低マグネシウム設計のものや、尿のpHを適切にコントロールする効果のある製品を選ぶことが予防につながります。
おしっこの粗相は病気のサイン?
トイレの場所や猫砂が気に入らない、引っ越しで環境が変わったストレスなど、猫が粗相をする原因は様々です。しかし、特に環境の変化などがないにもかかわらず、急にトイレ以外の場所で粗相をするようになった場合、それは病気のサインかもしれません。猫の特発性膀胱炎の発生率は上記で多いとお伝えしましたが、若い猫で多く、一方で高齢の猫では腫瘍や尿路感染症の診断が多いともされています(Lew-Kojrys et al., 2017)。
膀胱炎や尿路結石による痛みで、トイレで排尿することに恐怖を感じていたり、頻尿でトイレまで間に合わなかったりする可能性があります。粗相は猫からのSOSと捉え、一度かかりつけの動物病院で診てもらうことをおすすめします。
日頃から猫が血尿を出していないかチェック!
猫の血尿は、時に命に関わる重大な病気のサインです。愛猫の健康を守るためには、日頃から血尿が出ていないか、トイレの砂やペットシーツの色を注意深くチェックすることが何よりも大切です。
特に、外で排泄する習慣のある猫の場合は、飼い主さんが尿の変化に気づきにくく、発見が遅れがちです。できるだけ室内にも猫が気に入る快適なトイレを用意し、毎日のおしっこの色、量、回数を確認できる環境を整えましょう。早期発見・早期治療が、愛猫を苦しみから救う鍵となります。
血尿を引き起こす病気の多くは、猫に強い痛みを伴います。つらい思いをさせないためにも、塩分やミネラルバランスを考慮した食事、適度な運動、十分な水分補給ができる環境づくりなど、日頃のケアを心がけていきましょう。