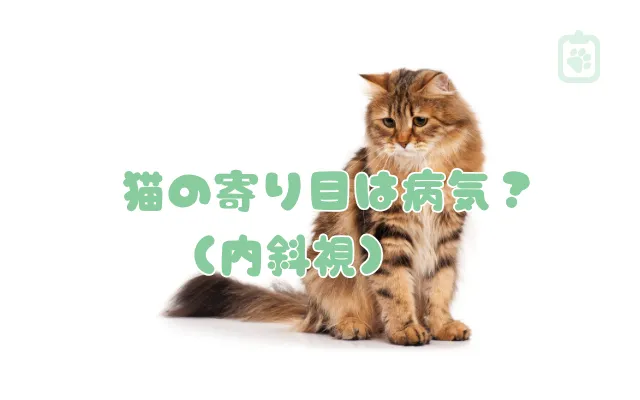愛猫の目が少し内側に寄っているように見える「寄り目」。専門的には「内斜視」といいます。可愛らしいチャームポイントに見える一方で、「これって病気なの?」「目に影響はないの?」と心配になる飼い主さんも多いのではないでしょうか。
猫の寄り目の多くは生まれつきの先天性のもので、日常生活に大きな支障はありません。しかし、成長してから突然寄り目になった場合は、病気や怪我が原因の可能性も考えられます。
この記事では、猫の寄り目(内斜視)について、その原因やメカニズム、なりやすい猫種、先天性と後天性の影響の違い、治療法まで詳しく解説します。
猫の寄り目(内斜視)とは
猫の斜視とは、左右の黒目が正しい位置からずれてしまう状態を指し、自分の意思で元に戻すことはできません。黒目が内側に向くものを「内斜視」、外側に向くものを「外斜視」と呼びます。
猫の斜視で最も多く見られるのが「内斜視」で、一般的に「寄り目」として知られています。
猫の寄り目(内斜視)は遺伝が主な原因
猫の寄り目の原因は、そのほとんどが遺伝による先天性(生まれつき)のものと考えられています。ただし、生まれてすぐに症状が現れるわけではなく、生後6〜8週頃から徐々に見られるようになります。
先天性の寄り目が自然に治ることはありませんが、日常生活に大きな問題はないことがほとんどです。一方で、子猫の時期に見られることがある「外斜視」は、体の成長とともに自然に治癒するケースが多く報告されています。
猫が寄り目になるメカニズム
ここでは、猫がなぜ寄り目(内斜視)になるのか、そのメカニズムを視覚の仕組みから解説します。
猫の正常な視覚の仕組み
| 正常な視覚情報の伝達経路 | |
|---|---|
| 情報を受ける場所 | 情報が送られる場所 |
| 右目の外側(耳側) | 右脳 |
| 左目の外側(耳側) | 左脳 |
| 右目の内側(鼻側) | 左脳 |
| 左目の内側(鼻側) | 右脳 |
猫の眼球の内側には、光を感じ取る「網膜」という組織があり、これは内側(鼻側)と外側(耳側)に分かれています。
正常な視覚回路では、左右の目の外側で受け取った情報はそれぞれ同じ側の脳(右目→右脳、左目→左脳)へ送られます。一方、左右の目の内側で受け取った情報は、脳の下にある「視交叉(しこうさ)」という部分で交差し、反対側の脳(右目→左脳、左目→右脳)へと伝達されます。
遺伝による網膜の異常が寄り目の原因
猫の寄り目(内斜視)は、先天的な遺伝子の影響で、この視覚情報の伝達経路に異常が生じることが主な原因です。
寄り目の猫の場合、本来なら交差しないはずの「目の外側」から入った情報の一部が、誤って視交叉を通り反対側の脳に送られてしまいます。これにより脳が情報を正しく処理できず、混乱した状態になります。
脳の混乱を防ぎ、視野を安定させるための適応
脳の混乱を解消するために、猫は自ら黒目を内側に寄せるようになります。目を内側に寄せることで、異常な経路を通りやすい「網膜の外側」から入る情報を制限し、正常な経路を通る「網膜の内側」からの情報を優先的に取り入れようとします。
つまり猫の寄り目は、視覚情報の混乱を抑え、できるだけクリアな視界を得るために発達した、猫自身の適応行動であると考えられています。
猫の寄り目が起こりやすい猫種
シャム
バーマン
ヒマラヤン
トンキニーズ
ラグドール
チンチラ など
猫の寄り目(内斜視)は、特定の猫種で発症しやすい傾向があります。
もちろん、これらの猫種のすべての個体が寄り目になるわけではありませんが、特にシャム猫やその血を引く猫、毛色が薄い猫は寄り目になる確率が高いとされています。
雑種であっても、シャム猫のような体の末端の色が濃い「ポインテッド」の猫や、色素が薄いアルビノの猫も、寄り目になりやすい遺伝子を持つといわれています。
シャム猫に寄り目(内斜視)が多い理由
シャム猫やその系統の猫に寄り目が多いのは、「サイアミーズ遺伝子」と「ダイリュート遺伝子」という2つの遺伝子が関係しています。
サイアミーズ遺伝子はシャム猫特有のポインテッド柄を発現させ、ダイリュート遺伝子は毛色を薄くする働きを持ちます。これらの遺伝子は、毛色のメラニン色素の生成を抑制する作用があります。しかし、この作用は温度に影響されるため、体温が低い手足の先や耳、尻尾などではメラニン色素が通常通り生成され、色が濃くなるのです。これがポインテッド柄の仕組みです。
このメラニン色素は、網膜の細胞から脳へつながる視神経の経路を正しく形成する上で重要な役割を担っていると考えられています。
メラニン色素を抑制する遺伝子の影響で、視神経の経路が正常に作られず、前述したような視覚情報の伝達異常が発生します。この異常を補うために、猫は自ら目を寄せるようになり、結果として寄り目(内斜視)になるのです。
眼球振盪(がんきゅうしんとう)を伴うことも
シャム猫の血を引く猫では、寄り目とあわせて、眼球が小刻みに揺れる「眼球振盪(がんきゅうしんとう)」が見られることもあります。
シャム猫との交配で生まれたヒマラヤン、バーマン、トンキニーズなども同様に、寄り目や眼球振盪が起こる可能性が高い猫種です。雑種でもシャム系の特徴を持つ猫は注意が必要です。
また、ポインテッド柄がなくても、クリームやライラックといった淡い毛色(ダイリュートカラー)の猫も、同じ遺伝子の働きにより同様の症状が出ることがあります。
もし、成猫になってから突然、寄り目や眼球振盪の症状が現れた場合は、目や脳の神経、筋肉の病気や怪我が疑われます。
猫が寄り目になった際の影響
猫が寄り目になった場合の影響は、生まれつきの「先天性」か、成長してから発症した「後天性」かによって大きく異なります。
【先天性】生まれつき寄り目の場合の影響
生まれつき寄り目の猫は、黒目が内側に寄っているため、両目で物を見る視野が狭くなり、立体感や奥行きを正確に捉えることが少し苦手です。
しかし、子猫の頃からその見え方に慣れているため、日常生活に大きな支障はありません。特に室内飼育であれば、危険はほとんどないでしょう。猫は優れたバランス感覚や聴覚など、他の能力で視野の狭さを十分に補うことができます。
外で暮らす猫の場合でも、寄り目が直接命に関わる危険は少ないですが、慣れない場所や障害物の多い環境では、咄嗟の判断が遅れるリスクは多少高まるかもしれません。
【後天性】急に寄り目になった場合の影響と原因
成猫になってから突然寄り目になった場合は、何らかの病気や怪我が原因である可能性が高く、注意が必要です。
怪我による視神経の損傷
交通事故や転落などで頭を強く打った際に、視神経がダメージを受けて寄り目になることがあります。頭部に怪我をした後、愛猫の目に異常が見られたらすぐに動物病院を受診しましょう。
命に関わる脳の病気
脳梗塞や脳出血、脳腫瘍といった脳の病気が原因で、寄り目の症状が現れることがあります。この場合、寄り目以外にも、けいれん発作、まっすぐ歩けない、ぐるぐる回る、倒れるといった神経症状が同時に見られることが多くあります。
このような症状は命に関わる重大なサインです。少しでも普段と違う様子が見られたら、迷わず動物病院で診察を受けてください。
目や神経の異常
目の周りの筋肉や、それを動かす神経に何らかの異常が起きて、後天的に寄り目になることもあります。
愛猫に突然寄り目の症状が現れたら、原因を特定するためにも、できるだけ早く動物病院を受診することが重要です。
猫の寄り目の治療方法
猫の寄り目の治療は、その原因によって異なります。
先天性の寄り目の場合、外科手術で目の筋肉の緊張を緩めることで見た目を改善することは可能です。しかし、原因が視神経の異常にあるため、根本的な治療とはならず、時間が経つと再発することがほとんどです。日常生活に支障がないため、積極的な治療は行わないのが一般的です。
一方で、病気や怪我が原因の後天的な寄り目は、その原因となっている病気(脳疾患など)を治療することで、症状が改善する可能性があります。
猫の寄り目(内斜視)に予防法はある?
遺伝が主な原因である先天性の内斜視(寄り目)には、残念ながら有効な予防法はありません。もし子猫に寄り目の症状が見られたら、一度動物病院で先天的なものか、他に異常がないかを確認してもらうと安心です。
猫の寄り目で注意すること
先天性の寄り目の猫と暮らす上で、基本的には過度な心配は不要ですが、いくつか配慮してあげたい点があります。
奥行きの把握が苦手なため、猫が走り回って遊ぶスペースには、ぶつかると危ない物を置かないようにしましょう。また、高い場所からのジャンプで距離感を見誤る可能性も考えて、キャットタワーの周りにはクッションを置くなど、安全な環境を整えてあげると安心です。
もし、寄り目の状態に加えて眼球の揺れ(眼球振盪)が激しくなったり、食欲不振や元気がないなど、他に何らかの異常が見られたりした場合は、すぐに動物病院を受診してください。
猫の寄り目を深く知るためのアレコレ
視力は人間の約10分の1
暗闇でものが見える仕組みがある
動くものを捉える動体視力に優れる
色の識別は苦手(特に赤色)
全体的な視野は人間より広い(約250°)
ここでは、猫の寄り目と関連の深い「猫の視覚」についての豆知識をいくつかご紹介します。
猫の視力は人間の約10分の1
猫の視力は0.1〜0.3程度とされ、人間の約10分の1しかありません。そのため、少し離れた場所にあるものや、静止しているものはぼんやりとしか見えていません。猫がはっきりと物を認識できるのは、およそ10m以内といわれています。
暗闇でものが見えるのは「タペタム」のおかげ
猫の目が暗闇で光るのは、網膜の裏にある「タペタム」という反射板のおかげです。タペタムは、網膜を通り抜けたわずかな光を反射して増幅させる働きがあり、これによって猫は人間の7分の1程度の光量でものを見ることができます。夜行性の猫にとって不可欠な器官ですが、光を多く反射する分、視界の解像度は低くなり、ぼやけて見えます。
猫は動体視力に優れる
猫は静止しているものを捉えるのは苦手ですが、動くものを追う「動体視力」は非常に優れています。特に、ネズミやトカゲといった獲物が動く速さに合わせて視覚が発達しており、素早い動きを正確に捉えることができます。
猫の目は色の識別が苦手
人間が虹の七色を識別できるのに対し、猫が識別できる色は限られています。特に赤色を認識するのは苦手で、主に青色や緑色の系統を識別していると考えられています。カラフルなキャットフードやおもちゃも、猫には人間と同じようには見えていません。
猫の全体視野は250度ある
| 視野の種類 | |
|---|---|
| 片目で見える範囲 | 単眼視野 |
| 両目で同時に見える範囲 | 両眼視野 |
| 左右の目を合わせた全体の視野 | 全体視野 |
| 視野の広さ | 猫 | 人間 |
|---|---|---|
| 両眼視野 | 120度 | 120度 |
| 全体視野 | 250度 | 200度 |
両目で物を見る「両眼視野」は、対象物との距離や奥行きを正確に測るために重要です。寄り目の猫の場合、この両眼視野がうまく機能せず、対象物までの正確な距離感を掴むのが難しいと考えられています。これが、日常生活で少し注意が必要な理由です。
愛猫の様子をしっかりと観察することが大切
猫の寄り目(内斜視)は、その多くが生まれつきの先天性のもので、個性の一つとして捉えることができます。日常生活に大きな支障はなく、過度に心配する必要はありません。
しかし、忘れてはならないのが、成猫になってから突然寄り目になった場合は、脳の病気や怪我といった緊急性の高い原因が隠れている可能性があるということです。
「生まれつきだから大丈夫」と安心するだけでなく、日頃から愛猫の目の状態や行動をよく観察し、少しでも「いつもと違う」と感じることがあれば、すぐに動物病院に相談しましょう。定期的な健康診断も、病気の早期発見につながる大切な習慣です。