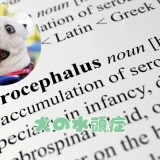愛犬のおしっこに血が混じる「血尿」。真っ赤な尿はもちろん、ピンクや茶色のおしっこも血尿のサインかもしれません。犬の血尿は、膀胱炎や尿路結石といった病気が隠れている可能性があり、飼い主さんにとっては非常に心配な症状です。しかし、血尿の色や量によっては気づきにくいこともあります。
この記事では、獣医師監修のもと、犬の血尿の症状や考えられる原因、ご家庭ですぐにできる対処法から動物病院での治療法までを詳しく解説します。愛犬の異変にいち早く気づき、病気の早期発見・治療につなげましょう。
犬の血尿、どんな症状?
犬の血尿とは、その名の通り尿に赤血球が混ざっている状態を指します。「血尿」は赤色尿に含まれ、赤色尿には血尿と見た目が同じに見える「血色素尿」もあります。
- 血尿:赤血球が尿に正常範囲を超えて含まれる状態の尿
- 血色素尿:ヘモグロビン尿、ミオグロビン尿などが含まれる
上記の2つは見た目で区別することは難しいです。また原因はそれぞれで異なります。
血尿と同時に起こりやすい症状
- トイレの回数が増える(頻尿)
- トイレの時間が長い、または出にくい
- 排尿時に痛そうに鳴く
- 陰部を頻繁に舐める、気にする
犬が血尿をしているとき、上記のような行動の変化が見られることが多くあります。何度もトイレに行くのに少ししか尿が出ない、排尿姿勢をとっている時間が長い、陰部を気にして舐め続けるといった行動は、泌尿器系のトラブルのサインです。これらの行動が見られたら血尿を疑い、おしっこの色を確認するために白いペットシートを使ったり、排尿後に白いティッシュペーパーで陰部を優しく拭いたりしてチェックしてみましょう。
犬の血尿、原因は?
- 尿路結石
- 膀胱炎
- 中毒
- 感染症
- 腫瘍
- 外傷
犬に血尿の症状が見られる場合、その原因は多岐にわたります。特に多いのは「尿路結石」や「膀胱炎」といった泌尿器系の病気です。その他、玉ねぎなどの危険な食べ物による中毒や、フィラリアなどの感染症、さらには交通事故などによる外傷が原因で尿の色調異常が出ることもあります。血尿は腎臓~外尿道口で内皮や上皮の損傷により出血が生じておこります。腎臓実質の出血も血尿の原因になりますが、多くは腎盂~外尿道口の部分が問題で生じます。その他として生殖器や副生殖器、血液凝固異常といった泌尿器以外の問題でも出血は認められることがあります。
以下は比較的多く認められる原因となります。
原因その1:尿路結石
尿路結石は、腎臓や膀胱などで形成された結石が尿の通り道(尿路)に詰まったり、粘膜を傷つけたりする病気です。結石が膀胱や尿道を傷つけることで出血し、血尿の原因となります。特にオス犬は尿道が細く長いため、結石が詰まりやすく、排尿困難に陥る危険性が高いとされています。
vet監修獣医師先生
原因その2:膀胱炎
- 細菌感染
- 結石による刺激
- 腫瘍
膀胱炎は、膀胱の粘膜に炎症が起こる病気で、犬の血尿の非常に多い原因の一つです。多くは尿道から侵入した細菌による感染が原因ですが、尿路結石や腫瘍が刺激となって発症することもあります。炎症によって膀胱の粘膜が傷つき、出血することで血尿となります。排尿の最後に血が混じることが多いのも特徴です。頻尿や排尿痛を伴い、悪化すると腎臓にまで炎症が広がる「腎盂腎炎」を引き起こすこともあります。
vet監修獣医師先生
原因その3:中毒
- 玉ねぎ、ネギ類
- 殺鼠剤(ねずみ駆除剤)
- ブドウ
犬にとって有害なものを誤って食べてしまうことで中毒を起こし、その症状の一つとして赤色尿が見られることがあります。代表的な原因は玉ねぎです。玉ねぎに含まれる成分が赤血球を破壊し、「溶血性貧血」を引き起こすことで、赤血球の色素が尿に混ざり、血色素尿となります。そのほか、嘔吐や下痢、元気消失などの症状を伴うことが多く、場合によっては命に関わる危険な状態です。殺鼠剤にはワルファリンが使用されており、人の抗血栓薬として使用されることがあります。これを大量に摂取してしまうことで出血がしやすい状態となり、血尿を引き起こす可能性があります。観葉植物で直接的に血尿を引き起こすものは一般的ではありませんが、腎障害が重度になった場合には腎性の血尿を認める可能性があります。観葉植物ではありませんがブドウは急性腎障害を引き起こし、結果として血尿を起こす可能性が考えられます。
原因その4:感染症
- フィラリア症
- バベシア症
- レプトスピラ症
特定の感染症が原因で尿の色調異常を引き起こすこともあります。これらの感染症は、尿の異常だけでなく全身に重篤な症状をもたらすため、早期の発見と治療が重要です。
フィラリア症
フィラリアは蚊が媒介する寄生虫で、主に犬の心臓や肺動脈に寄生します。多数のフィラリアが寄生することで「大静脈症候群」という急性症状を起こすと、赤血球が破壊され、赤ワインのような色の血尿(血色素尿)が見られます。咳や呼吸困難を伴い、緊急性の高い状態です。月1回の予防薬で確実に防げる病気です。
バベシア症
バベシアはマダニが媒介する原虫で、赤血球に寄生します。その結果、重度の貧血、高熱、黄疸、そして血色素尿といった症状を引き起こします。マダニの予防が最も効果的な対策です。
レプトスピラ症
レプトスピラはげっ歯類などの自然動物の尿で汚染された土壌や水に接触することで、経皮・経粘膜的に感染することがあります。いくつかの血清型がありそれぞれで症状に違いはありますが、多くで黄疸や急性腎不全症状、一般状態の低下が認められます。時に播種性血管内凝固(DIC)による出血傾向で血尿を示す可能性があります。
犬の血尿、発症しやすい犬種はいる?
- ミニチュア・シュナウザー:感染性ストルバイト、シュウ酸カルシウム
- シーズー:感染性ストルバイト、シュウ酸カルシウム
- ヨークシャー・テリア:シュウ酸カルシウム
- ミニチュア・ダックスフンド:シスチン
- ブルドッグ:特にイングリッシュブルドッグでは尿酸結石
- ダルメシアン:尿酸結石 など
犬の血尿の原因となる尿路結石やそれに続発する膀胱炎は、特定の犬種で発症しやすい傾向があります。上記の犬種は、遺伝的・体質的に尿路結石ができやすいとされています。しかし、犬種に関わらず、水をあまり飲まない犬、肥満気味の犬、なども血尿のリスクは高まります。
犬の血尿、発症してしまった場合の対処は?
愛犬の血尿に気づいたら、まずは落ち着いて様子を観察し、できるだけ早く動物病院を受診することが基本です。原因によって対処法は異なります。
尿路結石の場合
愛犬の血尿の原因が尿路結石だった場合、放置すると症状が悪化し、尿道が完全に詰まって尿毒症を起こすなど命に関わるため、早期の治療が不可欠です。排尿時に少しでも異変を感じたら、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。結石の種類や大きさによって治療法は異なり、食事療法や内服薬で結石を溶かす治療や、外科手術で結石を摘出する治療が行われます。
vet監修獣医師先生
膀胱炎の場合
血尿のほかに、頻尿や排尿痛などの症状がないか、元気や食欲はあるかなどをよく観察し、その内容を獣医師に伝えられるようにしておきましょう。可能であれば、清潔な容器に採尿して持参すると、スムーズな検査に繋がります。膀胱炎の治療は、主に抗生剤の投与など内科治療が中心となります。再発しやすい病気でもあるため、獣医師の指示に従って最後までしっかりと治療することが大切です。
中毒の場合
犬が有害なものを口にした可能性がある場合は、一刻も早く動物病院を受診してください。自己判断で無理に吐かせようとすると、かえって状態を悪化させることがあります。何を、いつ、どのくらい食べたかという情報を獣医師に伝えることが重要です。原因物質が残っていれば、それも持参しましょう。
vet監修獣医師先生
感染症の場合
感染症が疑われる場合も、速やかな動物病院の受診が必要です。原因となる病原体を特定するための検査を行い、その結果に基づいて適切な治療(駆虫薬、抗生剤の投与など)が行われます。フィラリア症やバベシア症は予防が可能な病気ですので、日頃からの対策が重要です。
犬の血尿、どんな検査が必要?
動物病院では、血尿の原因を特定するためにいくつかの検査を行います。
- 尿検査
- 画像検査(超音波、X線など)
- 血液検査
検査1:尿検査
犬の血尿の診断において、尿検査は最も基本的で重要な検査です。尿中の血液の有無や量、細菌、結晶、細胞などを顕微鏡で調べることで、膀胱炎や尿路結石などの病気の手がかりを得ます。
検査2:画像検査(超音波、X線など)
X線(レントゲン)検査や超音波(エコー)検査などの画像診断は、体内の様子を視覚的に確認するために行われます。これにより、結石や腫瘍の有無、大きさ、位置、そして膀胱や腎臓の状態を評価します。必要に応じて、より詳細なMRIやCT検査を行うこともあります。
検査3:血液検査
血液検査は、貧血の有無や腎臓・肝臓の機能、炎症の程度などを調べるために行います。重度の膀胱炎や腎盂腎炎、中毒、感染症など、全身に影響が及んでいる可能性がある場合に特に重要となります。
犬の血尿、対策するには?
愛犬を血尿の原因となる病気から守るためには、日頃からの予防が何よりも重要です。食事管理、適切な運動、生活環境の整備を心がけ、愛犬の健康を守りましょう。
- 適切な食事と水分補給:栄養バランスの取れたフードを与え、いつでも新鮮な水が飲める環境を整えましょう。十分な水分補給は、尿を薄め、結石の形成や膀胱炎の予防に繋がります。
- 適度な運動と体重管理:肥満は様々な病気のリスクを高めます。毎日の散歩などで適度な運動をさせ、理想的な体重を維持しましょう。
- トイレ環境を清潔に:トイレを我慢させないよう、常に清潔なトイレ環境を保ち、散歩の時間を確保してあげましょう。
- 誤飲・誤食の防止:犬にとって危険な食べ物や化学物質は、犬の手の届かない場所に保管し、誤飲事故を防ぎましょう。
- 感染症の予防:フィラリア予防薬の投与やノミ・マダニ駆除薬の使用、定期的なワクチン接種で感染症を予防しましょう。
愛犬をよく知ろう!
犬の血尿をはじめとする病気のサインにいち早く気づくためには、日頃から愛犬としっかりコミュニケーションを取り、普段の様子をよく観察することが大切です。毎日のスキンシップの中で体を触ったり、おしっこやうんちの状態をチェックしたりする習慣をつけましょう。
また、愛犬の犬種がかかりやすい病気を知っておくことも、病気の予防や早期発見に繋がります。普段の様子との「ちょっとした違い」が、病気の重要なサインであることも少なくありません。愛犬の健康を守れるのは、一番近くにいる飼い主さんです。