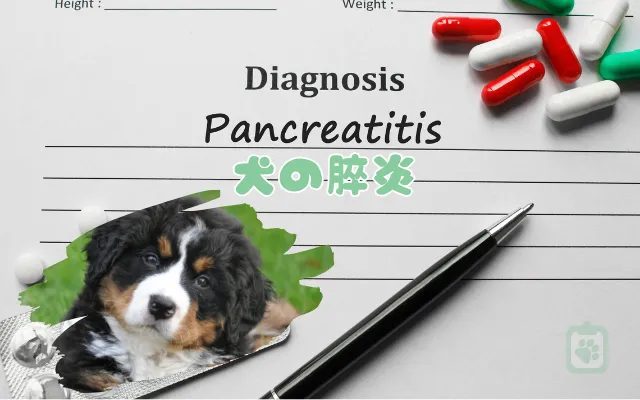愛犬が突然食欲をなくしたり、嘔吐や下痢を繰り返したりする姿を見ると、飼い主さんとしては非常に心配になりますよね。その症状、もしかしたら「犬の膵炎」かもしれません。
犬の膵炎とは、食べ物の消化を助ける「膵液」が何らかの原因で膵臓自体を消化してしまい、強い炎症を引き起こす病気です。膵液の流れ道である膵管が腫瘍や異物で詰まったり、激しい嘔吐が続いたりすることで発症リスクが高まります。
特に、中年齢以上のメス犬や肥満気味の犬、高脂血症(血液中の脂肪分が多い状態)の犬は膵炎にかかりやすいため、日頃からのケアが重要です。
✓愛犬の膵炎のために、何をしてあげればいいの?
✓犬の膵炎について、もっと詳しく知りたい
✓日頃のケアで膵炎は予防できる?
この記事では、犬の膵炎の症状や原因、具体的な治療法や手術、費用について詳しく解説します。愛犬の健康を守るための正しい知識を得て、少しでも飼い主さんの不安を取り除くことができれば幸いです。
犬の膵炎とは?
犬の膵炎とは、膵臓が分泌する消化酵素(膵液)によって、膵臓自体が消化されてしまい、重い炎症を起こす病気です。本来、膵液は十二指腸に送られてから活性化しますが、何らかの異常で膵臓内で活性化してしまうことで発症します。
急性の膵炎では強い腹痛を伴うため、犬は背中を丸めてうずくまったり、前足を伸ばして胸を床につけ、お尻を高く上げる「祈りのポーズ」と呼ばれる特徴的な姿勢をとったりすることがあります。
急性膵炎を繰り返すことで、炎症が持続する「慢性膵炎」に移行することもあります。犬ではこの慢性再発性膵炎が多く見られます。
膵臓の働き
膵臓は、胃の後ろに位置する細長い臓器です。主な働きは2つあります。
- 内分泌機能:インスリンやグルカゴンといった、血糖値をコントロールするホルモンを血液中に分泌します。
- 外分泌機能:タンパク質や脂肪、炭水化物を分解する消化酵素(膵液)を作り、十二指腸へ分泌します。
この両方の機能が、犬の健康維持に欠かせない重要な役割を担っています。
犬の膵炎、症状は?
犬の膵炎は、症状の現れ方によって「急性膵炎」と「慢性膵炎」の2つに分けられます。
急性膵炎
急性膵炎は、突然激しい症状が現れるのが特徴です。命に関わる危険な状態に陥ることも少なくありません。主な症状には以下のようなものがあります。
- 繰り返す嘔吐
- 激しい腹痛(お腹を触られるのを嫌がる、震える、祈りのポーズ)
- 食欲の完全な消失、元気がない
- 下痢(脂肪分を消化できず白っぽい脂肪便が出ることも)
- よだれが多い
重症化すると、「消化管からの出血」「黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)」「発熱」「呼吸が速くなる」といった症状が見られ、多臓器不全などを引き起こし、命を落とす危険性もあります。
慢性膵炎
慢性膵炎は、軽度の炎症が長期間続いたり、急性膵炎を繰り返したりすることで発症します。症状が穏やかであったり、症状が出たり治まったりを繰り返すため、他の消化器疾患との見分けがつきにくいのが特徴です。
- 断続的な嘔吐や下痢
- 食欲不振
- 体重の減少
- 元気がない
- 脱水症状
慢性膵炎によって膵臓の機能が徐々に低下すると、インスリンを分泌する能力が失われ、合併症として「糖尿病」を発症することがあります。また、重い炎症が続くと、体内の血液が固まりやすくなる「播種性血管内凝固症候群(DIC)」という危険な状態に陥ることも。無数の血栓(血の塊)が血管に詰まり、様々な臓器にダメージを与え、死に至るケースもあります。
vet監修獣医師先生
犬の膵炎、原因は?
高脂肪な食事
肥満
ホルモンの病気(内分泌疾患)
高脂血症
特定の薬剤や中毒
ストレス
犬の膵炎の正確な原因は完全には解明されていませんが、発症のリスクを高める危険因子がいくつか知られています。最も関連が深いと考えられているのが食事で、特に脂肪分の多い食事は膵臓に大きな負担をかけ、膵炎を引き起こす最大の要因とされています。
その他、肥満、ホルモンの病気(副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)、甲状腺機能低下症、糖尿病など)、高脂血症、ステロイド剤や抗がん剤などの薬剤、腹部の手術や外傷、ストレスなども発症に関与するといわれています。
vet監修獣医師先生
膵炎の診断・治療方法は?
診断方法
犬の膵炎を診断するためには、まず飼い主さんから食事内容や症状の経過などを詳しく聞く問診が行われます。その後、以下のような検査を組み合わせて総合的に判断します。
- 血液検査:炎症の程度を示す数値や、膵臓から漏れ出る酵素(リパーゼ、アミラーゼ)の値を測定します。特に「犬膵特異的リパーゼ(cPLI)」という検査は、膵炎の診断に非常に有用です。
- 画像検査:レントゲン検査や超音波(エコー)検査で、膵臓の腫れや炎症の様子、腹水の有無、他の消化器疾患との鑑別を行います。
治療方法
犬の膵炎の治療は、膵臓を休ませて炎症と痛みをコントロールすることが基本となり、多くの場合、入院による内科的治療が行われます。
- 輸液療法(点滴):脱水を改善し、体内の電解質バランスを整え、膵臓への血流を確保します。治療の基本となります。
- 薬物療法:吐き気を抑える「制吐剤」、強い痛みを和らげる「鎮痛剤」、二次的な細菌感染を防ぐ「抗生剤」などを投与します。
- タンパク分解酵素阻害剤:膵液の働きを抑え、膵臓の自己消化を防ぐ薬を使用することもあります。
- 栄養管理:絶食で膵臓を休ませることもありますが、近年では早期に栄養補給を開始することが推奨されています。鼻や食道にチューブを設置し、低脂肪・低タンパクの流動食を与えることもあります。
入院期間は症状の重症度によりますが、一般的には数日から1週間前後が目安です。退院後も、食事管理や投薬が必要になります。
手術費用について
膵臓の膿瘍や腫瘍が原因で膵炎を起こしている場合など、まれに外科手術が必要になることがあります。手術費用は病院や手術内容によって大きく異なりますが、10〜15万円程度が目安となることが多いようです。これに加えて、入院費用が1日あたり6,000円〜1万円ほど別途かかります。
高額な治療費に備え、万が一の時のためにペット保険への加入を検討しておくと安心です。
術後の対応
手術後は、全身状態が安定すれば退院となります。膵炎を一度発症した犬は再発しやすいため、退院後も獣医師の指示に従ったケアが非常に重要です。特に食事管理は生涯にわたって必要になることが多く、処方された療法食を続け、定期的な通院と検査が求められます。
退院後、うんちの状態が普段と異なることがあります。柔らかさや色がいつもと違う状態が続くようであれば、自己判断せず、かかりつけの獣医師に相談しましょう。
vet監修獣医師先生
犬の膵炎、食事は?
犬が膵炎にかかった場合、食事管理は治療と再発予防の要です。基本は「低脂肪・高消化性」の食事で膵臓への負担を最小限に抑えることです。
急性期を乗り越えた後や慢性膵炎の犬には、獣医師の指導のもと、膵炎用の療法食を与えるのが一般的です。手作り食を与える場合は、使用する食材に注意が必要です。
- おすすめの食材:鶏のささみや皮を取り除いた胸肉、タラなどの白身魚、じゃがいも、さつまいも、カッテージチーズ(低脂肪)、キャベツ、ブロッコリー、適量の白米など。
- 避けるべき食材:バターやラードなどの動物性脂肪、脂身の多い肉、揚げ物、加工品(ソーセージなど)、糖分の多い果物やおやつ。
食事は消化しやすいように人肌程度に温め、水分をしっかり摂らせることも大切です。急性膵炎から回復した後は数週間、慢性膵炎の場合は生涯にわたって食事療法を続ける必要があります。必要に応じて、ビタミンやミネラルを補うサプリメントの活用も獣医師に相談しましょう。
膵炎になりやすい犬種は?
遺伝的に膵炎を発症しやすい素因を持つとされる犬種がいます。
- ミニチュア・シュナウザー
- ヨークシャー・テリア
- コッカー・スパニエル
- コリー
- ボクサー
これらの犬種は、遺伝的な脂質代謝異常の傾向があり、膵炎のリスクが高いと言われています。しかし、膵炎は高脂肪食や肥満が大きな引き金となるため、犬種に関わらず、すべての犬で発症する可能性がある病気です。どんな犬でも日頃の食事と体重管理が重要です。
膵炎は対策できる?
犬の膵炎を100%予防する方法はありませんが、発症リスクを大幅に下げることは可能です。最も効果的な対策は、日々の生活習慣の見直しです。
- 食事管理の徹底:脂肪分の多い食事やおやつを避け、犬用の総合栄養食を基本としましょう。
- 人間の食べ物は与えない:味付けされた人間の食事は、犬にとって塩分や脂肪分が過剰です。絶対に与えないでください。
- 適正体重の維持:肥満は膵炎の大きなリスク因子です。定期的に体重を測定し、適度な運動とバランスの取れた食事で理想体型をキープしましょう。
- 定期的な健康診断:症状が出ていなくても、定期的に健康診断を受けることで、血液検査の異常などから病気の兆候を早期に発見できる可能性があります。
膵炎は早期発見・早期治療が非常に重要な病気です。日頃から愛犬の様子をよく観察し、少しでも異変を感じたらすぐに動物病院を受診しましょう。
毎日の食事で愛犬の健康を守ろう!
犬の膵炎は、日々の食生活と深く関わる、すべての犬にとって身近な病気です。しかし、それは裏を返せば、飼い主さんが毎日の食事を管理することで予防できる病気でもあるということです。
私たちが自身の健康のために食生活に気をつけるように、愛犬の食事もしっかりと管理し、肥満を防いで健康的な体を維持させてあげることが、飼い主の重要な役割です。
適切な食事管理と、愛犬に合った適度な運動を組み合わせることで、膵炎だけでなく様々な病気のリスクを減らすことができます。愛犬との健やかで楽しい毎日を一日でも長く続けるために、日頃のケアを大切にしていきましょう。