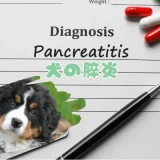愛犬の口が臭いと「もしかして病気?」と気になりますよね。飼い主さんにとって、愛犬の口臭は健康状態を知るための重要なサインです。
この記事では、獣医師監修のもと、犬の口臭の主な原因と、今日から始められる効果的な対策について詳しく解説します。
犬の口臭がひどい!口が臭い原因は?
犬の口臭には「口内環境の悪化」「胃腸や内臓の不調」「食べ物」の3つが考えられますが、そのほとんどは口内の問題が原因です。
口の中に残った食べカスをエサに雑菌が繁殖すると、歯の表面にネバネバとした歯垢(しこう)が形成されます。この歯垢こそが、雑菌が繁殖する温床となり、ひどい口臭を発生させるのです。
特に口臭がひどい、生臭い、腐敗臭がするといった場合は、歯垢が硬い歯石(しせき)に変化し、歯周病を発症している可能性が高いでしょう。歯周病は3歳以上の犬の約8割が罹患しているともいわれ、特に小型犬は若いうちから発症し、重症化しやすい傾向があるため注意が必要です。
放置は危険!犬の歯周病が引き起こす病気
歯周病を放置すると、歯周病菌が血管を通って全身に広がり、命に関わる病気を引き起こす可能性があります。
- 内臓疾患:心臓、肝臓、腎臓などの臓器に菌が到達し、心臓病や腎不全などを引き起こすことがあります。
- 下顎の骨折:歯を支える顎の骨が溶けてしまい、硬いものを食べただけで骨折することがあります。
- 根尖膿瘍(こんせんのうよう):歯の根元に膿が溜まり、目の下や顎が腫れて激しい痛みを伴います。
以下のような歯周病が疑われる症状が見られたら、早めに動物病院で診てもらいましょう。
- 歯茎が赤く腫れている、出血している
- 歯がグラグラしている
- 歯が黄色や茶色、黒っぽく変色している
- よだれが多い、よだれに血が混じる
- 口を触られるのを嫌がる
犬の口臭は、こうした深刻な病気のサインかもしれません。日頃から愛犬の口の中をチェックする習慣をつけましょう。
病気の可能性?
まれに、腎不全や肝不全、糖尿病、消化器系の病気などが原因で口臭が発生することもあります。アンモニア臭や甘酸っぱい臭いなど、普段と違う特有の口臭がする場合は注意が必要です。
口臭以外に「食欲がない」「元気がない」「水をたくさん飲む」「嘔吐や下痢」などの変化が見られる場合は、すぐに動物病院を受診してください。
vet監修獣医師先生
犬の口臭、原因が胃腸や内臓の不調だった場合は?
毎日の歯磨きなど、口内ケアをしても口臭が改善されない場合は、胃腸や内臓の不調が原因かもしれません。口臭の原因が口内かそれ以外かを見分ける簡単な方法があります。
まず、乾いたガーゼやタオルで愛犬の歯の表面を拭いてみてください。拭いたガーゼが臭ければ口内が原因、臭くなければ胃腸などから臭いが上がってきている可能性があります。胃腸炎や腸内環境の悪化が考えられるため、獣医師に相談しましょう。
胃腸や内臓が原因の口臭に家庭でできる対策
家庭では、腸内環境を整えることで口臭が改善される場合があります。
- プロバイオティクスを与える:ヨーグルトなどに含まれる善玉菌は、腸内環境のサポートにおすすめです。犬は乳糖を分解しにくいため、人間用の無糖ヨーグルトではなく、犬用のものを選びましょう。
- サプリメントを活用する:乳酸菌や酵素などが配合された犬用のサプリメントも効果的です。口臭だけでなく、便秘や軟便といったお腹の悩みを総合的にサポートしてくれます。
ただし、これらはあくまで補助的なケアです。根本的な原因が病気の場合は治療が必要ですので、まずは獣医師の診断を仰ぎましょう。
犬の口臭対策にできることは?
口臭対策の基本!ドッグフードを見直す
脂質やタンパク質が多いフードは、消化不良を起こしやすく口臭の原因になることがあります。また、穀物が多く含まれるフードは、炭水化物が口に残りやすく歯垢の元となります。
人工添加物が少なく、消化の良い高品質なドッグフードを選ぶことが口臭対策の第一歩です。フードを切り替える際は、今までのフードに少しずつ混ぜながら、1週間ほどかけてゆっくり慣らしてあげましょう。愛犬の健康のためにも、基本的には犬用の総合栄養食を与えるようにしてください。
最も効果的な口臭対策!毎日の歯磨き
犬の口臭対策として最も重要で効果的なのが、毎日の歯磨きです。歯垢は2〜3日で歯石に変わってしまうため、可能な限り毎日行いましょう。
注意点として、人間用の歯磨き粉は絶対に使用しないでください。人間用歯磨き粉に含まれる「キシリトール」は、犬が摂取すると重い中毒症状を引き起こす危険な成分です。必ず犬専用の歯磨き粉を使いましょう。
歯磨きの詳しいやり方は、こちらの記事も参考にしてくださいね。
歯磨きシート
どうしても歯ブラシを嫌がる犬には、歯磨きシートから始めるのも一つの方法です。指に巻きつけて歯の表面を優しく拭ってあげましょう。強くこすりすぎると歯茎を傷つけるので注意してください。
様々なフレーバーがあるので、愛犬が好むものを見つけて、まずは口に触られることに慣れてもらいましょう。
遊びながら口臭ケア!歯磨き効果のあるおもちゃ
犬は本来、獲物を噛みちぎることで自然と歯の汚れを落としていました。その習性を活かした、噛むことで歯垢を除去できるデンタルケア用のおもちゃも口臭対策に有効です。
ただし、硬すぎるおもちゃは歯が欠ける原因になるため、適度な弾力のあるものを選んであげてください。
動物病院での口臭対策!歯石除去
一度付着してしまった歯石は、家庭での歯磨きでは除去できません。動物病院で専門的な歯石除去(スケーリング)を受ける必要があります。
安全に隅々まで歯石を取り除くためには、全身麻酔下での処置が一般的です。無麻酔での歯石除去を謳うサービスもありますが、犬が動いて口内を傷つけたり、表面の歯石しか取れなかったりするリスクがあります。特に高齢犬や持病のある犬は、麻酔のリスクについて獣医師とよく相談した上で判断しましょう。
歯石除去は、信頼できるかかりつけの獣医師にお願いするのが最も安全です。費用は保険適用外で数万円かかりますが、歯周病の治療と判断されれば保険が適用される場合もあります。
手軽にできる口臭対策!デンタルスプレー
口に直接スプレーしたり、飲み水に混ぜたりするだけで口臭ケアができるデンタルスプレーも市販されています。歯磨きを嫌がる犬でも手軽に取り入れやすいのがメリットです。
歯石除去のような即効性はありませんが、日々のケアとして継続することで、口内環境を清潔に保ち、口臭を予防する効果が期待できます。愛犬に合った方法を選んであげましょう。
vet監修獣医師先生
まとめ
犬の口臭は、歯周病をはじめとする様々な病気のサインです。まずは口臭の主な原因である歯垢を溜めないために、毎日の歯磨きを習慣にしましょう。それでも口臭が改善されない場合や、他に気になる症状がある場合は、かかりつけの動物病院に相談することをおすすめします。日頃からのこまめなケアで、愛犬の健康と快適な暮らしを守っていきましょう。