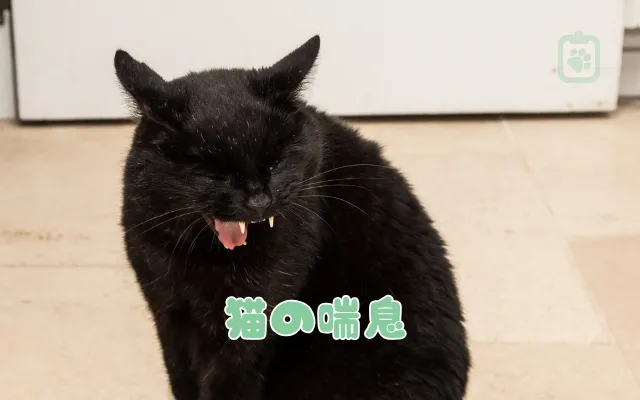猫の「喘息(ぜんそく)」は、アレルギーなどが原因で気管支に炎症が起こり、気道が狭くなることで呼吸困難などを引き起こす呼吸器系の病気です。
「アレルギー性気管支炎」や「好酸球性気管支炎」とも呼ばれ、放置すると命に関わる重篤な発作につながる可能性もあるため、早期発見と適切な治療が重要になります。
この記事では、猫の喘息について、具体的な症状の見分け方から原因、動物病院で行われる治療法までを詳しく解説します。
猫の喘息、症状は?
- 咳(特に乾いた咳)
- ゼーゼー、ヒューヒューという喘鳴(ぜんめい)
- 呼吸困難・呼吸が速い
- くしゃみ
- 嘔吐のような仕草
- チアノーゼ(舌や歯茎が青紫色になる)
猫の喘息の代表的な症状は、人間と同じような「咳」です。しかし、猫は犬ほど咳をしないため、飼い主さんが気づきにくい傾向にあります。
特に、急にしゃがみこんで首を前に伸ばし、咳き込む姿は「毛玉を吐こうとしている」と勘違いされがちです。咳の後に何も吐き出さない場合は、喘息のサインかもしれません。発作時には、ゼーゼー、ヒューヒューといった苦しそうな呼吸音(喘鳴)が聞こえたり、呼吸が速くなったりします。重度の発作では、酸欠により舌や歯茎が青紫色になる「チアノーゼ」が見られ、非常に危険な状態です。
猫の喘息、原因は?
- アレルギー性(アレルゲン)
- 非アレルギー性
猫の喘息が発症する明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、多くはアレルゲン(アレルギーの原因物質)に対する免疫の過剰反応による「アレルギー性」のものと考えられています。
アレルギー性
アレルギーの原因となるアレルゲンは、私たちの身の回りに数多く存在します。代表的なものには、ハウスダスト、ダニ、カビ、花粉、タバコの煙などがあります。その他、香水や芳香剤、殺虫剤、猫砂の粉じんなども原因となり得ます。
非アレルギー性
アレルギー以外では、肥満、ストレス、寄生虫(肺吸虫など)の感染、急激な温度変化(冷たい空気の吸引など)が、喘息の発作を引き起こす要因になることもあります。原因を特定し、生活環境から取り除くことが治療の第一歩となります。
猫の喘息、診断方法は?
- 身体検査(聴診など)
- X線(レントゲン)検査
- 血液検査
- 気管支肺胞洗浄(BAL)
猫の喘息の診断は、まず飼い主さんからの問診(症状や生活環境の確認)と、聴診などの身体検査から始まります。咳や呼吸困難といった症状は、心臓病や肺炎、フィラリア症など他の病気でも見られるため、それらの可能性を排除するための検査が重要です。
X線検査では、喘息に特徴的な気管支の壁が厚くなっている様子(ドーナツサイン)が確認できることがあります。血液検査ではアレルギー反応に関わる好酸球の増加が見られるかを確認し、気管支肺胞洗浄では気道内の細胞を直接調べることで、より正確な診断につなげます。診断は複数の検査結果を総合的に判断して行われます。
猫の喘息、治療はどのように行う?
- 内服薬・吸入薬による対症療法
- 原因(アレルゲン)の除去
猫の喘息治療は、炎症を抑える「ステロイド」と、狭くなった気管支を広げる「気管支拡張薬」の投与が中心となります。これらの薬は、飲み薬のほか、猫用の吸入器(エアロチャンバー)を使った吸入療法で投与することもあります。
呼吸困難など重度の発作を起こしている場合は、緊急的に酸素吸入や注射による処置が必要です。喘息は完治が難しい病気ですが、これらの治療と並行して、原因となるアレルゲンの特定と除去、生活環境の改善を行うことで、発作の頻度を減らし、症状をコントロールしていくことが治療の目標となります。
猫の喘息、対策はできる?
猫の喘息の最も効果的な対策は、発作の引き金となるアレルゲンや刺激物を生活環境から徹底的に排除することです。日頃から以下の点を心がけ、愛猫が快適に過ごせる環境を整えましょう。
- こまめな掃除と換気でハウスダストを除去する
- 空気清浄機を設置する
- 猫の近くでタバコを吸わない(受動喫煙の防止)
- 香りの強い芳香剤や消臭スプレー、香水の使用を控える
- 粉じんの少ない猫砂を選ぶ
- 適切な温度・湿度を保つ
これらの対策は、喘息の猫だけでなく、すべての猫の健康維持に役立ちます。
猫の喘息、飼い主が注意することは?
喘息を持つ猫の飼い主さんは、前述の環境整備に加えて、日々の愛猫の様子を注意深く観察することが何よりも大切です。
咳の回数や呼吸の状態を毎日チェックし、記録しておくと、獣医師との相談時に役立ちます。また、咳や発作の様子をスマートフォンなどで動画撮影しておくと、診察の際に非常に有力な情報となります。少しでも「いつもと違う」「呼吸が苦しそう」と感じたら、自己判断せず、かかりつけの動物病院に相談してください。定期的な通院で、症状をしっかりコントロールしていきましょう。
猫の喘息、かかりやすい猫種は?
猫の喘息は、特定の猫種だけに発症する病気ではありませんが、データ上はシャム猫やそのミックス、日本猫での発生がやや多いと報告されています。
年齢は2〜8歳くらいの若い成猫での発症が多い傾向にありますが、どの猫種、どの年齢の猫でも発症する可能性があります。猫種に関わらず、すべての猫で注意が必要な病気といえるでしょう。
愛猫のわずかな異変に気づいてあげることが大切!
猫の喘息は、発作が起きていない時は無症状であることが多く、飼い主さんが気づきにくい病気の一つです。「毛玉を吐こうとしているだけ」と思っていたら、実は苦しい喘息のサインだったというケースも少なくありません。
喘息も他の病気と同様に、早期発見と早期治療が、症状の悪化を防ぎ、愛猫のQOL(生活の質)を保つ鍵となります。日頃から愛猫の様子をよく観察し、スキンシップを大切にすることで、「いつもと違う」というわずかな変化に気づくことができます。気になる症状が見られたら、迷わず動物病院を受診しましょう。