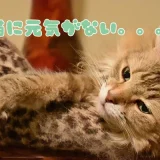「最近、愛猫が便をしていない」「トイレにいる時間が長い気がする」「なんだか苦しそうにいきんでいる」…そんな様子が見られたら、猫が便秘を起こしているサインかもしれません。
猫の便秘は、放置すると食欲不振や嘔吐につながり、重篤な病気の原因になることもあります。症状や原因、解消法についての正しい知識を身につけ、もしもの時に落ち着いて対応できるようにしましょう。
この記事では、猫の便秘について原因からご家庭でできる対策まで詳しく解説します。
猫の便秘、原因は?
食事内容や水分不足
運動不足
排便時の痛みや不快感
ストレス
薬の副作用
病気やケガ
体質
猫の便秘は、便に含まれる水分が減って硬くなり、腸内をスムーズに移動できなくなることで起こります。その原因は、水分不足や食事内容、運動不足といった生活習慣から、ストレス、病気、体質など、様々な要因が考えられます。
食生活のかたより
水分摂取量が不足すると、便が硬くなり便秘の直接的な原因となります。また、食物繊維(可溶性・不溶性繊維)の少ないフードや、毛や骨、異物などを飲み込んでしまった場合も、腸の動きが妨げられ、便秘を引き起こすことがあります。
運動不足
運動不足は、腸のぜん動運動を鈍らせる大きな原因です。適度な運動は、便を押し出すために必要なお腹の筋力を維持するだけでなく、消化器官の働きを司る自律神経を整える効果も期待できます。
排便時の痛み
関節炎などで排便の姿勢が辛い、肛門周りに傷や炎症がある、または腸内に異物があるといった理由で排便時に痛みを感じると、猫は排便を我慢してしまいます。我慢して便が腸内に長くとどまると、さらに水分が吸収されて便が硬くなり、悪循環に陥ります。
ストレス
猫は非常にデリケートな動物で、精神的なストレスが便秘につながることがあります。「引っ越しによる環境の変化」「トイレが汚れている、場所が変わった」「騒音や来客」など、些細なことでもストレスの原因になり得ます。
抗生物質の影響
病気の治療で使われる鎮痛剤、抗コリン剤、抗がん剤などの一部の薬は、副作用として腸の動きを抑制し、便秘を引き起こすことがあります。
腸の閉塞
腸内にポリープや腫瘍ができていたり、「会陰(えいん)ヘルニア」や「巨大結腸症」といった病気を発症していたりすると、物理的や神経学的異常による消化管運動機能低下により便が通りにくくなり、頑固な便秘の原因となります。
その他
加齢により消化機能や筋力が低下した10歳以上の高齢猫や、毛づくろいで多くの毛を飲み込みやすい長毛種の猫などでは便秘になりやすくなることが予想されます。猫で多い慢性腎臓病のような疾患でも便秘の併発は多いです。
猫の便秘、症状は?
2日以上排便がない
トイレで苦しそうにいきむ・吐く
硬くて小さいコロコロの便
1日に何度もトイレに行く
お腹が張っている、触ると嫌がる
少量の下痢のような便が出る
猫が便秘のときに見せる症状には、上記のようなものがあります。特に「2〜3日以上、便が出ていない」「お腹を触ると硬い感じがする」場合は、便秘の可能性が高いでしょう。
猫の便秘、嘔吐もする?
はい、猫は便秘が悪化すると嘔吐することがあります。これは、腸内に溜まった便が胃や腸を圧迫し、食べたものが逆流しやすくなるために起こります。
便秘による嘔吐は、食欲不振や脱水症状を併発し、猫の体を著しく衰弱させる危険なサインです。日頃からトイレをこまめに掃除して便の回数や状態をチェックし、スキンシップを兼ねてお腹の様子を触って確認する習慣をつけましょう。
猫の便秘、こんな時は病院へ
猫は不調を隠す習性があるため、飼い主が気づいたときには症状が進行していることも少なくありません。便秘を放置すると「巨大結腸症」など、手術が必要な病気に発展することもあります。以下のような症状が見られたら、すぐに動物病院を受診しましょう。
- 3日以上まったく便が出ていない
- 嘔吐や食欲不振がある
- ぐったりして元気がない
- お腹を触るとひどく嫌がる、または痛そうに鳴く
- トイレで鳴き叫ぶなど、明らかに苦しそう
動物病院では、触診やレントゲン検査などで便秘の原因を特定し、必要に応じて投薬や浣腸などの処置を行います。背景に何らかの病気が隠れている場合は、その治療を優先することで便秘の解消につながります。
何日も便秘の猫に、薬は効く?
何日も続くような頑固な便秘には、動物病院で処方される薬が有効です。自己判断で人間用の下剤やサプリメントを与えるのは、中毒や重度下痢を起こす可能性があり非常に危険ですので、絶対にやめましょう。
動物病院では、猫の状態に合わせて以下のような薬が処方されます。
- 下剤:便を柔らかくすることを主に目的としたものを使用します。強いエビデンスまではないですが、大腸の動きを促進することを期待して錠剤タイプを使用することもあります。最近では整腸剤を併用することも効果が期待されています。
- 浣腸:即効性がありますが、猫にとっては負担も大きいため、基本的には動物病院で獣医師が行う処置です。
薬を使用する際は、必ず獣医師の指示に従い、用法・用量を守ってください。
猫の便秘、日頃からできる解消法は?
食事と水分補給を見直す
ストレスのない環境を整える
こまめな毛玉対策
便秘は治療も大切ですが、日頃から予防することが最も重要です。日常生活で取り入れられる予防・解消法をご紹介します。
キャットフードを変える、新鮮な水を与える
便秘予防の基本は、十分な水分補給とバランスの取れた食事です。いつでも新鮮な水が飲めるよう、複数の場所に水飲み場を設置したり、こまめに水を交換したりする工夫をしましょう。特に夏場は水が傷みやすいので注意が必要です。
食事については、ウェットフードは水分補給に優れていますが、製品によっては食物繊維が少ないものもあります。一方、ドライフードは食物繊維が豊富な製品が多い傾向にあります。便秘気味の猫には、水分補給にウェットフードを活用しつつ、食物繊維が豊富に配合された便秘ケア用のドライフードを食事のメインにするのがおすすめです。急にフードを変えると食べないこともあるため、今までのフードに少しずつ混ぜながら切り替えていきましょう。完全に切り替えなくても現在の食事中の食物繊維の割合を増やすだけで効果を示すこともあります。
ストレスを解消する
猫のストレス原因は主に「運動不足」と「生活環境への不満」です。キャットタワーを設置して上下運動ができるようにしたり、おもちゃで定期的に遊んであげたりして、運動不足を解消しましょう。
また、「トイレは常に清潔か」「安心してくつろげる場所があるか」「騒がしくないか」など、猫の目線で生活環境を見直すことも大切です。キレイ好きな猫種の場合、少しの汚れも大きなストレスになります。
毛玉対策をする
猫は毛づくろいで飲み込んだ毛が消化管内に溜まり、「毛球症(もうきゅうしょう)」となって便秘の原因になることがあります。特に長毛種は注意が必要です。日頃からこまめにブラッシングをして抜け毛を取り除き、飲み込む毛の量を減らしてあげることが重要です。
正しい解消法を実践してあげよう!
猫の便秘は、多くの飼い主が経験する身近なトラブルです。しかし、その裏には病気が隠れている可能性もあり、決して軽視はできません。
大切なのは、日頃から愛猫の様子をよく観察し、便の回数や状態、食欲、元気の有無など、小さな変化に早く気づいてあげることです。この記事で紹介した原因や症状、解消法を参考に、ご家庭でできるケアを実践しつつ、少しでも不安な点があれば、迷わずかかりつけの動物病院に相談してください。それが愛猫の健康を守る一番の近道です。