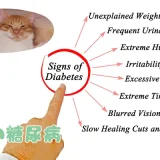愛猫がしきりに耳をかゆがったり、頭を振ったりしていませんか?その行動、もしかしたら「耳疥癬(みみかいせん)」、通称「耳ダニ」が原因かもしれません。耳ダニは猫の耳の中に寄生し、強いかゆみを引き起こす厄介な寄生虫です。
放置すると外耳炎や中耳炎に発展し、愛猫に大きな苦痛を与えてしまいます。また、非常に感染力が強いため、多頭飼いの場合は他の猫にもあっという間に広がってしまう可能性があります。
この記事では、猫の耳ダニの具体的な症状から、動物病院での駆除・治療方法、使用される薬、治療費の目安、そして家庭でできる効果的な予防対策まで、獣医師監修のもと詳しく解説します。
猫の耳ダニとは?どんな症状がでるの?
猫の耳ダニ症は、主に「ミミヒゼンダニ」という0.3~0.4mmほどの非常に小さなダニが、耳の穴から鼓膜までの間(外耳道)の皮膚表面に寄生して起こる感染症です。このダニは耳垢や皮膚の分泌物をエサにして繁殖します。
- 頻繁に頭を激しく振る
- 後ろ足で耳をしきりに掻く
- 壁や床、家具などに耳を擦りつける
- 大量の黒く乾燥した耳垢が出る
- 耳から異臭がする
- 耳を触られるのを極端に嫌がる
ミミヒゼンダニに寄生されると、その糞や分泌物に対するアレルギー反応で、猫は耐えがたいほどの激しいかゆみに襲われます。上記チェックリストのような行動が見られたら、耳ダニに感染している可能性が高いでしょう。
特に、黒くてカサカサした、まるでコーヒーの出がらしのような耳垢が大量に出るのが最大の特徴です。この特徴的な耳垢により、耳の中を観察することで耳ダニの感染を疑うことができます。
ミミヒゼンダニは繁殖力が非常に強く、放置すると耳の中で爆発的に増殖します。その結果、慢性の外耳炎を引き起こし、さらに炎症が奥へと広がると中耳炎や内耳炎にまで発展する恐れがあります。重症化すると平衡感覚に異常をきたし、歩行に障害が出ることもあるため、早期発見・早期治療が何よりも重要です。
耳ダニの感染原因は?
猫の耳ダニは、すでに感染している他の動物との接触によってうつります。主な感染経路は、耳ダニに感染した母猫から子猫へ、あるいは同居している猫同士での接触です。
また、屋外に出る習慣のある猫は、他の感染猫と接触する機会があるため、感染リスクが高まります。愛猫が屋外と室内を自由に行き来している場合は、こまめに耳の中をチェックし、行動に変化がないか注意深く観察してください。
猫の耳ダニ、駆除・治療の方法は?
もし愛猫に耳ダニの症状が見られたら、自己判断で市販薬などを使わず、速やかに動物病院を受診してください。獣医師が耳垢を顕微鏡で検査し、耳ダニの成虫や卵を確認して診断を確定します。
治療は、まず耳道を傷つけないように専用の洗浄液で耳の中をきれいに洗い、大量の耳垢やダニを除去します。その後、駆除薬を投与してダニを駆除するのが一般的な流れです。耳を掻き壊して細菌感染を起こしている場合は、抗生物質の投与も併せて行います。
猫の耳ダニ治療を成功させるためのポイントは、「ダニのライフサイクルに合わせた継続的な駆除」「同居猫の同時治療」「耳垢の徹底的な除去」の3つです。駆除薬は成虫には効果がありますが、卵には効きにくいため、卵が孵化するタイミングに合わせて、少なくとも3週間〜1ヶ月程度の継続的な治療が必要になります。
多頭飼いしている場合は全頭の治療が必須!
猫を多頭飼いしているご家庭では、特に注意が必要です。耳ダニは非常に感染力が強いため、1匹の症状に気づいた時点で、他の猫にもすでに感染していると考えるべきです。
症状が出ていない猫がいても、1匹だけ治療してもすぐに他の猫から再感染してしまいます。必ず同居している全ての猫を動物病院に連れて行き、同時に検査と治療を開始してください。
猫の耳ダニ、治療にはどういう薬を使うの?
猫の耳ダニ(ミミヒゼンダニ)の駆除薬として、現在主流となっているのは、首筋(肩甲骨の間)に液体を垂らすスポットオンタイプの滴下薬です。「セラメクチン」や「イベルメクチン」といった成分が含まれた薬が用いられます。
これらの薬は、猫が自分で舐められない場所に投与することで、皮膚から吸収されて血流に乗り、耳の中にいるダニを駆除する効果があります。
また、耳ダニ感染は激しいかゆみから外耳炎を併発しているケースがほとんどです。そのため、かゆみや炎症を抑えるための点耳薬を併用して外耳炎の治療も行います。
飼い主さんが綿棒などを使って耳の奥まで掃除しようとすると、かえって耳道を傷つけたり、耳垢を奥に押し込んでしまったりする危険があります。耳の洗浄や処置は、必ず動物病院で獣医師に行ってもらいましょう。
猫の耳ダニ、治療費はいくら?
猫の耳ダニ治療にかかる費用は、猫の症状の重さや動物病院によって異なりますが、初回の通院で3,000円~5,000円程度(診察料、耳垢検査、耳処置、駆虫薬など)が目安となります。
その後、完治するまで複数回の通院が必要になることが多く、外耳炎の治療薬などが追加されると、総額では1万円~数万円になることもあります。ペット保険に加入している場合は、補償対象となるか確認してみましょう。
愛猫の行動の変化に早く気づき、症状が軽いうちに治療を開始できれば、通院回数も少なく済み、結果的に治療費を安く抑えることができます。普段と違う様子が見られたら、迷わず動物病院へ相談することが大切です。
猫の耳ダニ、対策はどうすればいいの?
猫の耳ダニを予防するには、感染源との接触を断つことが最も重要です。したがって、最も効果的な対策は「完全室内飼いを徹底すること」です。外に出なければ、他の感染猫から耳ダニをもらってくるリスクを大幅に減らせます。
やむを得ず外出する機会がある猫や、すでに耳ダニの寄生歴がある猫の場合は、動物病院で処方される駆除薬を定期的に投与して予防するのが安心です。
また、日頃のスキンシップを兼ねたブラッシングや耳のチェックも、耳ダニの予防と早期発見に繋がります。特徴的な黒い耳垢がないか、かゆがっていないかなどを定期的に確認する習慣をつけましょう。
室内の環境整備も予防の一環
耳ダニは猫から離れても数日間は生存できるため、室内の環境を清潔に保つことも大切です。飼い主さんの衣服について外から持ち込まれる可能性もゼロではありません。愛猫が使っているベッドや毛布、カーペット、ソファなどをこまめに掃除・洗濯し、ダニが繁殖しにくい環境を維持しましょう。
気になる初期症状は獣医師に相談してみる
「最近、愛猫がよく耳をかく」「耳のニオイが気になる」といった、飼い主さんだからこそ気づける愛猫のささいな変化や初期症状を見逃さないでください。それが病気の早期発見の第一歩となります。
様子がおかしいと感じたら、スマートフォンなどでその行動を動画に撮っておくと、診察の際に獣医師に状況が伝わりやすくなります。自己判断はせず、どんな些細なことでもまずはかかりつけの獣医師に相談しましょう。
猫の耳ダニ対策は、感染させない予防と、日々の観察による早期発見が鍵となります。室内環境を清潔に保ち、愛猫とのコミュニケーションの中で健康状態をチェックする習慣をつけ、大切な家族を耳ダニの苦痛から守ってあげてください。