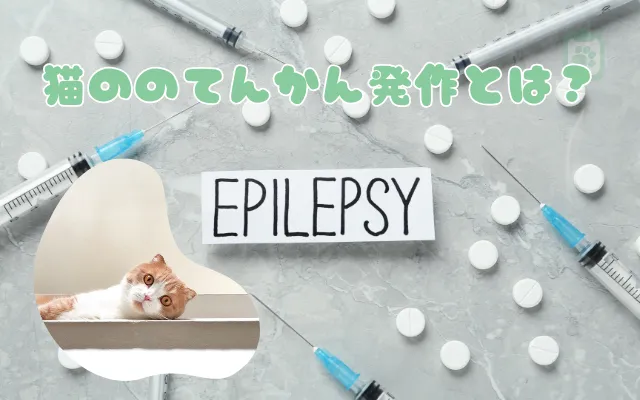猫も人間と同じように、「てんかん」という脳の病気を発症することがあります。突然愛猫がけいれんを起こしたら、飼い主さんはとても驚いてしまいますよね。この記事では、猫のてんかんについて、具体的な症状や原因、動物病院での治療法、費用、そして寿命との関係まで、飼い主さんが知っておきたい情報を詳しく解説します。
猫がかかる「てんかん」ってどんな病気?症状は?
てんかんとは、脳の神経細胞が異常に興奮することで、てんかん発作(けいれん、意識障害など)を繰り返し引き起こす病気です。発作は脳の異常な電気信号によって引き起こされ、猫自身の意思とは関係なく突然起こります。
猫にてんかん発作が起きると、体のコントロールを失い、以下のような様々な症状が見られます。
- 全身または手足が突っ張り、硬直する
- ガタガタと震えるようなけいれんを起こす
- よだれを大量に出したり、口から泡を吹いたりする
- 意識を失う
- おしっこやうんちを漏らしてしまう(失禁・失便)
発作は数分でおさまることが多く、発作後は何事もなかったかのように普段通りに振る舞うこともあります。しかし、てんかんは自然治癒する病気ではないため、放置は禁物です。「てんかんかもしれない」と感じたら、すぐに動物病院で獣医師に相談しましょう。なお、猫のてんかんの発生率は1%未満と、犬に比べると低いといわれています。
猫のてんかんと症状が似ている病気も
てんかん発作のような症状は、他の病気が原因で起こることもあります。特に症状が似ている病気として、以下のものが挙げられます。
- ナルコレプシー:感情の高ぶりなどをきっかけに、突然強い眠気に襲われ、眠り込んでしまう病気。意識を失います。
- カタプレキシー:意識ははっきりしているのに、突然全身の力が抜けて、ぐったりと動けなくなってしまう病気。
てんかんが激しいけいれんや硬直を伴うことが多いのに対し、これらの病気は全身の脱力が見られるという違いがあります。しかし、症状だけで飼い主さんが判断するのは非常に危険です。原因を特定し、適切な治療を受けるためにも、愛猫の様子に異常があれば、必ず獣医師の診察を受けましょう。
猫のてんかん、原因とは?
猫のてんかんは、原因によって大きく2つに分けられます。原因が特定できる「症候性(しょうこうせい)てんかん」と、原因不明の「特発性(とくはつせい)てんかん」です。
症候性てんかんの主な原因には、以下のようなものがあります。
- 脳の病気:脳腫瘍、脳炎、水頭症、脳梗塞など
- 頭部の外傷:交通事故や落下事故による脳の損傷
- 代謝性の異常:肝臓や腎臓の病気、低血糖など
- 中毒:毒物や化学物質の摂取
- 感染症:猫伝染性腹膜炎(FIP)など
原因によって治療法が大きく異なるため、まずは精密検査で原因を突き止めることが重要です。自己判断で様子を見ることは絶対にやめましょう。
猫のてんかん、どういう治療をするの?
猫のてんかん治療は、その原因に応じて行われます。
- 原因となる病気の治療:脳腫瘍や内臓疾患など、てんかんの原因が特定できた場合は、まずその病気の治療を優先します。原因となっている病気が改善することで、てんかん発作が治まることがあります。
- 抗てんかん薬による治療:原因が特定できない特発性てんかんや、原因疾患の治療が難しい場合は、発作を抑えるための「抗てんかん薬」を投与します。この薬は、てんかんを完治させるものではなく、発作の回数を減らしたり、症状を軽くしたりすることを目的としています。
抗てんかん薬は、長期的に、毎日決まった時間に投薬を続けることが非常に重要です。副作用が出る可能性もあるため、獣医師の指示をよく守り、愛猫の様子を注意深く観察しましょう。自己判断で薬の量を変更したり、投薬を中断したりすると、かえって発作を悪化させる危険性があります。
猫のてんかん、治療費用はどれくらい?
てんかんの治療費用は、検査内容や治療法によって大きく異なります。まず原因を特定するために、以下のような検査が行われることが一般的です。
- 血液検査・尿検査:数千円~2万円程度
- レントゲン検査:数千円~1万円程度
- MRI・CT検査:5万円~10万円以上(全身麻酔が必要)
これらの検査に加えて、継続的な抗てんかん薬の薬代(月に数千円~)や定期的な診察料が必要になります。治療が長期にわたる場合、総額で数十万円以上になることも珍しくありません。高額な治療費に備え、万が一の場合を考えてペット保険への加入を検討しておくのも一つの方法です。
猫がてんかんになってしまった・・・寿命は?
「てんかんになったら、寿命は短くなってしまうの?」と心配になる飼い主さんは多いでしょう。しかし、てんかんという病気そのものが、直接猫の寿命を縮めることは稀です。
獣医師の指導のもとで適切な治療を続け、発作をコントロールできていれば、健康な猫と同じように天寿を全うできる可能性は十分にあります。ただし、注意したいのが発作中の事故です。けいれんによって高い場所から落下したり、家具の角に頭をぶつけたりして、命に関わる大怪我をしてしまう危険性があります。愛猫の安全を守るため、室内環境を整えてあげましょう。
猫のてんかん、対策は可能?
原因が多岐にわたるため、猫のてんかんを完全に予防することは困難です。しかし、発症のリスクを減らすために飼い主ができる対策はあります。
- ワクチン接種:感染症が原因のてんかんを防ぐため、子猫のうちに混合ワクチンをきちんと接種しましょう。
- 完全室内飼いの徹底:交通事故による頭部外傷や、他の猫からの感染症のリスクを減らすことができます。
- 定期的な健康診断:てんかんの原因となりうる内臓の病気などを早期発見・早期治療するために、半年に1回程度は健康診断を受けさせましょう。
日頃から愛猫の健康状態に気を配ることが、結果としててんかんの予防に繋がります。
てんかんは自然治癒を望まず、早めの治療を。脳に障害が残る可能性も
もし愛猫がてんかん発作を起こしたら、慌てず冷静に対処することが大切です。まずは猫の体を毛布やタオルで優しく包み、怪我をしないように静かで安全な場所へ移動させましょう。発作は通常1~2分で治まりますが、発作が5分以上続く場合や、短い間隔で発作を繰り返す場合(てんかん重積状態)は、命の危険があります。すぐに動物病院へ連絡し、指示を仰いでください。発作を繰り返すと脳にダメージが蓄積し、後遺症が残る可能性もあるため、早期治療が何よりも肝心です。
発症=死ではない!愛する猫がてんかんになっても、諦めず治療を
愛猫が突然けいれんを起こす姿を見るのは、飼い主にとって非常につらく、怖いものです。しかし、てんかんは「発症=死」に直結する病気ではありません。適切な治療を根気よく続けることで、発作をコントロールし、穏やかな生活を送ることは十分に可能です。診断された場合は、決して諦めずに、かかりつけの獣医師とよく相談しながら、愛猫にとって最善の治療を続けていきましょう。