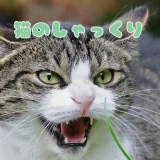愛猫の目元に悩みを抱える飼い主さんは多いのではないでしょうか。特に「目やに」は、猫の健康状態を知る上で重要なサインとなり、多くの飼い主さんにとって悩みの種です。
✓なんでこんなに目やにが出るんだろう
✓何か病気なのかな?
✓ちゃんとした目やにの取り方とかあるの?
このような疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。「元気そうだから大丈夫」「たかが目やに」と軽く考えてしまうこともあるかもしれません。
しかし、猫の目やには、見過ごせない病気のサインである可能性も潜んでいます。この記事では、猫の目やにの様々な原因から、安全な取り方、そして危険な病気のサインの見分け方まで詳しく解説します。
愛猫のキラキラした瞳を守るため、目やにについて正しい知識を身につけましょう。
猫の目やにの原因は?黒い目やには大丈夫?
猫の目やにの正体は、涙に含まれる粘液が、目に入ったホコリや古い細胞、抜け毛などを絡め取ってできた老廃物です。
猫の目やにの主な原因として、まずは心配のいらない生理的なものが挙げられます。健康な猫でも新陳代謝によって少量の目やにが出るのはごく自然なこと。特に、黒い目やにや茶色っぽい乾燥した目やには、涙の成分が空気に触れて酸化したものであることが多く、少量であれば生理的なものなので基本的には大丈夫です。この場合は病気の心配はほとんどありません。
また、寝起きに目やにがついていることもよくあります。これは、睡眠中にまばたきが減ることで、涙や分泌物が正常に排出されずに目頭に溜まってしまうのが原因です。これも少量であれば特に問題はありません。
猫の目やに、病気や外傷のサインは?
しかし、すべての目やにが安心というわけではありません。次に挙げるようなサインが見られる場合、病気や外傷が猫の目やにの原因となっている可能性があります。異常を感じたら、速やかに動物病院を受診しましょう。
結膜炎などの感染症
結膜炎などの細菌やウイルスに感染している場合、免疫反応によって膿が混ざるため、黄色や緑色のドロッとした粘り気のある目やにが出ます。これは病気のサインとして非常に分かりやすい特徴です。ほかにも、目の充血や腫れ、涙の量が増えるといった症状を伴う場合は、猫カゼ(猫ヘルペスウイルス感染症、猫カリシウイルス感染症)やクラミジアなどの感染症が疑われます。時間が経つと、目やにの色が赤茶色に変化することもあるため注意が必要です。
目に傷がついている
猫同士のケンカや、自分で目をこすってしまうことなどで目に傷がつく外傷も、目やにの原因になります。目やにとともに、透明でサラサラした涙が大量に出る、目をしょぼしょぼさせて痛がる、といったサインが見られる場合は角膜炎や角膜潰瘍の可能性があります。特に片目だけに症状が出ている場合は、外傷を疑いましょう。放置すると猫がさらに目を傷つけ、重症化する恐れがあります。
流涙症
常に涙があふれて目の周りが濡れている場合、「流涙症(りゅうるいしょう)」という病気が考えられます。これは、涙の生産量が過剰になったり、涙を鼻に排出する鼻涙管(びるいかん)が詰まったりすることが原因で起こります。流涙症自体が直接的な病気のサインであり、放置すると涙で濡れた部分の毛が茶色く変色する「涙やけ」や、湿気による皮膚炎を引き起こすことがあります。
猫の目やに、正しい取り方を教えて!
病的な原因ではなく、生理的な猫の目やにであれば、ご自宅でのケアが基本となります。固まってしまう前に、こまめに拭き取ってあげるのが理想です。
目やにを取る際は、まずぬるま湯で湿らせたコットンやガーゼを用意します。乾いたティッシュや硬い布は皮膚を傷つける可能性があるため避けましょう。正しい取り方のポイントは、力を入れずに優しく拭き取ることです。目頭から目尻に向かって、そっと汚れを拭います。固まって取れにくい場合は、湿らせたコットンを数秒当ててふやかしてから取ると、猫への負担が少なくなります。
人用のウェットティッシュは、アルコールや香料が含まれていることがあるため使用は避けてください。必ずペット用か、アルコールフリーのものを選びましょう。ゴシゴシこするのは絶対にNGです。目の周りのデリケートな皮膚を傷つけたり、眼球を傷つけたりする危険があります。
気になる初期症状は獣医師に相談してみる
猫の目やには、時に重大な病気の初期症状であるため、飼い主さんが「いつもと違う」と感じるサインを見逃さないことが非常に重要です。「目やにの色がおかしい」「量が急に増えた」「心配だけど重症なのかわからない…」といった、飼い主さんだからこそ気がつく初期症状は、決して放置してはいけません。
普段から愛猫とのスキンシップを兼ねて目の状態をチェックし、少しでも異常を感じたら、まずは動物病院へ相談しましょう。その際、目やにの状態や、猫が目を気にする様子などをスマートフォンで動画撮影しておくと、獣医師が診断する際の貴重な情報となります。些細なことと思わずに、専門家である獣医師に相談することが、愛猫の目の健康を守る第一歩です。