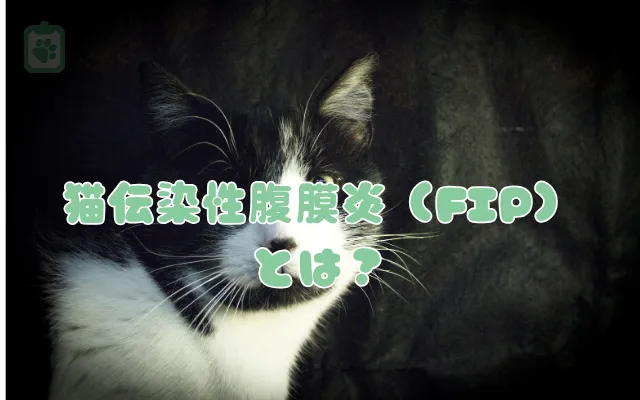猫伝染性腹膜炎(FIP)は、猫コロナウイルスが突然変異して引き起こされる病気で、一度発症すると致死率が非常に高く、多くの飼い主さんを悩ませる深刻な病気です。
この記事では、猫の伝染性腹膜炎(FIP)について、その特徴的な症状、発症の原因、診断方法、最新の治療法、そして飼い主としてできる対策や注意点を詳しく解説します。
猫伝染性腹膜炎・FIP、症状は?
- 腹水や胸水(体液がたまる)
- 持続する発熱
- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)
- 食欲不振・元気消失
FIPを発症すると、全身の血管に炎症(血管炎)が起こります。この血管炎により、タンパク質を多く含んだ液体が血管から漏れ出し、お腹(腹水)や胸(胸水)に溜まっていきます。また、肝臓の機能が低下することで黄疸が見られ、皮膚や白目、尿が黄色くなるのも特徴的な症状です。
猫伝染性腹膜炎の症状は、体液が溜まる「ウェットタイプ」と、内臓にしこり(肉芽腫)ができる「ドライタイプ」の2種類に大別されます。
ウェットタイプ(滲出型)
- 腹水によるお腹の膨らみ
- 胸水による呼吸困難
- 元気消失、発熱、黄疸
ウェットタイプはFIPの中でも進行が早く、腹水でお腹が膨れたり、胸水で肺が圧迫されて呼吸が苦しくなったりといった症状が顕著に現れます。食欲不振や持続的な発熱、黄疸などもみられ、急激に状態が悪化することがあります。
ドライタイプ(非滲出型)
- 食欲不振・体重減少
- 臓器の肉芽腫(にくげしゅ)
- 神経症状(ふらつき、麻痺、けいれん)
- 目の症状(ぶどう膜炎など)
ドライタイプは、腎臓、肝臓、腸、脳、眼などの様々な臓器に肉芽腫という炎症性のしこりができるのが特徴です。脳や脊髄に病変が及ぶと、歩行困難やけいれん発作などの神経症状が、目に及ぶと視力障害や失明に至ることもあります。ウェットタイプから移行したり、症状がゆっくり進行したりするため診断が難しいケースも少なくありません。
猫伝染性腹膜炎・FIP、原因は?
猫腸コロナウイルスの突然変異
猫伝染性腹膜炎(FIP)の原因は、多くの猫が持っている病原性の低い「猫腸コロナウイルス」が、猫の体内で強毒性の「猫伝染性腹膜炎ウイルス(FIPV)」に突然変異することです。
猫腸コロナウイルスの接触感染
猫腸コロナウイルス自体は、感染した猫の便や唾液などを介して他の猫にうつります。トイレの共有やグルーミング、食器の共用などが主な感染経路です。ほとんどの場合、軽い下痢程度の症状で済むか、無症状で経過します。
突然変異によるFIPの発症
なぜウイルスが突然変異を起こすのか、その正確なメカニズムはまだ解明されていません。しかし、ストレスや他の病気による免疫力の低下、遺伝的素因などが引き金になると考えられています。特に、3ヶ月~3歳頃の子猫や10歳以上の高齢猫、多頭飼育環境の猫はFIPを発症するリスクが高いとされています。
猫伝染性腹膜炎・FIP、診断方法は?
猫伝染性腹膜炎(FIP)の確定診断は非常に難しく、症状、血液検査、レントゲン・エコー検査、溜まった体液の検査、抗体価検査などの複数の結果を総合的に評価して診断します。
症状がある場合の診断
腹水や黄疸などの典型的な症状が見られる場合、まず血液検査を行い、炎症反応や高グロブリン血症(高タンパク血症の一種)の有無を確認します。腹水や胸水が溜まっていれば、それを採取して性状を調べる検査が診断の大きな助けとなります。これらの所見が揃えば、FIPの可能性が極めて高いと仮診断されます。
症状がない場合の診断
無症状の猫に対して、FIPを発症しているかどうかを診断することは困難です。コロナウイルスの抗体価検査は、あくまで「過去にコロナウイルスに感染したことがあるか」を示すもので、FIPの発症を直接証明するものではありません。健康な猫でも高い数値が出ることがあるため、この検査だけでFIPと診断することはできません。
猫伝染性腹膜炎・FIP、治療はどのように行う?
- ステロイド剤(抗炎症作用)
- インターフェロン(免疫調整)
- 支持療法(栄養補給、対症療法など)
かつてFIPは治療法のない不治の病とされていましたが、近年では治療の選択肢も増えつつあります。ただし、現在でも完治は非常に難しく、治療の主な目的は、炎症を抑えて症状を緩和し、猫のQOL(生活の質)を維持することになります。
治療の中心となるのは、強力な抗炎症作用を持つステロイド剤です。これにより血管の炎症を抑え、一時的に症状を改善させます。その他、免疫を調整するインターフェロンや、二次感染を防ぐための抗生剤が使われることもあります。※近年、海外ではウイルスの増殖を直接抑える新薬による治療報告もありますが、日本では未承認薬であり、治療を受ける際は獣医師との十分な相談が必要です。
猫伝染性腹膜炎・FIP、対策はできる?
FIPの発症を100%防ぐ確実な予防法はありませんが、原因となる猫腸コロナウイルスの感染リスクや、発症の引き金となる要因を減らすための対策は可能です。
最も重要な対策は、猫に過度なストレスを与えないことです。清潔で静かな飼育環境を維持し、たくさん遊んであげるなど、愛猫が安心して暮らせるように心がけましょう。また、栄養バランスの取れた食事で免疫力を高く保つことも、FIPの発症予防につながります。こちらの記事では免疫力維持におすすめのキャットフードを紹介しています。
猫伝染性腹膜炎・FIP、飼い主が注意することは?
- ストレスの少ない生活環境の維持
- 日々の健康チェック(食欲・元気・排泄物)
- 完全室内飼育の徹底
- 多頭飼育の場合はトイレを清潔に保つ
FIPの発症リスクを抑え、万が一の際に早期発見するために、飼い主さんの日頃の観察が非常に重要です。他の猫との接触によるコロナウイルス感染を防ぐためにも、完全室内飼育を徹底しましょう。特に多頭飼育の場合は、トイレの数を増やして常に清潔に保ち、食器を分けるなどの工夫で感染拡大のリスクを減らすことができます。
猫伝染性腹膜炎・FIP、かかりやすい猫種は?
- 純血種全般
FIPはどんな猫でも発症する可能性がありますが、遺伝的素因から純血種は発症リスクが高い傾向があるといわれています。特に、アメリカンショートヘア、ペルシャ、ロシアンブルー、アビシニアン、ベンガル、ラグドールなどが好発猫種として挙げられます。ただし、猫種に関わらず、すべての猫で注意が必要な病気です。
わからないことが多い病気
猫伝染性腹膜炎(FIP)は、今なお多くの謎が残る、猫にとって非常に厳しい病気です。しかし、飼育環境を整えてストレスを減らし、免疫力を維持することで、発症のリスクを低減させることは可能です。
愛猫の食欲や元気、お腹の張り、呼吸の状態など、日々の小さな変化に気を配り、少しでも異変を感じたら、すぐに動物病院を受診することが何よりも大切です。正しい知識を持って、愛猫をFIPから守ってあげましょう。