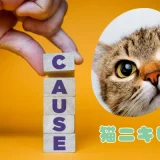「猫エイズ」という言葉を聞いたことがある方は多いかもしれませんが、その実態については誤解や偏見も少なくありません。猫エイズは「猫免疫不全ウイルス感染症(FIV)」という正式名称を持つ病気です。もし愛猫や保護した猫がこのウイルスに感染しているとわかっても、正しい知識があれば、慌てず冷静に対応することができます。
この記事では、飼い主として知っておくべき猫エイズの症状や感染経路、そして最新の治療法や対策について、網羅的に解説します。
猫エイズは人に感染しない
まず最も重要なことは、猫エイズ(FIV)は人には絶対に感染しないということです。猫エイズウイルスは、人間のエイズウイルス(HIV)とは全く異なる種類のウイルスであり、種を超えて感染することはありません。
また、猫同士であっても、流血するほどの激しい喧嘩や交尾がなければ、感染リスクは極めて低いとされています。食器の共有やグルーミングといった日常的な接触で感染する可能性はほとんどありません。この事実を知っておくだけでも、過度な不安から解放され、冷静な判断ができるようになります。
猫エイズの感染経路と症状は?
猫エイズウイルスの主な感染経路は、感染猫との喧嘩による咬傷(こうしょう)です。ウイルスは唾液に多く含まれるため、深い咬み傷から体内へ侵入します。屋外での猫同士の縄張り争いなどが主な原因となるため、特に未去勢のオス猫は注意が必要です。交尾による感染も報告されています。
感染後の症状は、以下のステージをたどって進行します。
- 急性期:感染後数週間から数ヶ月の時期。ウイルスが体内で増殖し、発熱、下痢、リンパ節の腫れなど、風邪のような症状が見られます。多くの場合は軽度で、飼い主が気づかないうちに次のステージへ移行します。
- 無症状キャリア期:急性期の症状が治まると、ウイルスは体内に潜伏し、表面的には健康な状態に見えます。この期間は非常に長く、平均4〜5年、長い場合は10年以上続くこともあります。適切な飼育環境であれば、このまま寿命を迎える猫も少なくありません。
- 発症期(エイズ関連症候群):免疫機能が徐々に低下し始めると、慢性的な口内炎や歯肉炎、治りにくい皮膚炎、下痢、鼻炎などを繰り返すようになります。体重も少しずつ減少していきます。
- エイズ期:免疫機能が著しく低下し、健康な猫なら問題にならないような弱い病原体にも感染してしまう「日和見感染(ひよりみかんせん)」が頻発します。重度の貧血や、リンパ腫などの悪性腫瘍を併発し、最終的には死に至ります。
猫エイズワクチンは現在販売中止に
かつては日本でも猫エイズ(FIV)ワクチンが流通していましたが、2024年現在、国内では販売中止となっています。
販売中止に至った背景には、いくつかの理由があります。
- ウイルスの型が地域によって異なり、ワクチンが全ての型に有効ではなかったこと。
- ワクチン接種後に、注射部位にしこり(ワクチン関連肉腫)が発生するリスクが報告されたこと。
- アナフィラキシーショックなどの強い副反応が見られるケースがあったこと。
これらの理由から、ワクチンの有効性と安全性を考慮した結果、現在は使用されていません。
猫エイズの治療方法は?
猫エイズウイルスそのものを体内から排除する特効薬はなく、根本的な治療は困難なのが現状です。そのため、治療は免疫力を維持し、発症した症状を和らげる「対症療法」が中心となります。
具体的な治療法としては、以下のようなものがあります。
- 各種症状への治療:口内炎や歯肉炎に対する抗生物質や消炎剤の投与、下痢や皮膚炎などに対する薬剤治療。
- 免疫の補助:ネコインターフェロンの注射などを用いて免疫機能をサポートし、ウイルスの増殖を抑制します。
- 栄養管理と支持療法:貧血が進行した場合には輸血を行ったり、食欲不振の際には点滴や栄養補助食を与えたりします。
定期的な健康診断で体調の変化を早期に発見し、その都度適切な治療を行うことが重要です。
猫エイズ、対策方法は?
有効なワクチンがない現在、猫エイズの最も確実な対策は「ウイルスに感染させないこと」です。そのために最も効果的な方法は「完全室内飼育」を徹底することです。
屋外は、他の猫との喧嘩など、感染のリスクに満ちています。室内で暮らすことで、感染機会をほぼゼロにすることができます。すでに多頭飼育しているご家庭でキャリアの猫がいる場合でも、激しい喧嘩をしない関係であれば同居は可能です。ただし、万が一発症すると唾液中のウイルス量が増えるため、食器を分けたり、猫同士の接触を注意深く見守ったりする配慮が必要になる場合があります。
疑わしい場合、すぐに動物病院へ
「最近、口内炎が治りにくい」「下痢を繰り返す」「体重が減ってきた」など、猫エイズを疑う症状が見られたら、自己判断せずに速やかに動物病院を受診し、獣医師の診断を受けてください。
猫エイズは血液検査で簡単に調べることができます。たとえ陽性と診断されても、悲観する必要はありません。近年の獣医療の進歩により、適切なケアと治療を続けることで、QOL(生活の質)を高く保ちながら長生きできる猫が増えています。早期発見と適切なサポートで、愛猫が穏やかに過ごせる時間を最大限に延ばしてあげましょう。