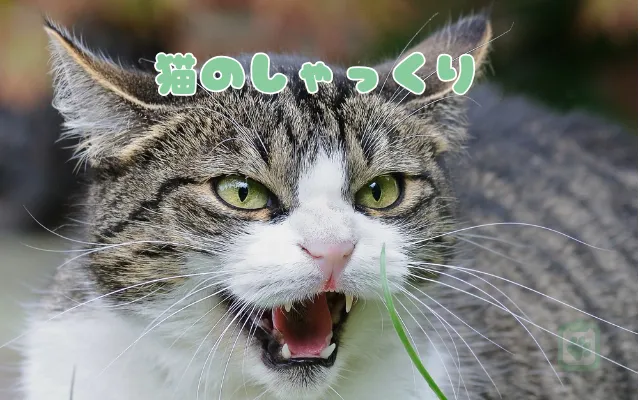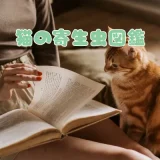猫も人間と同じように「ヒック、ヒック」としゃっくりをします。初めて見る飼い主さんは「苦しそう」「病気かも?」と驚いてしまうかもしれませんが、ほとんどの場合は心配いりません。落ち着いて様子を見てあげましょう。
この記事では、猫のしゃっくりの特徴や考えられる原因、すぐにできる止め方から、しゃっくりが止まらない場合の対策までを詳しく解説します。
猫のしゃっくりの特徴
猫のしゃっくりは、人間のように「ヒック」と小さな音を出したり、お腹や背中がピクッ、ピクッと痙攣するように波打ったりするのが特徴です。特に、成長期の子猫によく見られる仕草で、通常は数分から長くても1日以内には自然に治まります。
ただし、猫のしゃっくりは咳や、毛玉(ヘアボール)を吐き出そうとする仕草と似ているため、見分けがつきにくいことがあります。しゃっくりはリズミカルに続くことが多いのに対し、咳は「ケホッケホッ」と不規則で、毛玉を吐く際はより苦しそうな素振りを見せるのが見分けるポイントです。
猫のしゃっくりの原因
猫のしゃっくりの原因は、人間と同じく横隔膜の痙攣によるものです。横隔膜が何らかの刺激を受けることで、しゃっくりが引き起こされます。主な原因は以下の通りです。
- 早食いや食べ過ぎ:勢いよくフードを食べたり、一度にたくさん食べたりすると、胃が膨らんで横隔膜を刺激します。
- 毛玉(ヘアボール):体内に溜まった毛玉を排出しようとする際に、しゃっくりのような症状が出ることがあります。
- ストレスや興奮:遊んでいる最中などに興奮しすぎると、呼吸が乱れて横隔膜が痙攣することがあります。
- 病気の可能性:まれに、喘息などの呼吸器疾患、胃腸の不調、脳の疾患などが原因でしゃっくりが続くことがあります。
猫しゃっくりの止め方
猫のしゃっくりは生理現象の一環であることが多く、基本的には自然に止まるのを待つのが一番です。無理に止めさせようとすると、かえって猫を驚かせてしまうかもしれません。もし飼い主として何かしてあげたい場合は、以下の対処法を試してみてください。
- 少量の水を飲ませる:水を飲むことで呼吸のリズムが整い、しゃっくりが止まることがあります。
- 優しくマッサージする:猫の胸のあたりを上から下に優しく撫で、リラックスさせてあげましょう。
- おもちゃで気を紛らわせる:軽くおもちゃで遊びに誘い、意識をそらすことで呼吸が整う場合があります。
これらの対処法を試しても、猫が嫌がるそぶりを見せたらすぐに中止してくださいね。
猫のしゃっくりが止まらないときの対策
ほとんどのしゃっくりは一時的なものですが、長時間続いたり、毎日何度も繰り返したりする場合は注意が必要です。特に食後にしゃっくりが頻発するなら、食事の方法に原因があるかもしれません。まずはしゃっくりが起こる前後の行動をよく観察し、原因を探ってみましょう。もし、しゃっくり以外に「元気がない」「食欲不振」「嘔吐」「苦しそうな呼吸」などの症状が見られる場合は、病気が隠れている可能性も考えられるため、早めに動物病院を受診してください。
食事の量の見直し
一度に食べるフードの量が多すぎると、胃が急激に膨らみしゃっくりの原因になります。まずは、パッケージに記載されている1日の給与量が適量かを確認しましょう。目分量ではなく、毎回きちんと計量カップやスケールで測ることが大切です。
1日の総量に問題がない場合は、食事の与え方に問題があるのかもしれません。対策として、1日の食事量は変えずに、食事の回数を2〜3回から4〜5回に小分けにして、一度に食べる量を減らしてあげましょう。
餌の時間間隔調整
食事と食事の間隔が空きすぎると、強い空腹感から早食いにつながってしまいます。猫の早食いはしゃっくりの大きな原因です。この対策としても、前述の通り食事の回数を小分けにすることが有効です。食事の間隔を短くすることで、空腹感を和らげ、落ち着いて食べられるようになります。肥満を防ぐため、1日の総給与量は必ず守るようにしてください。
餌の大きさの見直し
フードの粒が小さいと、猫がよく噛まずに丸呑みしてしまい、早食いや空気の飲み込みにつながります。愛猫がフードを丸呑みしているようであれば、少し粒の大きいフードに切り替えてみるのも一つの手です。自然と噛む回数が増え、食べるスピードがゆっくりになります。
また、食器を「早食い防止用食器」に変えるのも非常に効果的な対策です。食器の内部が凸凹しているため、一度にたくさんの量を口に入れられなくなり、時間をかけて食事をするようになります。
猫のしゃくりが止まらないときは生活習慣の見直しを
猫のしゃっくりのほとんどは、早食いなどの食事習慣が原因で起こる一時的な生理現象です。しゃっくり自体は病気ではありませんが、頻繁に繰り返す場合は、猫が食事で苦労しているサインかもしれません。今回ご紹介した「食事の回数を小分けにする」「フードや食器を見直す」といった対策をぜひ試してみてください。
ただし、しゃっくりが何日も止まらない、他の症状を伴うといった場合は、迷わず動物病院に相談しましょう。日頃から愛猫の様子をよく観察し、ささいな変化にも気づいてあげることが、健やかで楽しいペットライフにつながります。