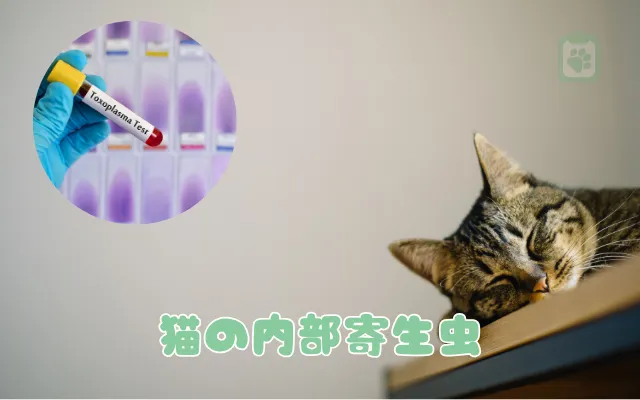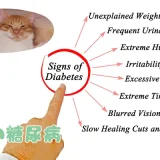猫の体内に棲みつく内部寄生虫は、愛猫の健康を著しく害する可能性があり、発見次第すぐに治療が必要です。
この記事では、猫の内部寄生虫として代表的な「回虫」「サナダムシ」「トキソプラズマ」について、それぞれの症状、感染経路、治療法、そして家庭でできる予防策を詳しく解説します。愛猫の様子に少しでも異変を感じたら、すぐに動物病院へ相談しましょう。
猫に寄生する回虫の感染経路と対策は?
猫回虫は、白から黄白色をしたヒモ状の寄生虫で、成虫は最大で10cmほどになります。主に猫の小腸に寄生し、さまざまな健康問題を引き起こします。
猫回虫の主な症状
猫回虫に感染すると、以下のような症状が見られることがあります。特に子猫の場合は重症化しやすいため注意が必要です。
- 下痢や嘔吐(吐しゃ物の中に虫体が見られることも)
- 食欲不振または異常な食欲
- 体重減少、栄養失調
- 毛ヅヤが悪くなる
- お腹が不自然に膨れる(子猫の場合)
- 咳(幼虫が体内を移動する際に肺を通過するため)
多数の回虫が小腸に寄生すると、腸閉塞を起こす危険性もあります。
猫回虫の感染経路と予防策
猫回虫の主な感染経路は以下の通りです。
- 母子感染:回虫に感染している母猫から、胎盤や母乳を通じて子猫に感染します。
- 経口感染:回虫の卵が含まれた他の猫の糞便を、グルーミングなどで口にしてしまうことで感染します。
- 捕食による感染:回虫の幼虫がいるネズミやゴキブリ、鳥などを捕食することで感染します。
予防策としては、定期的な駆虫薬の投与が最も効果的です。また、室内飼いを徹底し、猫のトイレはこまめに掃除して衛生的に保つことが感染リスクの低減に繋がります。
猫に寄生するサナダムシの感染経路と対策は?
サナダムシ(条虫)は、平たいヒモ状の寄生虫で、多数の片節(へんせつ)が連なった体をしています。猫では特に「瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)」の感染が多く見られます。
サナダムシの主な症状
サナダムシが寄生すると、以下のような症状や行動が見られます。
- 下痢や軟便
- 体重減少(食欲はあるのに痩せていく)
- 肛門付近を気にして舐めたり、床にお尻をこすりつけたりする
- 糞便や肛門周り、寝床などに白ゴマや米粒のような動く片節が付着している
サナダムシの感染経路と治療・予防
サナダムシの感染には、多くの場合ノミが関与しています。サナダムシの卵をノミの幼虫が食べ、そのノミが成虫になった後、猫がグルーミングなどで口にすることで感染が成立します。また、サナダムシに感染したネズミの捕食も感染経路となります。
治療には「プラジクアンテル」という成分を含む駆虫薬(注射または内服薬)が有効です。治療と同時に、再感染を防ぐためにノミの駆除・予防を徹底することが非常に重要です。
猫に寄生するトキソプラズマの感染経路と対策は?
トキソプラズマは、トキソプラズマ原虫という微生物による感染症です。人獣共通感染症(ズーノーシス)としても知られています。
トキソプラズマの症状と感染経路
健康な成猫の場合、感染しても無症状であることがほとんどです。しかし、子猫や免疫力が低下している猫では、発熱、下痢、食欲不振、呼吸器症状や神経症状などを示すことがあります。
主な感染経路は、トキソプラズマに感染しているネズミや鳥、加熱不十分な生肉などを食べることです。また、感染した猫の糞便中に排出されたオーシスト(卵のようなもの)を口にすることでも感染します。
対策と人(特に妊婦の方)への注意点
猫への対策は、室内飼いの徹底と、生肉を与えないことが基本です。人への感染については、猫の糞便から直接感染するケースは稀ですが、特に妊娠中の方が初めて感染すると、胎児に影響が出る可能性があるため注意が必要です。
- 猫のトイレ掃除は毎日行いましょう。(糞便中のオーシストが感染力を持つまでには24時間以上かかります)
- トイレ掃除の際は使い捨て手袋を着用し、終わったら石鹸でよく手を洗いましょう。
- ガーデニングなど土いじりをする際も手袋をしましょう。
妊娠前に抗体を持っているか不安な方は、産婦人科で抗体検査を受けると安心です。
寄生虫はすぐに治療をしてあげてください
猫が内部寄生虫に感染すると、下痢、嘔吐、食欲不振、体重減少など、さまざまな症状が現れます。これらの症状は猫の体力を奪い、免疫力を低下させ、他の病気を引き起こす原因にもなりかねません。そのため、早期発見・早期治療が何よりも大切です。
愛猫を寄生虫から守るためには、動物病院での定期的な健康診断と検便が不可欠です。特に、新しく猫を迎え入れた際や、外に出る習慣のある猫は必ず検査を受けましょう。獣医師の指導のもと、適切な駆虫薬を定期的(月1回など)に投与することが最も確実な予防策となります。
内部寄生虫だけでなく、ノミやマダニといった外部寄生虫の予防も同時に行うことで、サナダムシなどの感染リスクも減らせます。飼い主として正しい知識を持ち、愛猫の健康を守ってあげましょう。