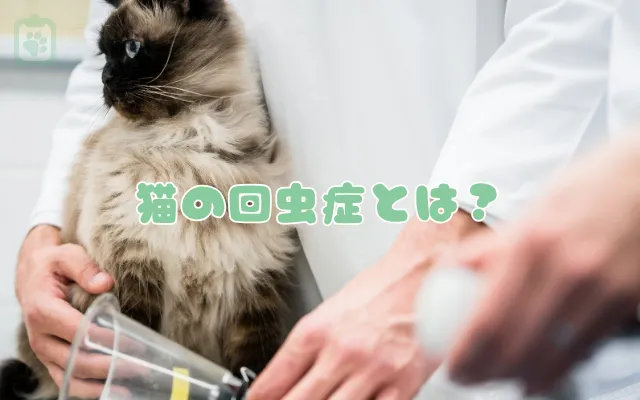猫を飼い始めたばかりの方や、野良猫を保護した方は、愛猫の健康について特に気になることが多いでしょう。中でも「回虫」という寄生虫は、多くの猫が感染する可能性があり、決して珍しいものではありません。
特に、外で暮らしていた経験のある猫では、高い確率で回虫に感染していると考えられています。
この記事では、猫の代表的な内部寄生虫である「猫回虫」について、その症状や危険性、正しい対処法、さらには人への感染リスクまで、飼い主さんが知っておくべき情報を分かりやすく解説します。
猫の回虫症とは?どんな病気?
原因:猫回虫という寄生虫の感染
寄生場所:主に猫の小腸
猫の回虫症とは、「猫回虫」と呼ばれる寄生虫が猫の体内に寄生することで引き起こされる病気です。猫回虫は白〜黄白色で、そうめんや細いヒモのような見た目をしており、成虫になると体長4cm~12cmほどにまで成長します。
猫回虫の成虫は、主に猫の小腸に寄生し、猫が食べたものから栄養を横取りして生きています。一方で、幼虫は筋肉や内臓など、猫の全身の組織に潜んでいることがあります。
感染した猫の便には、猫回虫の卵が大量に含まれていることが多くあります。排泄されたばかりの卵に感染力はありませんが、土の中などで時間が経ち、卵の中で幼虫が発育すると感染能力を持つようになります。
猫回虫の感染経路は?
猫回虫の主な感染経路は、以下の通りです。
- 経口感染:感染力のある猫回虫の卵が付着した土や草、水を口にすることで感染します。毛づくろいの際に、体に付いた卵を舐めとってしまうケースも少なくありません。
- 捕食による感染:猫回虫の幼虫が体内にいるネズミやゴキブリ、鳥などを捕食することで感染します。
- 母子感染(垂直感染):感染している母猫から、母乳を介して子猫に感染します。妊娠中に胎盤を通じて感染するケースもあります。
猫回虫の卵は非常に生命力が強く、乾燥や低温にも耐え、土の中で1年以上も生き続けることがあります。そのため、猫が屋外に出る場合は常に感染のリスクがあると言えるでしょう。
猫回虫は人間に感染する?
猫回虫は人間にも感染する「人獣共通感染症(ズーノーシス)」の一つです。猫と同様に、回虫の卵を何らかの形で口にしてしまう「経口感染」が主な感染ルートです。
特に、公園の砂場で遊んだ後などに手を洗わずに食事をしてしまうことのある幼児は、感染リスクが高いため注意が必要です。猫を撫でた手でそのまま物を食べることも感染の原因となります。
人に感染した場合、「トキソカラ症」と呼ばれ、幼虫が体内を移行することで様々な症状を引き起こします。主な症状は以下の通りです。
- 発熱、咳
- 全身の倦怠感、食欲不振
- 肝臓の腫れ
- 視力低下や視野の異常(眼幼虫移行症)
免疫力が低下している場合は、強いアレルギー反応や神経症状が現れることもあり、決して軽視できない感染症です。
猫回虫の症状は?放置すると悪化する?
下痢や軟便
食欲はあるのに痩せてくる
毛づやが悪くなる
お腹がぽっこり膨れる(腹部膨満)
嘔吐(吐瀉物に虫が混じることも)
咳が出る
猫回虫に感染した場合、上記のような様々な症状が見られます。多数の回虫が寄生すると、栄養失調や発育不良につながります。
健康な成猫の場合、少数寄生では症状がほとんど現れない「不顕性感染」も多いです。しかし、体力の少ない子猫が感染すると、下痢や嘔吐が激しくなり重症化しやすく、多数の虫によって腸閉塞を起こし命に関わることもあるため特に注意が必要です。
猫回虫は自然に治ることはなく、放置すれば症状は悪化します。また、無症状でも便からは虫卵が排出され続けるため、他の猫や人間への感染源となってしまいます。猫の便に白く細いひも状のものを見つけたり、体調に異変を感じたりした際は、すぐに動物病院を受診しましょう。検査の際は、乾燥しないようにビニール袋などに入れた新鮮な便を持参するとスムーズです。
検便による検査費用は、1回あたり1,500円程度が目安です。
回虫の駆除はどうする?必要な費用や駆除薬の価格は?
診察・治療費:2,000円~
駆虫薬(処方薬):1,000円~1,500円程度
動物病院で猫回虫の感染が確認された場合、駆虫薬を投与して治療します。駆虫薬には、皮膚に滴下するスポットタイプや、経口投与する錠剤・シロップタイプなどがあります。
治療にかかる費用は、診察料を含めて2,000円程度からが目安となります。市販の駆虫薬(虫下し)も1,000円~1,500円程度で販売されていますが、猫の体重や健康状態に合わない薬を選ぶと副作用のリスクもあります。安全かつ確実に駆除するためにも、まずは動物病院で適切な診断と処方を受けることが強く推奨されます。
多頭飼いの場合、1匹に感染が見つかると他の猫にも感染している可能性が非常に高いため、同居しているすべての猫を同時に検査・駆除することが重要です。
通常、駆虫薬を投与した後、一定期間をあけて再度検便を行い、便から虫卵が検出されなくなれば治療完了となります。
猫回虫の対策、人間へ感染しないためにできる工夫を
愛猫と飼い主さん自身を猫回虫から守るためには、日頃からの予防と対策が非常に重要です。具体的な対策と工夫を以下にまとめました。
猫自身への感染対策
- 完全室内飼いの徹底:屋外には回虫の卵が存在する可能性が高いため、室内飼いにすることで感染リスクを大幅に減らせます。
- 定期的な駆虫薬の投与:動物病院で処方される予防薬(フィラリア予防薬と兼用のものが多い)を定期的に投与することで、回虫の寄生を防ぎ、万が一感染しても駆除できます。
- 定期的な健康診断と検便:症状が出ていなくても、定期的に動物病院で便の検査を受けることで早期発見につながります。
人間への感染を防ぐための工夫
- 手洗いの徹底:猫を触った後や、猫のトイレを掃除した後、また外から帰宅した際には、必ず石鹸で丁寧に手を洗いましょう。
- 猫のトイレの衛生管理:猫の便はすぐに片付け、トイレは常に清潔に保ちましょう。排泄された便は時間が経つと感染力を持つため、こまめな掃除が感染予防の鍵です。
- 猫との過度な接触を避ける:口移しで食べ物を与えたり、キスをしたりする行為は感染リスクを高めるため避けましょう。
- 砂場などでの注意:公園の砂場や庭の土などは、野良猫が排泄している可能性があります。お子さんが遊んだ後は、特に念入りな手洗いを心がけてください。