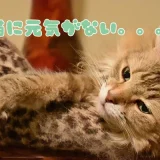猫も人間と同じように、おならをすることをご存知でしょうか?
猫のおならは「プシュッ」と小さな音がする程度で、ほとんど音が出ないため気づかれにくいですが、その臭いは強烈だと言われています。
おならは自然な生理現象ですが、あまりに頻繁だったり、普段より臭いがきつかったりすると、愛猫の体調が心配になりますよね。
- ✓ 最近、おならの回数が増えて臭いも気になる…
- ✓ お腹がパンパンに張っているように見える…
- ✓ もしかして、何かの病気のサイン…?
この記事では、そんな飼い主さんの不安を解消するために、猫のおならが臭くなる原因と具体的な対策を詳しく解説します。
注意すべき病気の兆候についても紹介しますので、愛猫のおならの臭いや回数に変化を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
猫もおならをする?
猫も人間と同様に、食べたものを消化する過程でおならをします。おならは、腸内で食べ物が発酵する際に発生したガスが体外に排出されるもので、食事をする以上、避けることのできない生理現象です。
猫のおならは音がしないことが多いため、飼い主さんが気づくのは「臭い」がしたときかもしれません。おならをするときのポーズも決まっておらず、寝ながら、あるいは歩きながらしていることもあります。
そのため、臭いや回数の変化は、愛猫の健康状態を知るための重要なバロメーターになります。「いつもよりおならが臭い」「ガスが溜まってお腹が張っている」「頻繁におならをする」といった変化に気づけるよう、日頃から愛猫の様子を注意深く観察してあげましょう。
猫のおならが臭いときの原因は?
おならの臭いは、腸内で発生する硫化水素、インドール、スカトール、アンモニアといった成分が原因です。これらは腸を持つ動物なら発生するものですが、特に猫のおならが臭くなりやすいのには、いくつかの原因が考えられます。
肉食動物特有の消化
猫は生粋の肉食動物です。食事のメインとなる肉類(タンパク質)を分解する際に、臭いの元となるアンモニアなどの物質が多く発生します。これは、人間がお肉中心の食事を続けるとおならが臭くなるのと同じ原理です。
ただし、猫は犬や人間よりも多くのタンパク質を必要とする動物なので、単純にタンパク質を減らすのは健康上よくありません。猫のおならがある程度臭いのは、肉食動物である以上、自然なことと理解しておきましょう。
ストレスによる消化機能の低下
人間がストレスで胃腸の調子を崩すように、猫もストレスによって消化器官の働きに影響が出ます。猫は非常にデリケートで、環境の変化(引越し、模様替え)、大きな音、来客、同居ペットとの関係など、様々なことがストレスの原因になり得ます。
ストレスを感じると腸の動きが悪くなり、消化不良を起こしやすくなるため、おならが臭くなることがあります。愛猫がリラックスできる静かな環境を整え、ストレスの原因を取り除いてあげることが大切です。
腸内環境の乱れ
消化に悪いフードや体質に合わない食事、ストレスなどが原因で、腸内環境が乱れることがあります。猫の腸は肉類を効率よく消化するために短くできており、穀物など消化しにくい原材料が多く含まれるフードは、消化不良や腸内環境の悪化を招きやすいです。
腸内で悪玉菌が増えると、異常発酵が起きて臭いガスが大量に発生します。これはおならが臭くなるだけでなく、便秘や下痢、さらには他の病気を引き起こす原因にもなるため注意が必要です。
猫のおならが臭いときの対策は?
愛猫のおならの臭いが気になるときは、病的な原因がなければ、生活習慣の見直しで改善が期待できます。特におすすめの対策は以下の2つです。
キャットフードを見直す
最も効果的な対策は、キャットフードの見直しです。フードに含まれるタンパク質が体質に合わなかったり、質が悪く消化しにくかったりすると、消化しきれなかったタンパク質が大腸で腐敗し、強い臭いのガスを発生させます。
消化性の高い良質な動物性タンパク質を主原料とし、穀物不使用(グレインフリー)で、不要な添加物が含まれていないフードを選ぶのがおすすめです。乳酸菌やオリゴ糖など、腸内環境をサポートする成分が配合されたフードも良いでしょう。フードを切り替える際は、1週間ほどかけてゆっくりと行いましょう。
ストレスに注意する
ストレスは腸の働きを鈍らせ、おならの原因となります。猫が安心して過ごせる環境づくりを心がけましょう。爪とぎやキャットタワーを設置して運動不足を解消したり、清潔なトイレを猫の数+1個用意したり、静かで落ち着ける隠れ場所を確保してあげることが、ストレス軽減に繋がります。
猫の臭いおならが続くときは病気なの?
「いつもより明らかに臭いがきつい」「おならの回数が異常に多い」といった状態が続く場合は、単なる消化不良ではなく、病気が隠れている可能性も考えられます。おなら以外の症状にも注意してください。
腸閉塞(イレウス)
異物の誤飲や腫瘍などによって腸が塞がってしまう病気です。腸の動きが止まるため、便やガスが排出されにくくなります。そのため、おならの回数は減りますが、たまに出るおならは非常に強烈な腐敗臭がします。お腹がパンパンに張り、嘔吐や食欲不振といった症状が見られたら、命に関わる危険な状態です。すぐに動物病院を受診してください。
慢性的な下痢や腸炎
腸内環境の悪化が続き、慢性的な腸炎や下痢を起こしている場合、腸の異常発酵によっておならの回数が増え、臭いもきつくなります。嘔吐や食欲不振を伴うことも多く、体重が減少することもあります。下痢が続くと脱水症状なども引き起こすため、早めに獣医師に相談しましょう。
寄生虫感染症
お腹の中に寄生虫がいると、腸の粘膜が傷つけられて消化吸収がうまくいかなくなり、臭いおならや下痢、血便などの症状が出ることがあります。お腹がぽっこりと膨れる、元気や食欲がなくなる、嘔吐するといった症状が見られる場合も。定期的な駆虫薬の投与で予防することが大切です。
愛猫の腸内環境も日々見てあげよう!
猫のおならは、健康な状態でもある程度は臭うものです。大切なのは「普段との違い」に気づいてあげることです。
普段よりおならが臭い、回数が多いといった変化は、食事やストレスが原因の場合もあれば、病気のサインである可能性もあります。おならだけでなく、食欲、元気、うんちの状態などもあわせてチェックし、少しでもおかしいと感じたら動物病院を受診しましょう。
日々のケアとして、愛猫の体に合った消化の良いフードを選び、ストレスのない快適な環境を整えてあげることが、腸の健康を守り、臭いおならの予防に繋がります。
愛猫が発する小さなサインを見逃さず、健やかな毎日をサポートしてあげてくださいね。