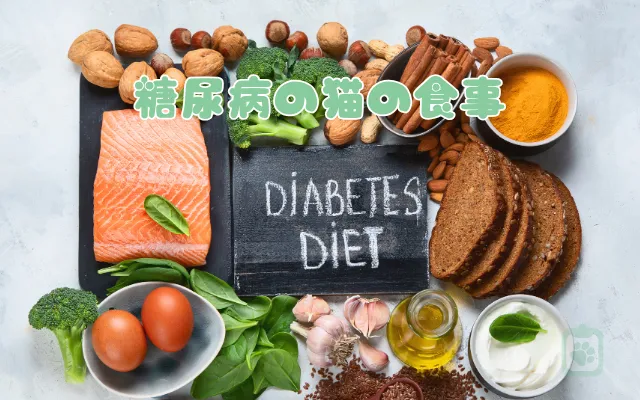「うちの猫、最近よく水を飲むし、おしっこの量も多いかも…」と感じていませんか?それはもしかしたら糖尿病のサインかもしれません。糖尿病は人間だけの病気ではなく、猫にとっても身近な病気の一つです。
糖尿病と診断された場合、インスリン治療と並行して、毎日の「食事管理」が非常に重要になります。適切な食事は、血糖値を安定させ、猫のQOL(生活の質)を維持するために不可欠です。
この記事では、猫が糖尿病になった際の食事の基本から、具体的なフードの選び方、与える際の注意点までを詳しく解説します。
猫の糖尿病は食事も関係している?
糖尿病とは、血糖値を下げる働きを持つ「インスリン」というホルモンが不足したり、うまく作用しなくなったりすることで、血液中の糖分(血糖)が増え、高血糖状態が続いてしまう病気です。
猫の糖尿病は、インスリンが分泌されていても体がうまく反応しない「Ⅱ型糖尿病」がほとんどを占めます。このⅡ型糖尿病は、遺伝的な要因だけでなく、生活習慣、特に食生活や肥満が大きく関係していると考えられています。
糖尿病のリスクを高める主な要因には、以下のようなものがあります。
- 肥満
過剰な体脂肪はインスリンの働きを妨げ(インスリン抵抗性)、糖尿病の最大のリスク因子となります。特に室内飼いの猫は運動不足になりがちで、肥満のリスクが高まります。 - 不適切な食事
炭水化物が多すぎる食事は、食後の血糖値を急激に上昇させ、インスリンを分泌するすい臓に負担をかけます。これが長期間続くと、糖尿病の発症につながることがあります。 - 早食い・一気食い
一度に大量のフードを食べると血糖値が急上昇し、インスリンが過剰に分泌されます。この繰り返しが、インスリンの効きを悪くする原因となります。
猫が糖尿病になったら、食事は何を食べればいいの?
猫が糖尿病と診断された場合、食事の目的は「血糖値の急激な上昇を抑え、安定させること」です。そのために、獣医師の指導のもと、専用の「療法食」を与えるのが基本となります。
糖尿病の猫のための療法食には、以下のような特徴があります。
- 高タンパク質
筋肉量を維持し、健康的な代謝をサポートします。タンパク質は糖質に比べて、食後の血糖値上昇が緩やかです。 - 低炭水化物・低糖質
血糖値の急上昇を抑えるために、原因となる炭水化物の含有量が調整されています。 - 適度な食物繊維
水溶性・不溶性の食物繊維がバランスよく配合されており、糖の吸収を穏やかにする効果が期待できます。
どの療法食が愛猫に合っているか、また1日に与えるべき量については、猫の体重や活動量、併発している病気などによって異なります。必ずかかりつけの獣医師と相談し、その子に合ったフードを選んでください。
猫の糖尿病で食事の注意点は?
糖尿病の食事管理を成功させるためには、フードの種類だけでなく、与え方にも注意が必要です。以下のポイントを守り、血糖値のコントロールをサポートしましょう。
- 食事の回数を増やす
1日の食事を2〜4回、あるいはそれ以上に小分けにして与えることで、一度に血糖値が急上昇するのを防ぎます。タイマー付きの自動給餌器を活用するのも非常に有効です。 - 正確な計量
食べ過ぎは肥満につながり、糖尿病を悪化させます。1回に与えるフードの量は、必ずキッチンスケールなどで正確に計量しましょう。 - おやつは原則NG
市販のおやつは糖質や脂質が高いものが多く、血糖コントロールを乱す原因になります。おやつやトッピングを与えたい場合は、必ず事前に獣医師に相談し、許可されたものを少量にとどめましょう。 - 新鮮な水をいつでも飲めるように
糖尿病の猫は多飲多尿になりがちです。脱水を防ぐため、新鮮な水をいつでも十分に飲める環境を整えてあげてください。
猫の糖尿病は食事のケアも大切
猫の糖尿病は、一度発症すると完治が難しい病気ですが、適切な食事管理とインスリン治療によって、血糖値を良好にコントロールすることは可能です。食事療法によって血糖値が安定すれば、インスリンの投与量を減らせるケースもあります。
大切なのは、飼い主さんが病気への理解を深め、根気強くケアを続けることです。食事管理のポイントは以下の通りです。
- 基本は獣医師推奨の「療法食」
- 食事は「小分け」にして与え、血糖値の急上昇を防ぐ
- 1日の摂取カロリーを守り、「肥満」を解消・予防する
- 自己判断でおやつや人間の食べ物を与えない
食事内容や与え方に気を配り、定期的に獣医師の診察を受けながら、愛猫が穏やかに過ごせる毎日をサポートしてあげましょう。