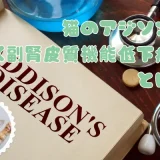愛犬の体がいつもより熱い気がする…そんな時、飼い主さんなら誰でも「もしかして病気?」と心配になりますよね。犬の平熱は人間より高いため、ただ熱いだけでは判断が難しいもの。しかし、その「いつもと違う」という感覚は、重大な病気のサインかもしれません。
この記事では、犬の発熱のサインとなる症状から、正しい熱の測り方、ご自宅でできる応急処置、そして危険な病気の可能性まで、飼い主さんが知っておくべき情報を詳しく解説します。犬の発熱は重症化しやすいため、異変に気づいたらすぐに対応できるよう、ぜひ参考にしてください。
犬の発熱、症状は?
犬が発熱しているとき、体温の上昇以外にも様々な体調不良のサインを見せます。愛犬の様子がいつもと違うと感じたら、以下のような症状がないか注意深く観察してみてください。
- 元気がない、ぐったりしている
- 食欲が落ちる、全く食べない
- 小刻みに震えている
- 呼吸が速い、または荒い
- 散歩や遊びに興味を示さない
- 歩き方がふらついている、よろよろ歩く
これらの症状は、犬が体調不良を訴える重要なサインです。一つでも当てはまる場合は、発熱を疑い体温を測ってみることを強くおすすめします。
犬の発熱、測り方は?
犬の体温を最も正確に測る方法は、ペット用の体温計を使い、お尻の穴(直腸)で検温することです。人間用の体温計でも代用は可能ですが、先端が硬いため直腸を傷つけるリスクがあります。また、衛生面や感染症のリスクを避けるためにも、必ず犬専用のものを用意し、人と共用するのはやめましょう。
もし体温計がない場合、緊急の確認方法として耳の付け根や内股を触ってみる方法があります。普段からこれらの場所を触り、平熱時の温かさを覚えておくことで、いざという時に「いつもより熱い」という変化に気づきやすくなります。ただし、これはあくまで目安ですので、正確な体温は必ず体温計で測定してください。
vet監修獣医師先生
犬の発熱、平熱は?
38.5℃前後
犬の平熱は個体差もありますが、一般的に38.5℃前後と人間よりも2〜3℃高いのが特徴です。運動後や興奮している時は一時的に体温が上昇するため、愛犬がリラックスして落ち着いている時に測るのが理想的です。
犬にとって39.5℃以上は「発熱」している状態であり、特に40℃を超える高熱は非常に危険なサインです。高熱が続くと脱水症状を引き起こし、体力の消耗も激しく、命に関わる事態に発展する恐れがあります。39.5℃以下の微熱であっても、ぐったりしているなど他の症状が見られる場合は、できるだけ早く動物病院で獣医師の診察を受けましょう。
犬の発熱は病気なの?
犬の発熱は、それ自体が病気なのではなく、体内で起きている何らかの異常を知らせる「警告サイン」です。体がウイルスや細菌と戦っている時や、炎症が起きている時に体温が上昇します。犬の発熱から考えられる原因には、以下のような様々な病気が潜んでいる可能性があります。
- ウイルスや細菌による感染症(犬ジステンパー、犬パルボウイルス感染症など)
- 肺炎、気管支炎などの呼吸器系の炎症
- 子宮蓄膿症、膀胱炎、腎盂腎炎などの泌尿生殖器系の病気
- 外傷や手術後の炎症反応
- 熱中症や日射病
このように、犬の発熱の原因は多岐にわたるため、飼い主さんご自身で原因を特定するのは非常に危険です。必ず獣医師による適切な診断と治療を受けさせてあげてください。
犬の発熱、下げ方などの対処法は?
愛犬に発熱の症状が見られた場合、まずは動物病院へ連れて行くのが最善ですが、すぐに受診できない時のために応急処置を知っておくことも大切です。ただし、人間用の解熱剤は絶対に使用しないでください。犬には毒となり、命を落とす危険があります。
ご自宅でできる対処法は以下の通りです。
- 安静にさせる:静かで涼しい、温度変化の少ない室内でゆっくり休ませましょう。外飼いの犬も必ず室内に入れてあげてください。
- 水分補給を促す:脱水を防ぐため、いつでも新鮮な水が飲めるようにしておきましょう。
- 体を冷やす:タオルで包んだ保冷剤や氷嚢を、首の付け根、脇の下、内股の付け根など、太い血管が通っている場所に当てて優しく冷やします。
これらの応急処置をしても体温が下がらなかったり、ぐったりして呼吸が荒い状態が続いたりする場合は、夜間救急なども含めてすぐに動物病院へ連絡してください。一般的に、症状が出始めてから3〜6時間経っても改善が見られない場合は、受診の一つの目安となります。
犬の発熱は普段からよく接していると気づきやすい
犬の発熱は、様々な病気のサインであり、早期発見・早期治療が何よりも大切です。犬の平熱は人間より高いことを理解し、40℃を超える高熱は命に関わる危険な状態であることを覚えておきましょう。
日頃から愛犬の体を撫でたり、抱っこしたりしてコミュニケーションをとることで、平熱時の体温や体の状態を把握でき、ささいな変化にも気づきやすくなります。愛犬のもしもの時に備え、かかりつけの動物病院の連絡先や、夜間・救急対応の病院を事前に確認しておくことも、発熱への重要な備えとなります。