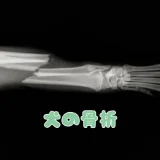愛犬が突然「ハアハア」と息苦しそうにしている姿を見ると、飼い主さんとしてはとても心配になりますよね。犬の息が荒くなる原因は、運動後や興奮といった一時的な生理現象であることも多いですが、中には心臓病や呼吸器系の病気など、緊急の治療が必要なケースも隠れています。
この記事では、犬の息が荒いときに考えられる原因や、その背景にある可能性のある病気、ご家庭でできる対処法や動物病院での検査について詳しく解説します。
正常時の犬の呼吸数は?
まず、愛犬の呼吸が「正常」か「異常」かを見分けるために、正常時の犬の呼吸数を知っておくことが大切です。犬がリラックスして落ち着いている状態のとき、1分間に15~30回程度が正常な呼吸数の目安とされています。
犬の呼吸数は、お腹や胸が上下に動くのを1回として数えます。長毛の犬種でお腹の動きが見えにくい場合は、鼻先にそっと手をかざし、手に当たる息の回数で確認することもできます。
正確に1分間測るのが難しい場合は、15秒間の呼吸数を数えて4倍するか、20秒間数えて3倍することで、1分間あたりの呼吸数を計算できます。
普段から健康なときの呼吸数を把握しておくことで、いざという時に「いつもより息が荒い」という異常に素早く気づくことができます。
犬の息が荒い原因は?
病気によるもの
生理的な現象
事故による外傷
犬の息が荒い原因は、大きく分けて「病気」「生理的現象」「事故」の3つが考えられます。犬が舌を出して苦しそうに「ハアハア」と呼吸している状態や、座り込んだまま肩を上下に大きく揺らして呼吸している場合は、息が荒い状態と言えるでしょう。
病気
呼吸が荒くなる症状が見られる場合、何らかの病気が原因となっている可能性があります。特に、心臓や呼吸器系の疾患、または体温調節に関わる病気が疑われます。
心臓や循環器系の病気
心臓の機能が低下すると、全身に十分な酸素を送れなくなり、それを補おうとして呼吸が速く、荒くなります。代表的な病気には「僧帽弁閉鎖不全症」や先天性の「心室中隔欠損症」、そして蚊が媒介する「フィラリア症」などがあります。
僧帽弁閉鎖不全症は、特に高齢の小型犬に多く見られ、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルは好発犬種として知られています。
フィラリア症は、心臓や肺動脈に寄生虫が住み着くことで深刻な循環障害を引き起こします。この病気は予防薬で確実に防ぐことができるため、定期的な予防が非常に重要です。
呼吸器系の病気や熱中症
気管や鼻、肺に異常があると、空気の通り道が狭くなり呼吸困難を引き起こします。具体的には、気管が潰れてしまう「気管虚脱」や「鼻炎」「肺炎」などが挙げられます。
また、重度の「熱中症」になると、体温が異常に上昇し、体温を下げるために激しいパンティング(ハアハアという呼吸)が見られます。息が荒いだけでなく、ぐったりしている、よだれが多い、嘔吐するなどの症状があれば、命に関わる危険な状態です。すぐに動物病院を受診しましょう。
生理的現象
散歩やドッグランで遊んだ後、興奮した時、夏の暑い日などに息が荒くなるのは、体温調節のための生理的な現象(パンティング)です。犬は人間のように全身で汗をかけないため、舌を出して唾液を蒸発させる気化熱を利用して体温を下げます。
このパンティングは自然な行動ですが、下記のような状況では病気のサインかもしれません。
涼しい場所で安静にしているのに、息が荒い
いつもより明らかに呼吸が激しく、なかなか収まらない
「ハアハア」という音に「ゼーゼー」「ガーガー」といった雑音が混ざっている
これらの場合は、単なるパンティングではなく、痛みや苦痛を伴う病気が原因である可能性を疑う必要があります。
事故
交通事故や落下事故などによる外傷が原因で、息が荒くなることもあります。特に、強い衝撃で胸を打った場合、肺挫傷や、横隔膜が破れてお腹の臓器が胸に入り込む「横隔膜ヘルニア」などを起こし、呼吸を圧迫することがあります。
事故に遭った直後は興奮していて症状が分かりにくいこともありますが、骨折や内臓損傷など目に見えないダメージを負っている可能性が高いため、必ず動物病院で診察を受けてください。
犬の息が荒くなる症状が起きやすい犬種はいる?
生理現象であるパンティングは、もちろん全ての犬種で見られます。しかし、病気が原因で息が荒くなる場合、特定の病気にかかりやすい犬種では特に注意が必要です。このように、犬の息が荒くなる症状が起きやすい犬種には、いくつかの傾向があります。
心臓病の「僧帽弁閉鎖不全症」はキャバリアやマルチーズ、シーズー、チワワといった小型犬に多く、加齢とともに発症リスクが高まります。
先天性の「心室中隔欠損症」は、柴犬やイングリッシュ・スプリンガー・スパニエルなどで報告があります。
「フィラリア症」は蚊に刺されることで感染するため、屋外で過ごす時間の長い短いにかかわらず、全ての犬種で予防が不可欠です。
熱中症が原因のときと特に気を付けたい犬種
熱中症による呼吸の悪化は、特に「短頭種」「北方原産の犬種」「肥満犬」でリスクが高まります。
パグ、フレンチ・ブルドッグ、シーズー、ペキニーズなどの短頭種は、骨格的に鼻の穴や気管が狭く、呼吸による体温調節が非常に苦手です。そのため、他の犬種であれば問題ないような気温や湿度でも、熱中症に陥りやすくなります。
シベリアン・ハスキーやサモエドといった北方原産の犬種は、寒さに耐えるための分厚い被毛を持っているため、体内に熱がこもりやすく、日本の夏の暑さは非常に危険です。
さらに、肥満犬は皮下脂肪が断熱材の役割をしてしまい熱が逃げにくい上、首周りの脂肪が気道を圧迫して呼吸機能の低下を招くため、熱中症のリスクが格段に上がります。
息が荒くなってしまったときの対処は?
愛犬の息が荒くなってしまったとき、飼い主さんはどのように対処すればよいのでしょうか。原因に応じた適切な対応が重要です。
病気が疑われる場合
まずは動物病院を受診し、息が荒い原因となっている病気を特定して、適切な治療を受けることが最優先です。受診する際は、「いつから息が荒いか」「どんな状況でひどくなるか」「他に変わった様子はないか」などをメモしておくと、獣医師が診断する上で重要な情報となります。自宅では、激しい運動を避けさせ、愛犬が楽な姿勢で過ごせるように静かな環境を整えてあげましょう。
生理的現象の場合
運動後や興奮による一時的なパンティングであれば、しばらく休ませれば自然に落ち着くため、特に心配はいりません。ただし、夏の暑さが原因の場合は熱中症に移行する危険があるため、早急な対策が必要です。エアコンで室温を25℃前後に保ち、クールマットを用意するなど、愛犬が涼しく過ごせる環境を作りましょう。
夏の散歩は、アスファルトの熱が冷めた早朝や夜間に行い、日中の暑い時間帯は避けるようにしてください。
事故の場合
事故に遭ってしまったら、見た目に大きなケガがなくても、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。体をむやみに動かすと状態を悪化させる可能性があるため、板のようなものに乗せるなどして、できるだけ安静な状態で運ぶことが大切です。獣医師の診察を受け、外傷以外の内臓損傷などがないかを確認してもらうことが重要です。
息が荒くなったときどんな検査が必要?
動物病院では、犬の息が荒くなった原因を突き止めるために、どんな検査が必要になるのでしょうか。状態に応じて、以下のような検査が行われます。
身体検査・体温測定
血液検査
レントゲン(X線)検査
超音波(エコー)検査
体温測定
まず、直腸で体温を測定します。犬の平熱は38℃台ですが、39.5℃以上ある場合は高体温状態です。運動などをしていない安静な状態で体温が高い場合、熱中症や、何らかの感染症、炎症、腫瘍などが疑われます。
血液検査
血液検査では、貧血や脱水の有無、炎症反応の数値、肝臓や腎臓といった内臓機能の状態などを調べることができます。これにより、全身の状態を把握することが可能です。また、フィラリアの感染の有無も、少量の血液で検査することができます。
レントゲン検査
胸部のレントゲン検査は、呼吸器や心臓の病気を診断する上で非常に重要です。心臓の大きさや形(心肥大)、肺の状態(肺炎、肺水腫)、気管の形(気管虚脱)、横隔膜の状態(横隔膜ヘルニア)などを視覚的に確認できます。
これらの検査に加えて、心臓の動きや血流をリアルタイムで見る「超音波検査」や、不整脈を調べる「心電図検査」などが必要になることもあります。
飼い主さんだから分かる変化を見落とさないで!
愛犬の息が荒いのが、一時的な生理現象なのか、それとも病気のサインなのか。その違いに一番早く気づけるのは、毎日を共に過ごす飼い主さんだからこそ分かる変化です。日頃から愛犬の様子をよく観察し、コミュニケーションをとることが、病気の早期発見・早期治療に繋がります。
特に、熱中症は予防が可能な病気です。夏場はエアコンによる室温管理を徹底し、愛犬がいつでも新鮮な水を飲めるようにしておきましょう。
暑い季節の散歩は、時間帯に十分配慮してください。アスファルトの照り返しは想像以上に犬の体力を奪い、熱中症のリスクを高めます。
「いつもと何か違う」と感じたら、それは重要なサインかもしれません。些細なことでもためらわずに、かかりつけの動物病院に相談してください。