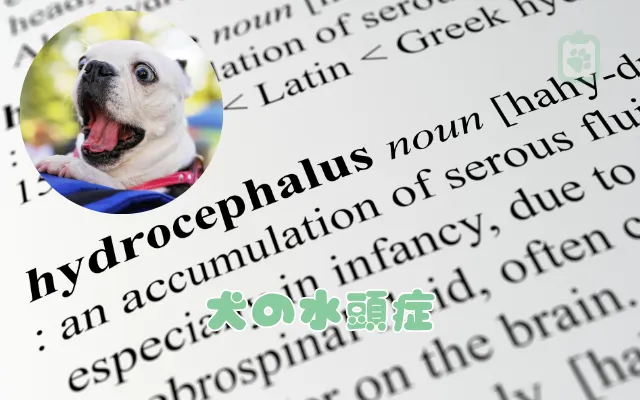犬の「水頭症(すいとうしょう)」という病気をご存知でしょうか?水頭症とは、脳の中にある「脳室」という部分に脳脊髄液(のうせきずいえき)という液体が過剰に溜まり、脳を圧迫してしまう病気です。
脳が圧迫されると、行動の変化や麻痺など、様々な神経症状が引き起こされる可能性があります。愛犬の異変にいち早く気づくためには、飼い主が水頭症について正しく理解しておくことが重要です。
この記事を読めば、以下のような疑問が解消できます。
- ✓犬の水頭症ではどんな症状が出るの?
- ✓かかりやすい犬種はいる?
- ✓治療法や飼い主ができることは?
そこでこの記事では、犬の水頭症について、具体的な症状や原因、診断方法、治療法、そして飼い主ができる対処法まで、分かりやすく解説します。愛犬の健康を守るために、ぜひ最後までお読みください。
水頭症ってどんな病気?
まずは、犬の水頭症がどのような病気なのか、その基本を解説します。症状や原因を知ることで、早期発見につなげることができます。
水頭症とは
水頭症とは、脳を衝撃から守ったり、栄養を運んだりする役割を持つ「脳脊髄液」が脳室に溜まりすぎることで、脳を内側から圧迫してしまう病気です。
通常、脳脊髄液は常に一定量が作られ、古くなったものは吸収されて排出されるというサイクルを繰り返しています。しかし、何らかの異常でこのサイクルのバランスが崩れ、「脳脊髄液が過剰に作られる」または「排出がうまくいかない」状態になると、水頭症を発症します。
水頭症の症状は?
水頭症の症状は、脳が圧迫される場所や進行度によって様々です。以下のような変化が見られたら注意が必要です。
- 元気がなく、ぐったりしている
- 寝てばかりいる、活動量が減った
- しつけができない、今までできていたことを忘れる(知能障害)
- 理由なく吠えたり、噛みついたりする(攻撃性の変化)
- 食欲不振
- 歩き方がふらつく、同じ場所をぐるぐる回る(異常行動)
- 視力障害(物にぶつかるなど)
- けいれん発作
- 四肢の麻痺
病気が進行すると、治療をしても症状の改善が難しくなり、外科手術のリスクも高まります。少しでも気になる症状があれば、自己判断せずにすぐに動物病院を受診しましょう。
水頭症の原因として考えられること
水頭症の原因は、生まれつきの「先天性」のものと、生まれてから何らかの原因で発症する「後天性」のものに分けられます。
先天性水頭症
遺伝的な要因や、胎児期の異常によって発症すると考えられています。子犬の頃(生後3〜6ヶ月頃)に症状が現れることが多いのが特徴です。
後天性水頭症
頭部の怪我(外傷)、脳腫瘍、髄膜炎(ずいまくえん)などの病気が原因で、脳脊髄液の流れが妨げられたり、過剰に作られたりすることで発症します。こちらは年齢に関係なく発症する可能性があります。
水頭症にかかりやすいとされる犬種
特に先天性の水頭症は、特定の犬種で発症しやすい傾向があります。一般的に、頭が丸く小さい小型犬や短頭種に多いとされています。
- チワワ
- トイ・プードル
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ヨークシャー・テリア
- シーズー
- パグ
- ボストン・テリア
- ペキニーズ
これらの犬種を飼っている場合は、特に注意深く様子を観察してあげることが大切です。
犬の水頭症を診断する方法は?
犬の水頭症の診断は、問診や身体検査に加え、専門的な検査を組み合わせて総合的に行われます。
特徴的な外見として「ドーム状に膨らんだ頭」や「泉門(せんもん)の開き(頭頂部の骨の隙間)」が見られることもありますが、外見だけでは判断できないケースも少なくありません。
そのため、以下のような画像診断や精密検査によって、脳の状態を詳しく調べます。
- X線検査:頭蓋骨の形や大きさを確認します。
- 超音波(エコー)検査:泉門が開いている子犬の場合、脳室の拡大を確認できます。
- CT検査・MRI検査:脳の状態や脳室の大きさを詳細に把握するための最も重要な検査です。水頭症の確定診断や、脳腫瘍など他の病気との鑑別に用いられます。
これらの検査結果をもとに、獣医師が水頭症かどうかを最終的に診断します。
犬の水頭症の治療法は?薬を飲むの?
犬の水頭症は、残念ながら完治が難しい病気ですが、治療によって症状を緩和し、進行を遅らせることを目指します。治療法は、主に「内科的治療」と「外科的治療」の2つがあります。
内科的治療法
症状が軽度の場合や、外科手術が難しい場合に行われる治療法です。薬の投与が中心となります。
- 利尿薬:体内の余分な水分を排出し、脳脊髄液の産生を抑えて脳圧を下げます。
- ステロイド剤:脳の炎症を抑え、脳圧を下げる効果が期待できます。
- 抗けいれん薬:けいれん発作が起きている場合に処方されます。
これらの投薬治療で症状をコントロールし、愛犬のQOL(生活の質)を維持することを目指します。
外科治療法
内科治療で効果が見られない場合や、症状が重度の場合に検討される治療法です。「脳室腹腔(のうしつふくくう)シャント術」という手術が一般的です。
この手術は、脳室に溜まった脳脊髄液を、細いチューブ(シャント)を使ってお腹(腹腔)に流すバイパスを作るものです。これにより、脳への圧迫を継続的に軽減させます。
ただし、手術には麻酔のリスクが伴い、術後もシャントの詰まりや感染症といった合併症の可能性があります。手術を行うかどうかは、愛犬の状態やリスクを考慮し、獣医師と十分に相談して決定することが重要です。
犬の水頭症は対処できる?
先天性の水頭症を完全に予防することは困難です。しかし、後天性の水頭症のリスクを減らすための対策や、症状の悪化を防ぐための対処は可能です。
飼い主ができる対処・対策法は以下の通りです。
- 頭部への強い衝撃を避ける:高い場所からの落下や、激しい衝突など、頭を強く打つ事故を防ぎましょう。
- 感染症の予防と早期治療:脳炎や髄膜炎の原因となる感染症にかからないよう、ワクチン接種や健康管理を徹底しましょう。病気になった際は、速やかに治療を受けることが大切です。
- 早期発見・早期治療:最も重要な対策です。普段から愛犬の様子をよく観察し、「いつもと違う」と感じたらすぐに動物病院に相談しましょう。
日頃のケアが、愛犬を水頭症のリスクから守る第一歩となります。
犬の水頭症は早期発見が大切
この記事では、犬の水頭症の症状や原因、治療法について解説しました。水頭症は完治が難しい病気ですが、早期に発見し、適切な治療を開始することで、症状の進行を抑え、愛犬との穏やかな時間を長く過ごせる可能性が高まります。
日々のスキンシップやコミュニケーションは、愛犬との絆を深めるだけでなく、元気や食欲、行動の変化といった些細なサインに気づく絶好の機会です。
大切な家族である愛犬の健康を守るために、少しでも気になる様子が見られたら、ためらわずに動物病院を受診してください。それが、愛犬にとって最善の選択となるはずです。