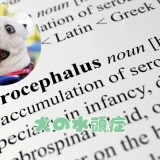人間は感情が高ぶると涙を流しますが、犬の涙は感情表現なのでしょうか。愛犬が涙を流していると、病気ではないかと心配になりますよね。
この記事では、獣医師監修のもと、犬が涙を流す症状や原因、動物病院での診断・治療法、そして飼い主ができる対処法や注意点について詳しく解説します。
犬が涙を流す症状は?
犬が涙を流すとき、飼い主が気づきやすいサインとして以下のような症状が現れます。
- 目ヤニの増加
- 涙やけ(目の周りの毛が赤茶色に変色する)
- 鼻の横の皮膚炎・湿疹
- 湿疹部分を気にして掻く、こする
犬の目には、ゴミなどの異物が入った際に涙で洗い流す自浄作用があります。しかし、常に涙を流していたり、涙の量が多い場合は「流涙症(りゅうるいしょう)」などの病気の可能性が考えられます。特に、トイプードルやマルチーズ、シーズーといった白い被毛の犬種では、涙やけによる赤茶色の変色が目立ちやすくなります。
涙やけで被毛が赤くなる原因
涙やけで毛が赤茶色に変色するのは、涙に含まれる成分が空気に触れることで変化するためです。主な原因は以下の通りです。
- 涙の成分による化学反応(ポルフィリン)
- 紫外線による変色
- 湿った部分でのバクテリアの繁殖
涙に含まれる「ポルフィリン」という成分が、酸素や紫外線に触れることで酸化し、赤茶色に変化することが主な原因です。
犬の涙から疑われる病気
犬が涙を流す症状の裏には、以下のような病気が隠れている可能性があります。
- 流涙症
- 結膜炎・角膜炎などの眼球の炎症
- ブドウ膜炎
- 眼瞼外反症(がんけんがいはんしょう)
- 眼瞼内反症(がんけんないはんしょう)
- 鼻涙管閉塞(びるいかんへいそく)
これらの病気は目に炎症を引き起こし、涙の量を増やす原因となります。軽い涙やけだと放置してしまうと、緑内障や白内障、網膜剥離といった失明につながる重篤な眼疾患に進行する危険性もあるため、早めの対処が重要です。
犬が涙を流す原因は?
犬が涙を過剰に流す場合、その多くは「流涙症」が原因です。流涙症が起こる原因は、大きく分けて2つのパターンがあります。
- 涙の産生量が過剰になり、目から溢れてしまうケース
- 涙を排出する器官(鼻涙管)が詰まり、正常に排水できなくなるケース
涙の産生量が過剰になる原因としては、ゴミ・被毛・シャンプーなどの異物混入、逆さまつげ、アレルギー、結膜炎や角膜炎、チェリーアイ(第三眼瞼腺突出)といった病気による刺激が挙げられます。また、パグやシーズーのように目が大きく前に出ている犬種も、目が乾燥しやすく刺激を受けやすいため、涙が出やすい傾向にあります。
一方、涙の排水路である「鼻涙管」が、炎症や副鼻腔炎、腫瘍などによって詰まってしまうと、涙が目から溢れ出てしまいます。生まれつき鼻涙管が閉じていたり、非常に細かったりする「無孔涙点」という先天性の障害が犬の涙の原因である場合は、手術による治療が必要になることもあります。
涙を流しているときの診断方法・治療方法まとめ
愛犬の涙が気になって動物病院を受診すると、まず原因を特定するための診断が行われます。飼い主から症状や普段の様子を聞き取った後、「視診検査」で逆さまつげの有無、異物の混入、角膜の傷などをチェックします。必要に応じて、涙の量を測る検査や、鼻涙管が正常に通っているかを確認する検査などが行われます。
このようにして犬が涙を流す原因を突き止めた上で、最適な治療方法が選択されます。
原因別の治療方法
原因によって治療法は異なり、内科的治療から外科的治療まで様々です。
異物や刺激が原因の場合
目にゴミなどの異物が入っている場合は、点眼薬などで洗い流します。被毛が目に入って刺激になっている場合は、トリミングで目の周りの毛を短くカットすることで改善が期待できます。
何かしらの疾患が原因の場合
結膜炎や角膜炎、チェリーアイなどが原因であれば、それぞれの病気の治療(点眼薬や内服薬など)が優先されます。涙嚢炎(るいのうえん)の場合は、原因菌を特定し、効果のある抗生物質の点眼薬を使用します。慢性化している場合は、麻酔下で鼻涙管を洗浄したり、再発防止のためにカテーテルを留置したりすることもあります。
無孔涙点など、先天的な構造の問題で涙を流している場合は、涙の通り道を作る外科手術が検討されます。
涙が溢れてしまうのは対策はできる?
流涙症の原因の多くは病気によるものなので、家庭でできる根本的な対策は限られています。しかし、症状の悪化を防ぎ、病気を早期発見するための対策は可能です。
犬が涙を流す症状は、すぐに命に関わるものではありませんが、放置は禁物です。定期的に動物病院で健康診断を受け、獣医師に目の状態をチェックしてもらうことが有効な対策となります。そこで気になる点があれば、本格的な検査に進むことができます。
そして、最も大切な対策は、飼い主が愛犬の様子を毎日こまめにチェックすることです。日々のコミュニケーションの中で目の状態を確認していれば、涙の量の変化や目ヤニの増加といった異常にいち早く気づくことができます。これが病気の早期発見・早期治療につながる最善の策といえるでしょう。
涙やけなど飼い主が注意することは?
犬の涙や涙やけに対して、飼い主が日頃から注意できる点がいくつかあります。
まず、涙の原因となる刺激を減らすケアが重要です。目の周りの被毛が長い犬種は、定期的なトリミングで毛が目に入らないようにカットしましょう。こまめなブラッシングで抜け毛を取り除くことも大切です。
目が大きくて飛び出している犬種の場合、散歩中に草むらで目を傷つけたり、シャンプー液が目に入ったりしないよう注意が必要です。愛犬が過ごす生活環境から、目に怪我をさせる可能性のある突起物などを取り除いてあげる配慮も求められます。
ただし、子犬の場合、目の周りの筋肉が未発達なために涙が溢れやすいことがあります。そのため子犬期は涙やけが起こりやすいですが、これは成長とともに自然に改善していくケースが多いことも知っておくと、過度に心配せずに済むでしょう。
涙が過剰になりやすい犬種がいる?
犬が涙を流す症状は、特定の犬種でより顕著に見られることがあります。体質や骨格が関係しているため、以下の犬種を飼っている場合は特に注意が必要です。
| 症状・病名 | かかりやすい犬種 |
|---|---|
| 流涙症 | チワワ、トイプードル、マルチーズ、シーズー |
| 鼻涙管閉塞 | プードル、アメリカン・コッカー・スパニエル、ゴールデン・レトリバー、パグ、フレンチ・ブルドッグ |
| 眼瞼外反症 | アメリカン・コッカー・スパニエル、セント・バーナード、ブルドッグ |
| 眼瞼内反症 | アメリカン・コッカー・スパニエル、グレート・ピレニーズ、ブルドッグ、ラブラドール・レトリバー、チャウチャウ |
流涙症は、チワワやトイプードルのような小型犬に多く見られます。被毛が長い犬種や、目が大きい犬種は物理的な刺激を受けやすく、涙が出やすい傾向にあります。特に、被毛が白色や薄い色の犬種は、涙やけによる変色が目立つため、日頃のケアが欠かせません。
パグやフレンチ・ブルドッグなどの短頭種は、骨格的に鼻涙管が圧迫されたり曲がったりしやすく、鼻涙管閉塞を起こしやすいのが特徴です。
また、「眼瞼外反症」や「眼瞼内反症」は、まぶたの形状による先天的な要因が大きい病気です。これらは慢性的な目の炎症の原因となるため、該当する犬種の飼い主は日頃から注意深く観察することが大切です。
いつもと違う症状があれば病院へ!
犬の涙が赤茶色になっていると、「血の涙では?」と驚かれるかもしれませんが、そのほとんどは涙に含まれる「ポルフィリン」という成分が酸化したものです。血が出ているわけではないので、まずは落ち着いてください。
しかし、涙の量が急に増えた、しきりに目をこする、目ヤニの色が黄色や緑色っぽいなど、いつもと違う症状が見られたら、それは動物病院へ連れて行くべきサインです。自己判断で市販の目薬を使うのは避け、必ず獣医師の診断を受けましょう。
犬の涙に関連する目の病気は、放置すると治療が困難になったり、失明に至ったりするケースも少なくありません。重篤な合併症を引き起こす前に、早期発見と適切な治療を開始することが、愛犬の目の健康を守るために最も重要です。
vet監修獣医師先生