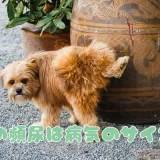愛犬の美しい被毛と健康な皮膚を保つために、毎日のブラッシングは欠かせないお手入れです。しかし、「ブラシを見せただけで逃げてしまう」「ブラッシング中に唸ったり噛もうとしたりする」など、愛犬が嫌がってしまい、お困りの飼い主さんも多いのではないでしょうか。
この記事では、犬がブラッシングを嫌がる主な理由と、それぞれの原因に合わせた具体的な対処法を詳しく解説します。愛犬との信頼関係を深めながら、ブラッシングを楽しいコミュニケーションの時間に変えていきましょう。
犬がブラッシングを嫌がる理由1:飼い主に触れられるのがイヤ
犬にとって、お腹、しっぽ、足先などは、本来あまり触られたくないデリケートな部分です。過去に乱暴に触られた経験がなくても、本能的にこれらの部位を守ろうとするため、ブラッシングを嫌がることがあります。
まずは、愛犬がリラックスしている時に、毛並みに沿って優しく撫でることから始めましょう。この時、おやつを与えながら行うと「触られる=良いことがある」と学習し、ポジティブな印象を与えることができます。体を預けてきたり、うとうとし始めたりしたら、リラックスしているサインです。
触られることに慣れてきたら、ブラシをそっと体に当てる練習をします。いきなりとかすのではなく、まずはブラシの存在に慣れさせることが重要です。それでも特定の場所を触られるのを極端に嫌がる場合は、怪我や関節の痛みなど、他の原因が隠れている可能性も考えられます。様子がおかしいと感じたら、獣医師に相談しましょう。
犬がブラッシングを嫌がる理由2:トラウマになってしまっている
以前のブラッシングで、痛い思いや怖い思いをしたことがトラウマになっているケースは少なくありません。例えば、毛玉を無理やり引っ張られたり、ブラシで皮膚を強くこすられたりした経験が、「ブラシ=痛いもの」という恐怖心に繋がってしまいます。
まずは、ブラッシングに対するネガティブなイメージを払拭することが大切です。リラックス効果が期待できる「背線マッサージ」などを取り入れてみましょう。指の腹で、尻尾の付け根から首に向かって、背骨の両脇を優しくマッサージします。愛犬が気持ちよさそうにしていたら、その流れでブラシを優しく当ててみてください。
ブラッシングを再開する際は、毛先のもつれを優しくほぐすことから始め、決して無理に引っ張らないように注意しましょう。「とかす」というより「撫でる」ような感覚で、短い時間で終えるのがポイントです。終わった後は、たくさん褒めてご褒美をあげることを忘れないでください。
犬がブラッシングを嫌がる理由3:道具があっていない
犬用のブラシには、毛の長さや毛質に合わせて様々な種類があります。愛犬の被毛に合わないブラシを使っていると、痛みを感じたり、不快に思ったりしてブラッシングを嫌がる原因になります。愛犬に最適なブラシを選ぶことが、快適なブラッシングへの第一歩です。
ブラシ選びに迷ったら、ペットショップのスタッフや、愛犬の犬種に詳しいトリマー、ブリーダーに相談するのがおすすめです。ここでは犬種別の一般的なブラシの選び方をご紹介します。
長毛種
ゴールデン・レトリバーやポメラニアンなどの長毛種は、毛が絡まりやすいため段階的なブラッシングが必要です。まず、アンダーコート(下毛)の抜け毛を優しく取り除く「スリッカーブラシ」を使い、その後、毛並みを整える「ピンブラシ」や「コーム」で仕上げます。いきなり根元からとかすと皮膚を引っ張ってしまうため、毛先から少しずつ丁寧にとかしましょう。
短毛種
柴犬やフレンチ・ブルドッグなどの短毛種は、硬いブラシで皮膚を傷つけやすいため注意が必要です。皮膚への刺激が少ない「ラバーブラシ」や「獣毛ブラシ」がおすすめです。これらのブラシはマッサージ効果も期待でき、血行促進にも繋がります。抜け毛が気になる換毛期にも活躍します。
ワイヤー種
ミニチュア・シュナウザーやジャック・ラッセル・テリアなどのワイヤー種は、硬い毛質が特徴です。基本的には長毛種と同様に「スリッカーブラシ」で抜け毛を取り除きます。特に換毛期には、アンダーコートを効率的に除去できる専用のコーム(ナイフ)を使うと、よりすっきりと仕上げることができます。
犬がブラッシングを嫌がる理由4:ブラシをおもちゃと勘違いしている
特に子犬や遊び盛りの犬に多いのが、動くブラシをおもちゃだと思い、じゃれついたり噛みついたりするケースです。飼い主がブラシを動かす様子が、遊びに誘われているように見えてしまうのです。
この場合は、「ブラッシングは遊びではない」ということを根気強く教える必要があります。「おすわり」や「ふせ」で一旦落ち着かせてからブラッシングを始めましょう。もしブラシにじゃれてきたら、一旦動きを止めて無視し、犬が落ち着いたら再開します。これを繰り返すことで、ブラッシング中は静かにするべき時間だと学習していきます。
ブラッシングが気持ち良いものだと理解すれば、次第に協力してくれるようになります。短い時間で終え、終わった後にはたくさん褒めて、遊びの時間とのメリハリをつけることが大切です。
犬がブラッシングを嫌がる理由5:病気が原因
急にブラッシングを嫌がるようになった場合、体に何らかの病気や痛みが隠れている可能性があります。ブラシが当たることで痛みを感じているのかもしれません。
例えば、アトピー性皮膚炎や膿皮症などで皮膚に炎症や湿疹があると、ブラシが触れるだけで激しい痛みを伴います。また、関節炎や椎間板ヘルニアなどの場合も、特定の体勢になることや、体の特定の部分に触れられることを嫌がります。
まずは愛犬の体をよく観察し、皮膚に赤み、フケ、脱毛、しこりなどがないかチェックしてください。体を触って特定の場所を痛がったり、歩き方がおかしかったりするなど、少しでも異変を感じたら、自己判断せずにすぐに動物病院を受診し、獣医師の診察を受けましょう。
愛犬にブラッシングを嫌いにさせないためには?
愛犬がブラッシングを嫌いになる背景には、「痛かった」「怖かった」「長時間拘束された」といったネガティブな経験が関係していることがほとんどです。また、飼い主さんが「ちゃんとやらなきゃ」と必死になるあまり、怖い顔になってしまい、その緊張感が愛犬に伝わっていることもあります。
ブラッシングは、飼い主さんも愛犬もリラックスして行うことが何よりも大切です。「おやつを食べながら」「お散歩に行く前に」など、愛犬にとって嬉しいことと関連付けるのも効果的です。愛犬が少しでも嫌がる素振り(顔をそむける、あくびをするなど)を見せたら、無理に続けずに一度中断し、ブラシの種類やブラッシングの時間、環境などを見直してみましょう。
ブラッシングは大切なコミュニケーション
最初は嫌がっていたブラッシングも、正しい方法で根気強く慣らしていくことで、愛犬の健康を守るだけでなく、飼い主さんとの絆を深める最高のスキンシップの時間に変わります。日々のブラッシングは、皮膚の異常やしこり、ノミ・ダニなどを早期に発見できる貴重な健康チェックの機会でもあります。
焦らず、愛犬のペースに合わせて、毎日少しずつでも続けていきましょう。楽しいお手入れの時間を通じて、愛犬の心と体の健康を維持してあげてくださいね。