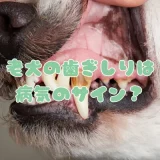愛犬のブラッシングやシャンプーは定期的に行うけれど、耳掃除はつい後回しになりがち…という飼い主さんは少なくありません。しかし、犬の耳はデリケートでトラブルが起きやすい部位のため、定期的なケアが非常に重要です。特に、垂れ耳の犬や耳の毛が長い犬は、耳の中が蒸れて汚れやすいため、こまめなチェックと正しい耳掃除が欠かせません。
この記事では、犬の耳掃除の正しい方法から適切な頻度、洗浄液の選び方、そして犬が嫌がるときの対処法まで、具体的なポイントを専門家のコメントを交えて詳しく解説します。
犬の耳掃除、方法1「耳の外側と中の状態をチェック」
犬の耳掃除を始める前に、まずは耳の外側(外耳)と内側の状態をしっかりチェックすることから始めましょう。外耳は汚れが目立ちやすい部分なので、耳垢や異物で汚れている場合は、洗浄液を含ませたコットンで優しく拭き取ります。
次に耳の中を覗き込み、「耳の中が赤く炎症を起こしている」「耳垢の色や量、耳の臭いがいつもと違う」といった異常がないか確認してください。これらの症状は外耳炎など病気のサインである可能性があるため、耳掃除は行わず、すぐに動物病院で獣医師の診察を受けましょう。
どういう耳垢が危険?
耳垢の色は犬の体質にもよりますが、病気の重要なサインとなることがあります。以下のような耳垢が見られた場合は注意が必要です。
- 黒い耳垢: 「耳ダニ(ミミヒゼンダニ)感染症」が疑われます。かゆみが強く、コーヒーの出がらしのようなカサカサした黒い耳垢が特徴です。
- 茶色く湿った耳垢: 「マラセチア」という常在菌(カビの一種)の異常繁殖による皮膚病(マラセチア性外耳炎)が考えられます。独特の甘酸っぱい臭いを伴うことが多いです。
- 黄色や緑色の耳垢: 細菌感染による「化膿性外耳炎」の可能性があります。膿のような耳垢で、強い臭いを放つことがあります。
vet監修獣医師先生
犬の耳掃除、方法2「耳の中に洗浄液を垂らしてマッサージ」
耳の状態に問題がなければ、洗浄液(イヤークリーナー)を使って掃除を進めます。洗浄液の量は、犬の耳に数滴垂らす程度で十分です。入れすぎると耳の中に水分が残り、かえって雑菌が繁殖する原因になるため注意しましょう。
洗浄液を入れたら、耳の付け根の軟骨部分を親指と人差し指で優しく挟み、液をなじませるようにクイクイと揉みほぐします。マッサージがうまくできると「クチュクチュ」「チャプチャプ」という音が聞こえるので、これを合図に30秒ほど続けてください。
犬の耳掃除に使う洗浄液は市販品も豊富ですが、愛犬の肌に合うか分からない場合は、かかりつけの動物病院やブリーダーに推奨される洗浄液を選ぶと安心です。
犬の耳掃除、方法3「首を振らせ汚れをふき取る」
マッサージが終わったら、一度手を離して犬が自然に頭をブルブルと振るのに任せましょう。この動きによって、耳の奥で浮き上がった汚れと洗浄液が外に排出されます。もし犬が頭を振らない場合は、耳の中に「フッ」と優しく息を吹きかけると、その刺激で頭を振ってくれることがあります。
耳から出てきた洗浄液や耳垢を、コットンやガーゼなどの柔らかいもので優しく拭き取れば、犬の耳掃除は完了です。耳の入り口付近や、ひだの汚れも綺麗にしてあげましょう。
犬の耳掃除、注意点は?
犬の耳は非常にデリケートです。耳掃除の際は、力を入れてゴシゴシこすらないように注意してください。強くこすると耳の皮膚を傷つけ、外耳炎を引き起こす原因になってしまいます。
また、人用の綿棒は犬には刺激が強すぎるうえ、汚れを耳の奥へ押し込んでしまう危険性があるため使用は避けてください。必ずコットンやガーゼなど、柔らかく安全なものを使用しましょう。
vet監修獣医師先生
耳の中に毛が生えている犬種の注意点
トイプードル、マルチーズ、シーズーなどの犬種は、耳道内に毛が生えているため通気性が悪くなりがちです。皮脂や耳垢がその毛に絡みつき、外耳炎を起こしやすい傾向にあります。耳掃除の前に、イヤーパウダーなどを使って滑りを良くし、鉗子(かんし)で余分な耳毛を数本抜いてから掃除をすると効果的です。
ただし、耳毛には外部からのゴミや虫の侵入を防ぐ役割もあります。抜きすぎるとかえって炎症を起こすことがあるため、通気性を確保できる最低限の量に留めましょう。
垂れ耳の犬種の注意点
ゴールデンレトリバーやダックスフンド、キャバリアといった垂れ耳の犬種は、耳が常にフタをされた状態になり、耳の中が高温多湿になりがちです。これは細菌や真菌(カビ)が繁殖するのに最適な環境です。
この状態を放置すると汚れが溜まり、外耳炎から中耳炎、内耳炎へと進行するリスクが高まります。日頃から定期的に耳をめくって通気性を良くし、汚れを拭き取って清潔な状態を保つことが大切です。犬用のイヤーパウダーで耳を乾燥した状態に保つ工夫も有効です。
脂漏症になりやすい犬種の注意点
アメリカン・コッカー・スパニエル、シーズー、ダックスフンドなどは、皮脂の分泌が多い「脂漏症」になりやすい犬種です。ベタベタした脂っぽい耳垢が多い場合、通常のイヤークリーナーでは洗浄力が足りないことがあります。
その場合は、脂を溶かす作用を持つ「脂漏症用のイヤークリーナー(例:エピオティックなど)」を試してみるのがおすすめです。非アルコールで低刺激ながら、しっかりと脂汚れを浮かせて除去することができます。
犬の耳掃除、頻度は?
2週間に1回程度が基本(健康な場合)
犬の耳が健康な場合、耳掃除の頻度は2週間に1回程度が目安です。耳の汚れ具合を毎日チェックすることは大切ですが、やりすぎは禁物。頻繁すぎる耳掃除は、かえって耳の中を傷つけ、外耳炎を引き起こす原因になります。
また、動物病院で耳の診察を受ける予定がある日は、事前に耳掃除をしないようにしましょう。耳垢は診断の重要な手がかりになるため、ありのままの状態で獣医師に診てもらうことが正しい診断につながります。
最初は病院やブリーダーから教わるのが確実
自宅での犬の耳掃除は、正しい方法を理解し、犬をリラックスさせるコツが必要です。もしご自身でのケアに自信がない場合や、愛犬がひどく嫌がる場合は、無理に行わず動物病院やトリミングサロンでプロに相談・依頼するのが最も安全で確実です。
また、洗浄液には様々な種類がありますが、アルコール成分が入っている製品は刺激が強く嫌がる犬もいます。最初は自然由来成分配合など、犬のデリケートな皮膚に配慮した優しい洗浄液から試してみるのがおすすめです。