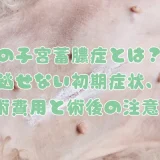「愛犬が最近足を引きずる」「散歩を嫌がるようになった」など、歩き方の変化に不安を感じていませんか。それは、骨の病気のサインかもしれません。犬の骨の病気には、事故による「骨折」から、命に関わる悪性腫瘍である「骨肉腫」まで様々です。特に犬種によってかかりやすい病気があるため、飼い主として正しい知識を持つことが愛犬を守る第一歩となります。
この記事では、犬が発症しやすい骨の病気について、それぞれの症状、考えられる原因、そして最新の治療法までを詳しく解説します。
犬の骨の病気1. 骨折
| 病名 | 骨折 |
|---|---|
| 治療法 | 外科手術、ギプス固定 |
| かかりやすい犬種 | トイプードル、ポメラニアン、イタリアングレーハウンドなどの小型犬 |
どんな病気?
犬の骨折は、交通事故や落下などの強い衝撃によって骨が折れてしまう状態を指します。特にトイプードルなどの小型犬は骨が細いため、日常生活における些細な事故でも前足を骨折してしまうケースが多く見られます。
症状や特徴
犬が骨折すると、患部が目に見えて腫れあがり、強い痛みを伴います。足を骨折した場合は体重をかけられなくなるため、足を引きずったり、地面につけずぶらぶらさせたりします。
ただし、指先などの小さな骨のひび(不全骨折)などの場合、明確な症状が出ないこともあるため注意が必要です。
発症の原因
犬の骨折における最も多い原因は交通事故です。次いで、ソファや飼い主の腕からの落下、ドアに挟まれるといった室内での事故が挙げられます。他の犬との喧嘩で骨折することもあります。
また、くる病や栄養不足により骨密度が低下していると、わずかな衝撃でも骨折しやすくなります。
治療法・防止策
愛犬の足の様子がおかしいと感じたら、無理に動かさず、すぐに動物病院でレントゲン検査などの診察を受けてください。治療法は年齢や骨折部位によりますが、手術で骨を正しい位置に戻して金属プレートなどで固定し、ギプスで保護するのが一般的です。
交通事故を防ぐため、散歩の際は必ずリードを装着しましょう。室内では、滑りやすい床にカーペットを敷いたり、高所から飛び降りられないように家具の配置を工夫したりする環境整備が重要です。
犬の骨の病気2. 骨肉腫
| 病名 | 骨肉腫 |
|---|---|
| 治療法 | 外科手術(断脚など)、化学療法 |
| かかりやすい犬種 | 大型犬(ゴールデンレトリバー、シベリアンハスキー、ロットワイラーなど) |
どんな病気?
骨肉腫は、骨に発生する悪性度の高い腫瘍(がん)です。骨髄や骨膜の細胞ががん化し、骨を破壊しながら増殖するため、非常に強い痛みを引き起こします。犬の骨にできる原発性腫瘍の約8割がこの骨肉腫で、特に四肢に発生しやすい傾向があります。
また、オスの発症率がメスよりもやや高いと報告されています。
症状や特徴
骨肉腫を発症した足には、硬いコブのような腫れが見られます。病気の進行とともに痛みは増し、足を引きずるようになり、最終的には全く歩けなくなることもあります。
このがんは肺など他の臓器へ転移しやすく、肺に転移した場合は咳や呼吸困難といった症状が現れます。
vet監修獣医師先生
発症の原因
骨肉腫の明確な発症原因はまだ解明されていません。しかし、骨が太く大きい大型犬、特に急激な成長期がある犬種での発症が多いことは事実です。過去の骨折や、その治療で体内に埋め込んだ金属プレートが関連している可能性も指摘されています。
治療法
骨肉腫の治療では、痛みのコントロールと転移の抑制が重要になります。多くの場合、第一選択として腫瘍ができた足の切断手術(断脚)が行われます。術後は、目に見えない微小な転移を抑えるために化学療法(抗がん剤治療)を組み合わせることが推奨されます。
vet監修獣医師先生
犬の骨の病気3. 股関節形成不全
| 病名 | 股関節形成不全 |
|---|---|
| 治療法 | 内科的治療(鎮痛剤、体重管理)、外科手術 |
| かかりやすい犬種 | 大型犬(ゴールデンレトリバー、ジャーマンシェパード、ラブラドールレトリバーなど) |
どんな病気?
股関節形成不全は、太ももの骨(大腿骨)と骨盤をつなぐ股関節が、成長過程で正常に形成されない病気です。遺伝的素因が強く関与しており、多くは先天性ですが、成長期の栄養や運動が発症に影響することもあります。
若い大型犬で両足に発症しやすいのが特徴です。
症状や特徴
股関節が不安定なため、腰を左右に振りながら歩く(モンローウォーク)や、両後ろ足を揃えてウサギのように跳ねる歩き方(バニーホップ)といった特徴的な歩行異常が見られます。また、散歩を嫌がる、段差を登れない、座り方がおかしいなどの症状も現れます。
発症の原因
主な原因は遺伝ですが、後天的な要因として、成長期の過度な運動やカロリーの高い食事による急激な体重増加が、関節への負担を増やし症状を悪化させることが知られています。
治療法
若齢で症状が軽い場合は、鎮痛剤の投与や体重管理、運動制限といった内科的治療で痛みをコントロールし、経過を観察します。
症状が重く、歩行に著しい支障が出ている場合は、骨盤の骨を切って角度を調整する骨盤三点骨切り術や、股関節を人工関節に置き換える手術などの外科的治療が検討されます。
vet監修獣医師先生
犬の骨の病気4. 膝蓋骨脱臼
| 病名 | 膝蓋骨脱臼(パテラ) |
|---|---|
| 治療法 | 外科手術、内科的治療 |
| かかりやすい犬種 | 小型犬(チワワ、マルチーズ、トイプードル、ポメラニアンなど) |
どんな病気?
膝蓋骨脱臼は、後ろ足の膝にあるお皿の骨(膝蓋骨)が、正常な位置からずれてしまう(脱臼する)病気で、「パテラ」とも呼ばれます。特に小型犬に多く、多くは内側に脱臼する「内方脱臼」です。
症状や特徴
症状は重症度によってグレード1~4に分類されます。グレード2までは時々足を上げてケンケンする程度の症状ですが、グレード3以上になると骨の変形を伴い、常に脱臼した状態になって歩行に支障をきたします。
放置すると変形性関節症などを併発し、痛みが悪化するため、グレード2以上では獣医師と手術を検討することが推奨されます。
発症の原因
先天的な骨格の異常(膝蓋骨がはまる溝が浅いなど)が主な原因ですが、高い所からの落下や打撲、フローリングで滑るなどの後天的な要因で発症・悪化することもあります。
治療法
膝蓋骨を正常な位置に戻し、再脱臼を防ぐための外科手術が根本的な治療となります。手術方法には、膝蓋骨がはまる溝を深くする、靭帯の位置を調整するなど複数の方法があり、症状に合わせて選択されます。
犬の骨の病気5. レッグ・カルベ・ペルテス病
| 病名 | レッグ・カルベ・ペルテス病(大腿骨頭壊死症) |
|---|---|
| 治療法 | 外科手術 |
| かかりやすい犬種 | 小型犬(トイプードル、ウエストハイランドホワイトテリア、ヨークシャーテリアなど) |
どんな病気?
股関節を形成する大腿骨の先端部分(大腿骨頭)への血流が滞り、骨が壊死してしまう病気です。「大腿骨頭壊死症」とも呼ばれます。治療が遅れると、筋肉の萎縮や永久的な歩行障害が残る可能性があります。
症状や特徴
生後1年未満の成長期にある小型犬に多く発症し、壊死した足に強い痛みが生じるため、足をかばって引きずります。進行すると、抱っこや足を触られることを極端に嫌がるようになります。
発症の原因
明確な原因は不明ですが、遺伝的要因やホルモンの影響などが関与していると考えられています。何らかの理由で大腿骨頭への血液供給が阻害されることで発症します。
治療法
この病気は内科治療での完治は難しく、壊死した大腿骨頭を切除する外科手術(大腿骨頭切除術)が唯一の治療法です。術後はリハビリを行うことで、多くの場合、正常に近い歩行機能を取り戻すことができます
犬の骨の病気6. 変形性骨関節症
| 病名 | 変形性骨関節症 |
|---|---|
| 治療法 | 抗炎症剤投与、体重管理、サプリメント、併発病の治療 |
| かかりやすい犬種 | 全犬種(特に中~高齢の大型犬、肥満犬) |
どんな病気?
関節の軟骨がすり減り、骨が変形することで、慢性的な痛みやこわばりを引き起こす病気です。加齢による一次性のものと、「膝蓋骨脱臼」や「股関節形成不全」など他の関節疾患に続発する二次性のものがあります。
症状や特徴
主な症状は関節の痛みで、散歩に行きたがらない、階段の上り下りを嫌がる、寝起きに動きがぎこちない、などの変化が見られます。関節を動かすと「ポキポキ」「ジャリジャリ」といった異音(捻髪音)が聞こえることもあります。
発症の原因
原因は大きく2つに分けられます。1つは加齢や肥満による関節への長期的な負担で、これはどの犬種でも起こりえますが、特に中・高齢の大型犬に多く見られます。
2つ目は、股関節形成不全や膝蓋骨脱臼、前十字靭帯断裂などの基礎疾患が原因で二次的に発症するケースです。
治療法
完治させる治療法はなく、痛みを管理し、病気の進行を遅らせることが治療の目的となります。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の投与で痛みを和らげ、食事療法による体重管理、関節の健康をサポートするサプリメントの使用などを行います。基礎疾患がある場合は、その治療が優先されます。
犬の骨の病気7. 前十字靭帯断裂
| 病名 | 前十字靭帯断裂 |
|---|---|
| 治療法 | 内科的治療(消炎鎮痛剤)、外科手術 |
| かかりやすい犬種 | 全犬種(特にロットワイラー、ラブラドールレトリバー、肥満犬) |
どんな病気?
膝関節の中にある、太ももの骨とすねの骨をつなぐ「前十字靭帯」が、部分的または完全に断裂してしまう病気です。犬の後ろ足の跛行(はこう)の最も一般的な原因の一つです。
症状や特徴
急に片方の後ろ足を上げてケンケンしたり、足先にわずかにしか体重をかけなかったりといった、はっきりとした歩行異常が見られます。放置すると関節炎が進行し、半月板損傷を併発することもあります。
発症の原因
激しい運動中の急なダッシュや方向転換、ジャンプの着地失敗などで靭帯に強い負荷がかかって断裂する外傷性のケースと、加齢や肥満、骨格の構造により靭帯が徐々に劣化して断裂する変性性のケースがあります。
治療法
体重5kg以下の小型犬で症状が軽い場合は、消炎鎮痛剤の投与と運動制限による内科的治療で改善することもありますが、多くの場合、外科手術が必要です。手術には、靭帯を再建する方法や、骨の形を変えて靭帯がなくても膝を安定させる方法(TPLOなど)があります。
犬の骨の病気8. 関節リウマチ
| 病名 | 関節リウマチ(免疫介在性多発性関節炎) |
|---|---|
| 治療法 | 免疫抑制剤(ステロイドなど)の投与 |
| かかりやすい犬種 | ミニチュアダックスフンド、シェットランドシープドッグ、トイプードルなどの小型犬 |
どんな病気?
自身の免疫機能が誤って自分の関節を攻撃してしまう自己免疫疾患の一種です。複数の関節(特に手首や足首など末端の小さな関節)に同時に炎症が起こります。
症状や特徴
関節の腫れや痛みのほか、発熱、元気・食欲の低下、関節のこわばりといった全身症状が見られます。特に朝起きた時などに動きが硬くなるのが特徴です。若齢で発症すると重症化しやすい傾向があります。
発症の原因
自己免疫機能に異常が生じることが原因ですが、なぜ異常が起きるのか、その明確な引き金はわかっていません。遺伝的な素因や、何らかの感染症が関与している可能性が考えられています。
治療法
過剰な免疫反応を抑えるため、ステロイド剤や免疫抑制剤を投与する内科的治療が中心となります。関節への負担を減らすための体重管理も重要です。完治は難しいですが、薬で症状をコントロールし、生活の質を維持することを目指します。
犬の骨の病気9. くる病
| 病名 | くる病(骨軟化症) |
|---|---|
| 治療法 | 食事療法、ビタミンD・カルシウムの投与 |
| かかりやすい犬種 | 全犬種(特に成長期の大型犬) |
どんな病気?
成長期の子犬において、ビタミンDやカルシウム、リンの不足により、骨が正常に石灰化できずに変形や成長障害が起こる病気です。成犬で同様の状態になった場合は「骨軟化症」と呼ばれます。
症状や特徴
骨が軟らかくなるため、足がO脚やX脚のように曲がったり、関節が腫れたりします。痛みから歩きたがらなくなり、骨密度も低下するため、わずかな衝撃で骨折しやすくなります。
発症の原因
手作り食などで栄養バランスが極端に偏った食事を与え続けている場合に発症します。また、日光浴不足は体内のビタミンD合成を妨げ、カルシウムの吸収効率を低下させるため、室内飼育で散歩の機会が少ない犬も注意が必要です。
治療法
栄養バランスの取れた総合栄養食への切り替えや、ビタミンD、カルシウム、リンのサプリメント投与といった食事療法が中心となります。消化器疾患などで栄養吸収がうまくいっていない場合は、その病気の治療も並行して行います。
vet監修獣医師先生
犬の骨の病気10. 汎骨炎
| 病名 | 汎骨炎 |
|---|---|
| 治療法 | 運動制限、鎮痛剤の投与 |
| かかりやすい犬種 | ジャーマン・シェパードなどの中・大型犬の若齢犬 |
どんな病気?
主に大型犬の若齢期(生後5~18ヶ月頃)にみられる、長骨(腕や足の長い骨)の骨髄に原因不明の炎症が起こる病気です。強い痛みを伴いますが、多くは成長とともに自然に治癒する一過性の疾患です。
症状や特徴
突然、強い痛みから足を引きずるのが特徴で、痛む足が右前足から左後ろ足へ、というように移動することがあります。発熱や元気・食欲の低下を伴うこともあります。
発症の原因
明確な原因は不明ですが、急激な骨の成長に関連していると考えられており、遺伝的素因や栄養、ストレスなどが関与している可能性が指摘されています。
治療法
特定の治療法はなく、対症療法が中心となります。痛みが強い期間は運動を制限し、必要に応じて鎮痛剤を投与して痛みを和らげます。ほとんどの場合、1~2歳になる頃には自然に症状は見られなくなります。
vet監修獣医師先生
犬の骨の病気、防止する方法は?
ここまで10種類の病気を紹介しましたが、重篤化すると断脚手術や生涯にわたる投薬が必要になる病気が少なくありません。
愛犬の骨の健康を守る上で最も重要なのは、病気のサインを見逃さないための早期発見です。日頃からマッサージなどのスキンシップを通じて、体を触られるのを嫌がらないか、不自然な腫れやしこりがないかを確認しましょう。
散歩中の歩き方を注意深く観察し、足を引きずる、ケンケンする、腰を振るなどの変化があれば、それは骨の病気のサインかもしれません。異常に気づいたら、自己判断せずに速やかに動物病院を受診してください。
また、骨折や脱臼は他の病気を併発する引き金にもなります。フローリングには滑り止めのマットを敷く、ソファなどにはステップを設置する、肥満にならないよう体重管理を徹底するなど、関節に負担をかけない生活環境を整えることも非常に有効な予防策です。
骨の病気は重篤化しやすいからこそ早期発見を
犬の骨の病気は、痛みを伴い歩行困難を引き起こすだけでなく、骨肉腫のように命を脅かすものもあります。言葉を話せない愛犬の痛みにいち早く気づいてあげられるのは、一番近くにいる飼い主さんだけです。
この記事で解説した病気の症状や原因、治療法は、愛犬と暮らすすべての飼い主さんに知っておいてほしい知識です。日々の観察を怠らず、少しでも気になることがあれば、ためらわずに獣医師に相談しましょう。