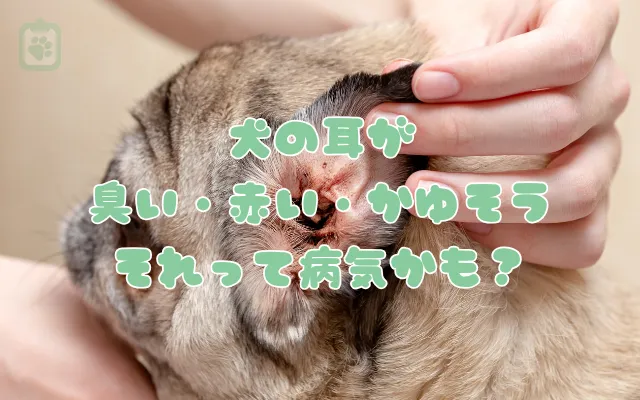愛犬の健康状態を知るための重要なサインの1つが「耳」です。健康な犬の耳は清潔で特有の臭いがなく、ピンク色をしています。もし、愛犬の耳が臭ったり、頻繁に痒がったりしている場合、それは何らかの病気のサインかもしれません。
この記事では、犬の耳に起こりやすいトラブルの原因と対処法を解説します。「最近、愛犬が耳を気にしているな」と感じる飼い主さんは、ぜひこの記事を参考に愛犬の耳をチェックしてみてください。
犬の耳が臭いときは病気?
犬の耳から酸っぱいような、あるいはツンとくるような悪臭がする場合、病気を疑う必要があります。健康な耳垢自体に強い臭いはないため、耳から不快な臭いがするときは、耳の中で細菌や真菌が繁殖している可能性が高いです。
耳が臭くなる代表的な病気には、「外耳炎」や「中耳炎」があります。これらは、耳道内で細菌やマラセチア(真菌の一種)が増殖することで引き起こされます。動物病院では、原因菌を特定したうえで、耳の洗浄や点耳薬、場合によっては抗生物質の投与といった治療が行われます。
特に、高温多湿な日本の環境は、耳の中で菌が繁殖しやすく、外耳炎などを発症しやすい傾向にあります。すでに炎症が起きている状態で自己判断で耳掃除をすると、かえって耳道を傷つけ、症状を悪化させてしまう危険性があります。
愛犬の耳の臭いが気になったら、まずはかかりつけの獣医師に相談することが最も重要です。病気と診断された場合は速やかに治療を開始しましょう。治療後の健康な状態を維持するために、獣医師の指導のもとで定期的な耳掃除(週に1〜2回が目安)を行うのがおすすめです。ただし、耳掃除のしすぎはデリケートな耳を傷つける原因になるため、適切な頻度を守りましょう。
犬の耳が赤いときは病気?
犬の耳が赤く見える場合、いくつかの原因が考えられます。特に、耳がパンパンに腫れているときは「耳血腫(じけっしゅ)」の可能性があります。
耳血腫とは、耳介(耳のひらひらした部分)の血管が破れて内部に血液が溜まり、赤く腫れあがる病気です。原因は様々で、以下のようなものが挙げられます。
- 外耳炎などによる強いかゆみで、耳を激しく掻いたり振ったりする
- 他の犬とのケンカや打撲による外傷
- アレルギーや細菌感染
- ノミやダニの寄生
耳血腫は自宅での治療が困難なため、発見したらすぐに動物病院を受診してください。悪化させないよう、犬が耳を掻けないようにエリザベスカラーを装着するのも有効です。
また、耳の赤みは「外耳炎」や「アレルギー」のサインでもあります。炎症がひどい場合は内服薬や点耳薬による治療が必要です。アレルギーが疑われる場合は、アレルゲンを除去した食事(除去食)を試したり、抗アレルギー薬を投与したりして原因を特定していきます。
犬の耳がかゆいときは病気?
犬がしきりに耳を掻いたり、頭を振ったり、床に耳をこすりつけたりするのは、強いかゆみを感じているサインです。犬が耳をかゆがる場合、外耳炎やアレルギー性皮膚炎など、様々な病気の可能性が考えられます。
特に注意したいのが「耳ダニ感染症(耳疥癬)」です。これは「ミミヒゼンダニ」という非常に小さなダニが耳の中に寄生する病気で、激しいかゆみを引き起こします。黒くて乾いたワックス状の耳垢が大量に出るのが特徴です。
耳ダニは耳垢を栄養源にして繁殖を繰り返し、感染した犬や猫との接触でうつります。多頭飼育の場合は、他のペットにも感染が広がらないよう注意が必要です。かゆがる様子が見られたら、すぐに動物病院で診てもらいましょう。
犬の耳にカビがはえることもあるの?
はい、犬の耳には「マラセチア」という常在菌(カビの一種である酵母菌)が存在しており、これが異常繁殖すると外耳炎などのトラブルを引き起こします。
マラセチアは、健康な犬の皮膚や耳道にも少数存在していますが、皮脂が多く湿度が高い環境を好むため、何らかの原因で耳の中の環境が悪化すると爆発的に増殖します。これにより、ベタベタした茶色い耳垢や独特の甘酸っぱい臭い、強いかゆみといった症状が現れます。これが「マラセチア性外耳炎」です。
垂れ耳の犬種やアレルギー体質の犬は、耳が蒸れやすく皮脂の分泌も多いため、特にマラセチアが増殖しやすい傾向にあります。耳の中を清潔で健康な状態に保ち、マラセチアが過剰に繁殖しないようケアしてあげることが大切です。
犬の耳を観察して変化に気づいてあげよう
犬の耳は、体調の変化が表れやすいデリケートな器官です。日頃から愛犬の耳をチェックする習慣をつけることで、病気の早期発見につながります。
「臭い」「赤い」「かゆがる」「耳垢が多い」といった変化は、愛犬からの重要なSOSサインです。耳のトラブルは、放置すると中耳炎や内耳炎に進行し、聴力に影響を及ぼすこともあります。自宅でのケアだけで治すのは難しいため、少しでも異変に気づいたら自己判断せずに、すぐに動物病院で専門家の診断を受けるようにしてください。早期治療が、愛犬の健康と快適な生活を守る鍵となります。