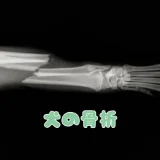犬の耳垢は、普段の適切なケアで多くのトラブルを防ぐことができます。
健康な犬でも耳垢は出ますが、もし愛犬の耳垢が「黒い」「臭い」、あるいは耳を触られるのを嫌がるそぶりを見せたら、それは外耳炎などの病気のサインかもしれません。
この記事では、獣医師監修のもと、犬の耳垢に隠された病気のサインや原因、動物病院での診断・治療法、そして自宅でできる正しいケア方法について詳しく解説します。
犬の耳垢、症状は?
- 耳垢が異常に溜まる
- 耳垢が黒い・茶色い
- 耳から異臭がする(酸っぱい、生臭いなど)
- 耳垢がベトベト、あるいはカサカサしている
- 耳から膿のような分泌物が出る
- 耳介(耳のひらひらした部分)が赤い・腫れている
健康な犬の耳垢は、通常は黄色がかった白色で、ベタつきや臭いはほとんどありません。しかし、細菌や真菌・寄生虫などに感染すると、上記のような犬の耳垢の異常な症状が現れます。
また、耳の痒みや痛みから、次のような行動の変化が見られるようになります。
- しきりに耳を掻く
- 頻繁に頭を振る
- 耳を床や家具に擦り付ける
- 耳を触られることを極端に嫌がる
犬の耳垢、原因は?
- 細菌の増殖
- 真菌(マラセチア)の増殖
- 寄生虫(ミミヒゼンダニ)の感染
犬の耳垢が異常に増える場合、その背景には外耳炎や中耳炎といった病気が隠れていることがほとんどです。
これらの病気は主に「細菌」「真菌(カビ)」「寄生虫」の感染によって引き起こされ、耳の炎症や、頭を頻繁に振るなどの行動につながります。
細菌
犬の耳垢トラブルで最も一般的な原因の一つが細菌の増殖です。代表的な原因菌にはブドウ球菌(スタフィロコッカス属)やレンサ球菌(ストレプトコッカス属)などがあり、これらが増殖すると悪臭を伴う乳白色や黄色のベタついた耳垢が見られます。
症状が進行すると耳の中がただれたり、外耳道の皮膚が厚く硬くなる(肥厚)ことで耳の穴が狭くなってしまうこともあります。
真菌
マラセチアという真菌(カビの一種)も、犬の耳垢の一般的な原因です。マラセチアは健康な犬の皮膚にも存在する常在菌ですが、アレルギーや皮脂の過剰分泌、湿気などによって異常増殖すると外耳炎を引き起こします。独特の甘酸っぱい臭いを放つ、茶色から黒褐色のベトベトした耳垢が大量に発生するのが特徴で、強い痒みを伴います。
寄生虫
ミミヒゼンダニ(耳ダニ)という寄生虫の感染も、耳垢の原因となります。ミミヒゼンダニが寄生すると、コーヒーの出がらしのような黒く乾燥した耳垢が大量に溜まります。この感染は非常に強い痒みと痛みを伴うため、「耳を激しく掻く」「頭を何度も振る」「耳を床や家具に擦り付ける」といった行動が特徴的です。
犬の耳垢、診断方法は?
- 耳鏡検査・耳垢細胞診
動物病院では、犬の耳垢の原因を特定するために、主に耳鏡検査や耳垢細胞診を行います。
耳鏡で耳の中の状態を観察した後、綿棒などで採取した耳垢をスライドガラスに塗り、顕微鏡で観察します。この検査によって、原因が細菌なのか、真菌(マラセチア)なのか、あるいはミミヒゼンダニのような寄生虫なのかを判断し、炎症の程度も確認します。原因を特定するために、耳垢を染色したり、細菌培養検査や薬剤感受性試験(どの薬が効くかを調べる検査)を追加で行うこともあります。
犬の耳垢、治療はどのように行う?
- 耳の洗浄と耳垢の除去
- 原因に応じた点耳薬・駆虫薬の投与
- 内服薬の併用(重症の場合)
犬の耳垢トラブルの治療は、診断で特定された原因に応じて行われます。基本は「耳の洗浄」と「原因に合わせた投薬」です。
細菌が原因の場合
まず、専用の洗浄液で外耳道を優しく洗浄し、耳垢や膿を丁寧に取り除きます。その後、原因菌に有効な抗菌薬の点耳薬を投与します。炎症がひどい場合や、中耳炎にまで進行している場合は、内服の抗菌薬を併用することもあります。
真菌が原因の場合
細菌感染と同様に、まずは耳の洗浄で大量の耳垢を除去します。その後、抗真菌薬の点耳薬を使用して、原因であるマラセチアの増殖を抑えます。痒みが強い場合は、痒み止めの薬を併用することもあります。
寄生虫が原因の場合
ミミヒゼンダニが原因の場合も、まず耳を洗浄して耳垢の塊を取り除きます。その後、駆虫薬(イベルメクチンなど)の点耳薬や滴下薬を投与してダニを駆除します。
ただし、コリー系の犬種(ボーダーコリー、シェットランドシープドッグなど)は、特定の遺伝子(MDR1遺伝子変異)を持っている場合、イベルメクチンなどの薬で重篤な副作用が出ることがあります。必ず獣医師の診断と指示に従って、安全な治療を受けてください。
犬の耳垢、対策はできる?
犬の耳垢トラブルは、日頃のケアで予防・対策することが可能です。
ご家庭での耳掃除は、犬用のイヤークリーナー(洗浄液)を染み込ませたコットンやガーゼで、見える範囲の耳介(耳のひらひらした部分)と外耳道の入り口を優しく拭うだけで十分です。奥まで無理に掃除しようとすると、かえって耳道を傷つけたり、耳垢を奥に押し込んでしまう危険があるので注意しましょう。
また、耳の病気を根本から予防するためには、以下の点も重要です。
- バランスの取れた食事で免疫力を維持する
- シャンプー後は耳の周りをしっかり乾かす
- 他の犬との接触後は耳の状態をチェックする
- アレルギーがある場合は、その管理を徹底する
毎日の耳チェックや2週間に1回程度の耳のケア、定期的な健康診断を心がけることが大切です。
vet監修獣医師先生
垂れ耳の犬種は入念なチェックを!
アメリカン・コッカー・スパニエルやゴールデン・レトリバー、キャバリアなどの垂れ耳の犬種は、耳の中が蒸れやすく、外耳炎になりやすい傾向があります。また、耳が垂れているため炎症や汚れに気づきにくく、発見が遅れがちです。
毎日のコミュニケーションの一環として耳をめくり、赤みや臭い、耳垢の量に異常がないかを確認する習慣をつけましょう。
早期発見・早期治療を心がけよう!
犬の耳垢の異常は、命に直接関わることは稀ですが、放置すると慢性化して治療が長引いたり、中耳炎や内耳炎に進行して聴力に影響が出ることもあります。何より、愛犬にとっては強い痒みや痛みが続くつらい状態です。
愛犬が快適な毎日を送れるよう、定期的な耳のチェックとケアを習慣にし、異常を感じたらすぐに動物病院を受診することが、早期発見・早期治療の鍵となります。