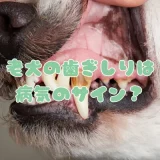愛犬が突然「ヒック、ヒック」としゃっくりを始めると、苦しそうで心配になりますよね。犬のしゃっくりは人間とメカニズムが似ており、多くは一時的なものですが、中には注意が必要なケースもあります。
しゃっくりは基本的には問題ありませんが、頻度や長さ、他の症状によっては病気のサインとなっている場合もありますよ。
この記事では、犬のしゃっくりの原因や症状、ご家庭でできる止め方、そして見逃してはいけない病気のサインについて詳しく解説します。
犬のしゃっくりとは?どんな症状?
犬も人間と同じように、しゃっくりをすることがあります。このしゃっくりのメカニズムは、胸とお腹を隔てている筋肉「横隔膜」が何らかの刺激で痙攣(けいれん)することによって起こる、生理的な反射運動です。
症状としては、人間のように「ヒック」と短い音を出しながら、体全体がピクッと動きます。特に子犬は横隔膜が未発達なためしゃっくりをしやすいですが、成犬でも起こります。
しゃっくり自体は病気ではありませんが、愛犬はいつもと違う体の動きに不快感を感じているかもしれません。
愛犬のしゃっくりが起こる原因と正しい止め方を知り、落ち着いて対処してあげましょう。
犬がしゃっくりをする原因は?
前述した通り、犬のしゃっくりは横隔膜が痙攣することで起こります。その痙攣を引き起こす、主な4つの原因について見ていきましょう。
- 1.食事
- 2.ストレス
- 3.体質(特に子犬)
- 4.病気
1.食事
犬のしゃっくりの原因として、最も一般的に考えられるのが食事に関連するものです。
- 一気に食べてしまう(早食い)
- 餌の量や形が合っていない
- 冷たいものを摂取する
一気に食べてしまう
早食いをすると、食べ物と一緒に空気をたくさん飲み込んでしまい、胃が急激に膨らみます。その結果、横隔膜が刺激され、しゃっくりの原因となることがあります。
愛犬の早食いがなかなか治らない場合は、一度に与えるフードの量を減らして食事回数を増やしたり、早食い防止用の機能性食器を活用したりするのがおすすめです。
vet監修獣医師先生
餌の量や硬さが合ってない
フードの量や粒の硬さが愛犬の体格や年齢に合っていない場合も、しゃっくりを引き起こすことがあります。
フードが体に合っていないと、消化不良を起こして胃にガスが溜まりやすくなり、横隔膜を刺激してしまうのです。
消化器への負担は、しゃっくりだけでなく様々な内臓疾患のリスクを高めるため、フードの見直しも検討しましょう。
胃が冷える
冷たい水や食べ物が急に胃の中に入ると、その温度変化が刺激となって横隔膜が痙攣し、しゃっくりの原因になることがあります。
特に夏場は、冷たいものを一度にたくさん与えすぎないように注意してあげてください。
2.ストレス
精神的なストレスや興奮も、犬のしゃっくりの原因となります。
強いストレスや、遊びすぎによる疲労などで自律神経が乱れ、呼吸が浅くなると、横隔膜が痙攣してしゃっくりが起こることがあります。また、飼い主さんと離れることへの分離不安が原因となるケースもあります。
適度な運動と十分な休養のバランスを心がけ、愛犬がリラックスできる環境を整えてあげましょう。
3.体質
しゃっくりは、体質によって出やすい犬もいます。
特に体の機能がまだ発達しきっていない子犬は、わずかな刺激でも横隔膜が痙攣しやすいため、成犬に比べてしゃっくりをしやすい傾向があります。
4.病気
ほとんどのしゃっくりは生理現象ですが、稀に病気の症状として現れることがあります。
しゃっくりが長時間止まらない、頻繁に繰り返す、他の症状も伴うといった場合は注意が必要です。重大な病気の可能性も考えられるため、少しでも疑いがあればすぐに動物病院を受診しましょう。
- 喘息
- 肺炎
- 心膜炎
- そのほか胸部の腫瘍や神経系の疾患など
喘息
犬の喘息は、ハウスダストや花粉などのアレルゲン、タバコの煙、急な寒暖差などが原因で気管支が収縮し、発作的な咳や呼吸困難を引き起こす病気です。
この呼吸器系の異常が横隔膜に影響を与え、しゃっくりが症状の一つとして現れることがあります。
肺炎
肺炎は、ウイルスや細菌、カビなどの感染によって肺に炎症が起こる病気です。
咳や呼吸困難、発熱、食欲不振といった症状が見られ、正常な呼吸のリズムが崩れることで横隔膜が刺激され、しゃっくりが出ることがあります。
心内膜炎
心内膜炎は、心臓の内部にある心内膜や弁に細菌が感染して炎症を起こす病気です。
症状としては、発熱や元気消失、心雑音、不整脈などが挙げられます。心臓の機能低下が呼吸に影響を与え、結果としてしゃっくりを引き起こす場合があります。
心臓の病気は症状が分かりにくいため、定期的な健康診断による早期発見が非常に重要です。
愛犬のしゃっくりをそのままにしてたらまずいの?
犬のしゃっくりは、数分程度で自然に止まることがほとんどです。そのため、基本的には様子を見ていても問題ありません。
ただし、長時間続いて苦しそうにしている場合や、ぐったりするなどの異変が見られる場合は、病気の可能性も考えられます。その際は、次にご紹介する方法を試したり、動物病院に相談したりすることをおすすめします。
犬のしゃっくりの正しい止め方は?
愛犬のしゃっくりがなかなか止まらず、つらそうな時は以下の方法を試してみてください。呼吸のリズムを変え、横隔膜の痙攣を落ち着かせる効果が期待できます。
- 水を少し飲ませる
- おやつを少量与えて意識をそらす
- おもちゃで軽く遊んで気分転換させる
- みぞおちのあたりを優しくマッサージする
これらの方法は、犬の意識を別のことに向けさせ、乱れた呼吸のリズムを整えることでしゃっくりを止める仕組みです。
みぞおち(胸骨の下の柔らかい部分)のマッサージは、横隔膜の痙攣を物理的に和らげるのに役立つと言われています。優しく撫でてリラックスさせてあげましょう。
なかなか止まらない時は?
上記の方法を試しても一向にしゃっくりが止まらない場合や、1日に何度も繰り返す場合は、病気や「逆くしゃみ」など他の症状の疑いがあります。
特に元気や食欲がない、嘔吐や下痢を伴うなど、他に異常が見られる場合は、早急に動物病院を受診し、獣医師に相談してください。
愛犬が睡眠中にしゃっくりをする。どうすればいい?
犬が睡眠中にしゃっくりをしたり、ピクピクと体を動かしたりすることがあります。これは、人間と同じように浅い眠り(レム睡眠)の時に夢を見ている可能性が高いです。
この場合のしゃっくりは生理的なもので、基本的には心配いりません。無理に起こさず、そっと見守ってあげましょう。
ただし、明らかに苦しそうな様子で長時間続く場合は、一度優しく起こして水を飲ませるなどして、しゃっくりを止めてあげると良いでしょう。
愛犬がしゃっくり中に嘔吐する場合は?
しゃっくりと同時に嘔吐が見られる場合は、注意が必要です。考えられる原因はいくつかあります。
- 食事の早食いや食べ過ぎ
- 消化器系のトラブル
- 胃捻転や異物の誤飲など重篤な病気
しゃっくり中に嘔吐してしまった場合、まずは早食いや食事量が原因ではないか見直してみてください。
それでも改善しない場合は、消化器系の不調や何らかの病気を患っている可能性が考えられます。自己判断せず、速やかに動物病院を受診することをおすすめします。
しゃっくりと間違えやすい他の症状
犬のしゃっくりと間違えやすい症状として、「逆くしゃみ」が挙げられます。
逆くしゃみ
くしゃみが息を勢いよく「吐き出す」現象であるのに対し、逆くしゃみは鼻から息を連続的に、発作的に「吸い込む」現象です。
「フガフガ!」「グーグー!」と、まるで豚が鳴いているかのような音を突然出すのが特徴で、特にチワワやトイプードルなどの小型犬や、鼻の短い短頭種によく見られます。
原因ははっきりしていませんが、逆くしゃみ自体は病気ではないとされています。通常は数十秒から1分程度で自然に治まりますが、あまりに頻繁な場合はアレルギーなどの可能性も考えられます。
異変を見落とさない
犬のしゃっくりは多くの場合、心配のない生理現象です。しかし、この記事で解説したように、時には病気が隠れているサインである可能性も潜んでいます。
愛犬のしゃっくりが「いつもと違うな」と感じたら、その小さなサインを見逃さないことが何より重要です。長時間止まらない、嘔吐や元気消失など他の症状を伴うなど、少しでも不安な点があれば、かかりつけの獣医師に相談しましょう。
日頃から愛犬の様子をよく観察することが、愛犬の健康を守る第一歩ですよ。