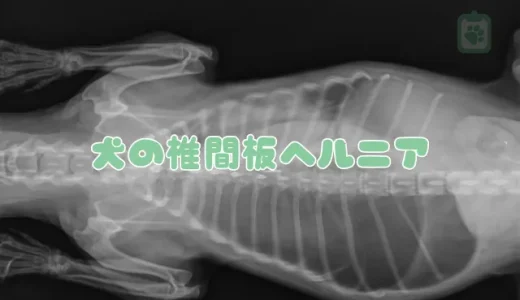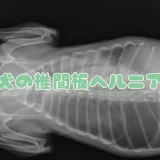愛犬にはいつまでも元気でいてほしい、そう願うのはすべての飼い主さんに共通する想いです。しかし、犬も人間と同じように、先天的な要因や加齢によって脳や神経の病気を発症することがあります。
✓ 犬の脳や神経の病気にはどんな種類がある?
✓ どんな症状が出たら注意すべき?
✓ 治療法や予防法はあるの?
こうした疑問や不安を感じるかもしれませんが、多くの病気は早期発見と適切な治療で対応が可能です。
大切なのは、愛犬が見せるささいな変化に気づけるよう、飼い主さんが病気の症状・原因・治療法について事前に知識を持っておくことです。この記事では、犬の代表的な脳・神経の病気や関連する感染症10種を、症状や原因、治療法とともに詳しく解説します。
愛犬と一日でも長く健やかな毎日を過ごすために、一緒に学んでいきましょう。
犬の脳・神経の病気1. 「水頭症」
| 病名 | 水頭症 |
|---|---|
| 治療法 | 内科治療(薬)、外科治療(手術) |
| 好発犬種 | チワワ、トイ・プードル、マルチーズ、ヨークシャー・テリア、ボストン・テリア、ケアン・テリア、パグ、ブルドッグ、ペキニーズ、シー・ズー |
水頭症とは、脳の中を満たしている脳脊髄液が過剰に溜まり、脳を内側から圧迫してしまう病気です。緊急性は高くないものの、生涯にわたる治療やケアが必要になることが多い病気として知られています。
軽度の場合は無症状のこともありますが、進行すると「意識障害」「視覚障害」「知覚の鈍化」「てんかん発作」など、様々な神経症状を引き起こします。
症状や特徴
先天性の水頭症では、頭がドーム状に大きく膨らんでいたり、目が外側を向く「外斜視」が見られたり、他の子犬に比べて発育が遅いといった特徴的な外見の変化が現れることがあります。
その他、脳の圧迫に伴う症状として、ぼーっとして反応が鈍くなる、性格が変わる、同じ場所をぐるぐる回る(旋回運動)、ふらつき、頭を壁などに押し付けるといった行動異常が見られます。
一方で、画像検査で水頭症の所見があっても、臨床症状が全く現れない犬も少なくありません。
発症原因
生まれつき脳室の形に異常がある「先天性」のものと、脳腫瘍や頭部の外傷、髄膜炎などによって脳脊髄液の流れが滞ることで発症する「後天性」のものがあります。
治療法
治療は、内科治療と外科治療の2つに大別されます。内科治療では、利尿薬やステロイドを用いて脳脊髄液の産生を抑え、脳圧を下げます。外科治療では、「シャントチューブ」と呼ばれる細い管を体に埋め込み、過剰な脳脊髄液を脳からお腹(腹腔)へ流す手術が行われます。
水頭症を確実に予防する方法はないため、疑わしい症状が見られたら速やかに動物病院を受診することが重要です。
引用元:水頭症
犬の脳・神経の病気2. 「てんかん」
| 病名 | てんかん |
|---|---|
| 治療法 | 抗てんかん薬の投薬 |
| 好発犬種 | ゴールデン・レトリーバー、ビーグル、シェパード、ボーダー・コリー、ボクサー、ダックスフンド、プードル など |
犬のてんかんは、脳の神経細胞が異常に興奮することで、けいれんなどの「てんかん発作」を繰り返し引き起こす脳の病気です。
発作の程度は、体がわずかにピクつくだけの軽微なものから、全身が激しくけいれんする重度のものまで様々です。脳の構造的な異常が原因の「構造的てんかん」と、原因が特定できない「特発性てんかん」に分けられ、犬では特発性てんかんが多く、1〜5歳の若いうちに最初の発作を起こす傾向があります。
症状や特徴
数日から数週間おきに発作を繰り返すのが特徴です。代表的な症状には、「全身の硬直」「手足のバタつき」「大量のよだれ」「失禁」「鳴き叫ぶ」などがあります。
全身が突っ張る「強直性発作」や、ガクガクと震える「間代性発作」が全身発作の典型です。顔や手足など、体の一部だけに症状が現れる「焦点発作(部分発作)」も見られます。
発症原因
一部の犬種では遺伝的な関与が指摘されていますが、特発性てんかんの明確な発症原因は、現在のところ解明されていません。
治療法
治療の主な目的は、抗てんかん薬の投薬によって発作の頻度や重症度をコントロールすることです(対症療法)。
発作が5分以上続いたり、短い間隔で発作を繰り返したりする「てんかん重積状態」に陥った場合は、命に関わるため、すぐに動物病院で注射などの緊急処置を受ける必要があります。
治療の目標は発作を完全にゼロにすることではなく、日常生活に支障がないレベルまで抑えることです。多くの場合、薬は生涯にわたって飲み続ける必要があります。
犬の脳・神経の病気3. 「脳梗塞」
| 病名 | 脳梗塞 |
|---|---|
| 治療法 | 血栓溶解療法、酸素吸入、ステロイド剤・利尿剤投与など |
| 好発犬種 | 全ての犬種 |
犬の脳梗塞は、脳の血管が血栓(血の塊)などで詰まり、その先の脳細胞に血液が届かなくなることで、脳組織が壊死してしまう病気です。犬における脳血管障害の中では最も発生が多いとされますが、犬全体での発生率は稀です。
脳のどの部分で梗塞が起きたかによって、現れる症状が異なるのが特徴です。
症状や特徴
症状は前触れなく、突然現れます。代表的なものに、ふらつきや旋回運動(ぐるぐる回る)、麻痺などがあります。
大脳で発症した場合は「けいれん」「旋回運動」「嗅覚の麻痺」、小脳で発症した場合は「首が傾く(斜頸)」「眼球が揺れる(眼振)」といった症状が見られます。
発症原因
犬の脳梗塞の直接的な原因は特定されていませんが、心臓病、腎臓病、甲状腺機能低下症、副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)などの基礎疾患や、脱水、高血圧などがリスクを高めると考えられています。
治療法
脳梗塞の治療は、発症からの経過時間によって治療法が大きく異なります。
発症後3時間以内
血栓を溶かす薬(血栓溶解剤)を投与する「血栓溶解療法」が選択されることがあります。ただし、重篤な副作用のリスクもあるため、適応は慎重に判断されます。
発症後3時間が経過
血栓溶解療法の適応時間を過ぎた場合は、脳のダメージを最小限に抑えるための対症療法が中心となります。脳の腫れを抑えるステロイド剤や利尿剤の投与、酸素吸入、点滴による循環改善などが行われます。
犬の場合、人間のように外科手術で血栓を取り除く治療は一般的ではありません。
犬の脳・神経の病気4. 「トキソプラズマ症」
| 病名 | トキソプラズマ症 |
|---|---|
| 治療法 | 抗生剤、対症療法 |
| 好発犬種 | 全ての犬種 |
トキソプラズマ症は、「トキソプラズマ」という名前の原虫(寄生虫)に感染することで発症する人獣共通感染症(ズーノーシス)です。血液検査で抗体を測定することで診断します。
症状や特徴
健康で免疫力が正常な犬の場合、感染しても症状が出ない「不顕性感染」がほとんどです。症状が出る場合でも、「発熱」や「筋肉痛」といった軽いものが主です。
ただし、子犬や免疫力が低下している犬が感染すると、「肺炎」「肝炎」「脳炎」など重篤な症状を引き起こすことがあります。また、妊娠中の犬が感染すると、流産や死産の原因となる可能性があります。
発症原因
主な感染経路は、トキソプラズマのオーシスト(虫卵のようなもの)に汚染された猫の糞便を口にしたり、感染した豚や鶏の生肉を食べたりすることです。
治療法
治療には抗生剤を投与します。発熱などの症状がある場合は、それらを和らげる対症療法も並行して行います。トキソプラズマは人間、特に妊婦さんが感染すると胎児に影響を及ぼす可能性があるため、愛犬の感染が疑われる場合はしっかりと治療することが大切です。
犬の脳・神経の病気5. 「脳腫瘍」
| 病名 | 脳腫瘍 |
|---|---|
| 治療法 | 外科手術、放射線療法、化学療法、支持療法 |
| 好発犬種 | ボクサー、ゴールデン・レトリーバー、ボストンテリア、フレンチブルドック |
脳腫瘍は、脳の内部に腫瘍(できもの)ができる病気で、特に中〜高齢の犬に多く見られます。脳そのものから発生する「原発性脳腫瘍」と、体の他の部位からがんが転移してきた「転移性脳腫瘍」があります。
症状や特徴
脳腫瘍によって引き起こされる症状で最も多いのが、てんかん発作(けいれん)です。その他、腫瘍ができた場所によって、「首が傾く(斜頸)」「同じ方向へぐるぐる回る(旋回運動)」「性格の変化」「視力障害」など、様々な神経症状が現れます。
腫瘍が小さいうちは無症状のことも多く、飼い主さんが異変に気づいたときには、すでに病状が進行しているケースも少なくありません。
発症原因
遺伝的素因や過去の頭部の外傷などが関連している可能性も指摘されていますが、脳腫瘍の明確な発生原因はまだ解明されていません。
治療法
治療は、腫瘍の種類や発生部位、犬の状態によって異なりますが、主に外科手術、放射線療法、化学療法(抗がん剤)を単独、または組み合わせて行います。
腫瘍を直接治療するのではなく、ステロイド剤などで脳の圧迫を和らげ、症状を軽減させる「支持療法(緩和治療)」も重要な選択肢の一つです。
犬の脳・神経の病気6. 「ジステンパーウイルス感染症」
| 病名 | ジステンパーウイルス感染症 |
|---|---|
| 治療法 | 支持療法(点滴、抗生剤投与など) |
| 好発犬種 | すべての犬種 |
ジステンパーウイルス感染症は、「犬ジステンパーウイルス」によって引き起こされる、非常に感染力が強く致死率も高い伝染病です。感染犬のくしゃみや咳などの飛沫を介して空気感染します。
特に、母犬からの免疫が切れる生後数ヶ月の子犬は感染リスクが最も高くなります。感染すると、数週間から数ヶ月で死に至ることもある恐ろしい病気です。
症状や特徴
初期には「発熱」「目やに」「黄緑色の鼻水」といった風邪のような症状が見られます。進行すると、「嘔吐・下痢などの消化器症状」、「咳などの呼吸器症状」に加え、神経症状として「けいれん発作」や「麻痺」などが現れます。また、鼻の頭や肉球の皮膚が硬くなる「ハードパッド」も特徴的な症状です。
発症の原因
感染した犬の目やに、鼻水、唾液、排泄物などに含まれるウイルスに接触したり、ウイルスを含んだ飛沫を吸い込んだりすることで感染します。
治療法
このウイルスに直接効く特効薬はないため、治療は点滴や二次感染を防ぐための抗生剤投与、けいれんを抑える薬などを用いた支持療法が中心となります。
ジステンパーは、混合ワクチン接種で確実に予防できる病気です。万が一感染した場合は、他の犬への感染拡大を防ぐため、厳重な隔離が必要です。
犬の脳・神経の病気7. 「認知症」
| 病名 | 認知症(認知機能不全症候群) |
|---|---|
| 治療法 | 薬物療法、食事療法、サプリメント、環境改善 |
| 好発犬種 | 柴犬などの日本犬や日本犬系の雑種 |
犬の認知症(認知機能不全症候群)は、加齢に伴って脳の機能が低下し、様々な行動の変化が現れる状態を指します。一般的に11〜12歳頃から発症率が高まり、高齢になるほど多く見られます。
症状や特徴
人間と同様に、脳内に「アミロイドβ」というタンパク質が蓄積することが一因とされています。症状は多岐にわたり、「飼い主を認識できない」「急に攻撃的になる」「夜鳴き」「徘徊」「トイレの失敗」などが代表的です。
他にも、部屋の隅や狭い場所で動けなくなる、意味もなく吠え続ける、昼夜が逆転して夜中に活動する、といった行動が見られるようになります。
発症原因
加齢による脳の萎縮や神経細胞の減少、脳内での活性酸素によるダメージなどが複合的に関わっていると考えられています。ストレスや生活環境の変化が症状を悪化させることもあります。
治療法
認知症を完治させる根本的な治療法はありませんが、進行を緩やかにするための治療が行われます。具体的には、薬物療法、食事療法、リハビリテーションが三本柱となります。
脳の血流を改善する薬や、不安を和らげる薬の投与、抗酸化成分や脳のエネルギー源となる成分を強化した食事(療法食)やサプリメントの活用が有効です。また、適度な散歩や飼い主とのコミュニケーションは、脳への良い刺激となります。
犬の脳・神経の病気8. 「椎間板ヘルニア」
| 病名 | 椎間板ヘルニア |
|---|---|
| 治療法 | 内科治療(安静、投薬)、外科手術、リハビリ |
| 好発犬種 | ミニチュア・ダックスフンド、ウェルシュ・コーギー、ペキニーズ、シー・ズー、ビーグルなど(軟骨異栄養性犬種) |
椎間板ヘルニアは、背骨の骨と骨の間でクッションの役割を果たす「椎間板」という組織が、脊髄神経が通る「脊柱管」の中に飛び出し、神経を圧迫してしまう病気です。特に胴長短足の犬種で好発します。
症状や特徴
症状は神経の圧迫度合いによって異なり、5つのグレードに分類されます。軽度(グレード1)では、背中を触ると痛がる、抱っこを嫌がる、段差を避けるといった痛みによる行動変化が見られます。
進行すると、後ろ足のふらつき(グレード2)、歩行不能(グレード3)、自力での排尿が困難になる(グレード4)、後肢の感覚が完全に失われる(グレード5)といった麻痺症状が現れます。
発症原因
加齢による椎間板の変性や遺伝的素因に加え、ソファからの飛び降り、激しい運動、肥満などが背骨に過度な負担をかけ、発症の引き金となります。
治療法
治療は症状のグレードに応じて選択されます。痛みのみの軽度な場合は、ケージレスト(ケージ内での絶対安静)と消炎鎮痛剤の投薬による内科治療が中心です。麻痺が見られる中〜重度の場合は、圧迫された神経を解放するための外科手術が主な治療法となります。術後は、機能回復のためのリハビリテーションも重要です。
犬の脳・神経の病気9. 「前庭疾患」
| 病名 | 前庭疾患 |
|---|---|
| 治療法 | 原因疾患の治療、対症療法、経過観察 |
| 好発犬種 | 全ての犬種(特に高齢犬) |
前庭疾患は、平衡感覚を司る「前庭」という器官(耳の奥や脳の一部)に異常が生じることで、めまいやふらつきなどの症状が現れる病気の総称です。特に原因不明で突然発症する「特発性前庭疾患」は、高齢犬に多く見られます。
症状や特徴
突然、頭が片方に傾いたままになる「斜頸」、眼球が左右や上下に小刻みに揺れる「眼振(がんしん)」、同じ方向にぐるぐる回ってしまう「旋回運動」が三大症状です。ひどいめまいから、嘔吐や食欲不振、起立不能に陥ることもあります。
発症の原因
原因は、内耳炎や中耳炎が前庭まで波及する「末梢性」と、脳腫瘍や脳炎、脳梗塞など脳自体に問題がある「中枢性」に分けられます。高齢犬に多い特発性前庭疾患は、その名の通り原因が特定できません。
治療法
中耳炎や脳腫瘍など、原因が明らかな場合はその治療を優先します。特発性の場合は、吐き気止めやめまいを和らげる薬を投与する対症療法を行いつつ、自然な回復を待つことが多く、数週間で症状が改善するケースも少なくありません。症状が重い間は、転倒による怪我を防ぐため、飼い主のサポートや環境整備が必要です。
犬の脳・神経の病気10. 「肝性脳症」
| 病名 | 肝性脳症 |
|---|---|
| 治療法 | 外科手術、内科治療(投薬)、食事療法 |
| 好発犬種 | 全ての犬種(門脈シャントは小型犬や純血種に多い) |
肝性脳症は、肝臓の機能が著しく低下することで、本来解毒されるべきアンモニアなどの有害物質が血液中に増加し、脳に達して神経症状を引き起こす病態です。先天的な血管の異常(門脈シャント)や、重度の肝炎・肝硬変などが原因となります。
症状や特徴
初期には「食欲不振」「元気消失」「嘔吐」「体重減少」などが見られます。進行すると、よだれを大量に流す、ふらつく、徘徊する、頭を壁に押し付けるといった神経症状が現れ、重症化すると「けいれん発作」や「昏睡」状態に陥ることもあります。
発症原因
門脈シャントなどの血管奇形により、腸で吸収されたアンモニアを含む血液が肝臓を素通りして全身に巡ってしまうことや、肝機能の低下によってアンモニアを解毒できなくなることが原因です。
治療法
門脈シャントが原因の場合は、異常な血管を結紮(縛る)する外科手術が根本治療となります。手術が困難な場合や、他の肝疾患が原因の場合は、内科治療が中心です。腸内でのアンモニア産