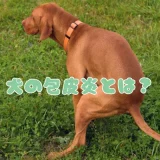いつも美味しそうにご飯を食べていたのに、「最近、愛犬がご飯を食べてくれない…」となると、飼い主さんはとても心配になりますよね。
- ✓どうしてご飯を食べてくれないの?
- ✓食欲がない時におすすめのフードは?
- ✓すぐに病院へ連れて行った方がいい?
など、愛犬の食欲不振にはわからないことも多いと思います。
犬の食欲不振には、ささいな理由から病気が隠れているケースまで様々です。愛犬の様子をしっかり観察して、何が原因なのか、どう対処すればいいのかを判断できるようになっておきましょう。
この記事では、犬がご飯を食べない原因と、家庭でできる食欲不振への対策を獣医師のコメントも交えて詳しく解説します。ぜひ参考にしてくださいね。
犬の食欲不振、原因は?
- 運動不足
- 気温や環境の変化
- 食習慣の問題
- 老化
犬の食欲不振は、必ずしも病気が原因とは限りません。生活環境や食習慣を見直すことで解決するケースも多くあります。
特に、運動不足、気温や環境の変化、食習慣、老化などが、犬の食欲不振の主な原因として挙げられます。
原因① 運動不足による消費カロリーの低下
私たち人間も、たくさん運動をした後はお腹が空きますよね。犬もそれと同じです。
犬は「1日3食きちんと食べなければ」という考えはなく、自身の消費カロリーを本能的に感じ取り、必要な食事量を判断しています。
そのため、散歩や遊びの時間が減って運動量が落ちると、消費カロリーも少なくなるため、自然と食事量が減るのです。
もちろん、犬種や性格によっては、出されれば出されただけ食べてしまう子もいますが、そういった子も肥満予防のために適切な運動は不可欠です。
原因② 気温や環境の変化によるストレス
犬は変化が少なく、規則正しい生活を好む動物です。季節の変わり目の急な気温の変化、気圧の変動、引越しによる住環境の変化などによってストレスを感じ、食欲不振に陥ることがあります。
特に繊細な小型犬はストレスを感じやすいため注意が必要です。ストレスが原因の場合は、その原因を取り除いてあげることが大切です。
引越しなどの環境変化には少しずつ慣れていきますが、ストレスを発散できるよう、散歩の時間をしっかり確保したり、室内で十分に遊んであげたりしましょう。
原因③ フードや与え方など食習慣の問題
愛犬の食欲が落ちたら、毎日の食習慣もチェックしてみましょう。
そもそも犬が好まないフードを与えていたり、フードが酸化して風味が落ちていたりしませんか?
フードの酸化とは、開封後に空気に触れることで品質が劣化してしまう現象です。腐敗とは異なりますが、栄養素が変化したり、味が落ちたりしてしまいます。
犬は嗅覚が優れているため、酸化してしまったフードは食べない傾向があります。犬の健康にも良くないので、開封したフードは酸化する前に食べ切るのが理想です。大袋の場合は密閉容器に移し、開封後1ヶ月以内を目安に使い切りましょう。
また、人間の食べ物を与えたことが原因で、ドッグフードを食べなくなるケースも少なくありません。
人間用に調理された食事は、犬にとって塩分や糖分が過剰です。犬に有害な食材が含まれている危険性もあるため、人間のご飯の残り物を与えるのは絶対にやめましょう。
犬が食べても良い食材であっても、そればかり与えていると栄養が偏ってしまいます。栄養バランスの整った総合栄養食のドッグフードが、愛犬の健康の基本です。
原因④ 老化によるシニア犬の機能低下
老犬(シニア犬)になると、嗅覚や消化機能が衰えることで食欲不振になることがあります。
犬は食事を匂いで判断するため、嗅覚が衰えるとご飯への興味自体が薄れてしまいます。
また、シニア犬は消化機能も衰えてくるため、成犬時と同じフードを同じ量与えていると消化不良を起こすことがあります。その結果、胃腸に不快感を覚えて食欲がなくなってしまうのです。
老犬の食欲不振の対策
ご飯を人肌程度に少し温めてから与えてみましょう。温めることで香りが立ち、食欲を刺激しやすくなります。
また、一度に与える量を減らし、食事の回数を増やす「少量多回」も有効な対策です。もちろん、新鮮な水をいつでも飲めるようにし、水分補給もこまめに行いましょう。
食事の工夫で改善しない場合は、無糖のプレーンヨーグルトなどを少量与えて腸内環境を整えるのもおすすめです。腸内の善玉菌や消化酵素を補い、消化機能をサポートする効果が期待できます。
ただし、同じ乳製品でも牛乳は犬が乳糖を分解できず下痢の原因になることがあるため、与えないように注意してください。
vet監修獣医師先生
犬の食欲不振、病気が原因の見分け方は?病院に連れて行く必要があるケース
| 考えられる病気 | 食欲不振と共にあらわれる症状 |
|---|---|
| 消化器系の病気・中毒 | 下痢、嘔吐、便秘、せき |
| 細菌やウイルスによる感染症 | せき、発熱、元気がない |
| 呼吸器系の病気 | 餌を飲み込みにくそうにする、呼吸が苦しそう |
| 泌尿器系の病気 | 尿が出ない、血尿が出る、普段より水をたくさん飲む |
| 歯周病 | 歯に異常がある、口臭が強い、よだれの量が多い |
| フィラリア症 | せき、お腹が張っている、呼吸が荒い |
| がん | 急にやせて元気がなくなる、しこりがある |
食欲不振だけでなく、上記のような症状がみられる場合は病気の可能性があります。自己判断せず、すぐに動物病院を受診し、適切な処置を受けさせてください。
また、明らかな症状がなくても、以下の項目は必ずチェックしましょう。
- ✓何日間ご飯を食べていないか
- ✓水は飲んでいるか
この2点は、愛犬の命に関わる重要なサインです。
犬種や年齢によって異なりますが、健康な成犬でも絶食の限界は最長で2日間、体力のない子犬やシニア犬、持病のある子の場合は最長1日と言われています。
それ以上食べない場合は、他に症状がなくてもすぐに動物病院へ連れて行きましょう。
また、ご飯だけでなく水も飲まない場合は特に危険です。
水分を摂らないこと自体が病気のサインである可能性もありますし、脱水症状を引き起こす危険性が非常に高くなります。どうしても水を飲まない場合は、スポイトなどで口を湿らせてあげながら、急いで病院へ向かってください。
vet監修獣医師先生
愛犬の食欲を失わせないためにすべきことは?
犬の食欲不振を予防するには、病気や老化以外の原因である「食習慣」「運動不足」「ストレス」を日頃からケアしてあげることが大切です。
ここでは、食欲を維持するための具体的な対策をご紹介します。
対策① 食習慣を見直して改善する
まず、人間の食べ物を与えるのは避け、栄養バランスの取れた総合栄養食を主食にしましょう。トッピングをする場合も、犬が食べても良い食材を少量乗せる程度に留めます。
フードは愛犬の食いつきが良く、無添加で良質な原材料を使用したものを選ぶのが理想です。
また、犬種、年齢、体重、体質に合ったフードを、適切な量与えることも健康維持の基本です。
対策② 適度な運動で運動不足を解消する
運動不足は消費カロリーを減らし食欲を低下させるだけでなく、犬にとって大きなストレスの原因にもなります。
チワワのような超小型犬は室内での遊びだけでも運動量を確保できる場合がありますが、気分転換や社会性を育むためにも外の散歩は大切です。
必要な運動量は犬種によって異なりますが、目安として小型犬は1日1回30分程度、中型犬は1日2回各30分程度、大型犬は1日2回各30〜60分程度の散歩が必要です。年齢や体力に合わせて、コースやペースを調整してあげましょう。
特に1歳未満の子犬期に、急に止まったり曲がったりするボール投げのような激しい運動をさせすぎると、関節を痛めることがあるので注意が必要です。
運動のさせすぎも良くありませんが、運動不足は肥満やストレスなど様々な問題につながります。愛犬に合った運動量がわからない場合は、動物病院で相談してみるのもおすすめです。
もうひとつ、散歩で注意したいのが時間帯です。夏場の暑い時間帯の散歩は避けましょう。地面に近い位置を歩く犬は、アスファルトの放射熱で熱中症になりやすく、肉球をやけどしてしまう危険もあります。
肉球のやけどは治療が難しいため、散歩は早朝の涼しい時間帯や、日が落ちて路面の熱が冷めた頃に行くようにしましょう。
対策③ 愛犬が快適な環境でストレスを軽減する
犬が感じるストレスは、人間関係のような心理的なものよりも、肉体的、環境的な要因が大きいと言われています。
・環境の変化:気温・気圧・湿度の変化、部屋が明るすぎる、騒々しい、苦手な臭いがする、引越し、家族構成の変化 など
・身体的な状態:空腹、喉の渇き、疲労、運動不足、病気による痛みやかゆみ、緊張、興奮、孤独 など
上記のように、多くのことが犬のストレス原因となり得ます。人間が快適だと感じる環境が、必ずしも犬にとっても快適とは限りません。
例えば、犬は暗い場所でもよく目が見えるため、明るすぎる照明はストレスになります。また、人間よりはるかに優れた嗅覚を持つため、芳香剤や香水の強い香りは不快に感じます。聴覚も敏感で、テレビや家電の電子音、掃除機の音などを怖がる子も多いです。
家庭内の険悪な雰囲気も、犬は敏感に察知してストレスを感じます。
過度なストレスは食欲不振だけでなく、問題行動や様々な病気の引き金にもなります。愛犬のストレスを減らすために、以下のポイントを意識してみてください。
- ✓長時間の留守番後は、たくさん構ってあげる
- ✓食事と水の管理、排泄物の状態を毎日チェックする
- ✓愛犬に合った適切な運動を毎日行う
- ✓寝床やトイレを常に清潔に保つ
- ✓照明を明るくしすぎず、静かな環境を心がける
- ✓家族が穏やかに過ごす
- ✓エアコンなどで快適な室温を保つ
愛犬が毎日ご飯を美味しく食べて、健康で長生きしてもらうためにも、できるだけストレスのない環境を整えてあげたいですね。
vet監修獣医師先生
気になるときはすぐに病院へ
ご紹介した対策を色々試してみても愛犬の食欲不振が続くときは、迷わず動物病院へ連れていってください。動物は本能的に弱みを見せないようにするため、なにか症状が出ているときには既に状態が良くないことも考えられます。愛犬に長生きしてもらうためにも、早期発見・早期治療が何よりも大切です。