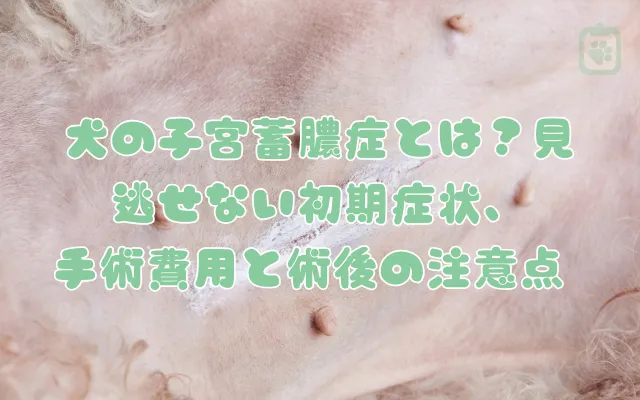犬は人間と同じように、性別によってかかりやすい病気が異なります。特に、避妊手術をしていない中高齢のメス犬がかかりやすい病気の一つに「子宮蓄膿症(しきゅうちくのうしょう)」があります。この病気は出産経験のない犬に多く見られる傾向があります。
この記事では、犬の子宮蓄膿症がなぜ起こるのか、その原因や発症時の具体的な症状、手術による治療法や費用について、獣医療の専門家の監修のもと詳しく解説します。
犬の子宮蓄膿症とは?原因は?
犬の子宮蓄膿症とは、子宮内に細菌が感染することで炎症が起こり、膿が溜まってしまうメス犬特有の病気です。犬の子宮蓄膿症の主な原因は、発情後のホルモンバランスの変化です。発情が終わると、プロゲステロン(黄体ホルモン)というホルモンの影響で子宮内膜が厚くなり、子宮の免疫力が低下します。このタイミングで大腸菌などの細菌が子宮内に侵入・増殖することで発症します。
特に高齢になり免疫力が低下している犬は注意が必要です。また、若い犬でも発情後の黄体期は免疫機能が低下するため、子宮蓄膿症を発症しやすくなります。
vet監修獣医師先生
犬の子宮蓄膿症の初期症状は?
犬の子宮蓄膿症を発症すると、以下のような初期症状が見られることがあります。飼い主が気づきにくいサインもあるため、日頃から愛犬の様子を注意深く観察することが重要です。
- 元気がなくなる
- 食欲が低下する、または全く食べない
- 発熱、嘔吐、下痢
- 水をたくさん飲み、おしっこの量が増える(多飲多尿)
- 陰部から黄色や茶褐色の膿が出る(膿が出てこないタイプもあります)
- お腹が張って膨らんでくる(腹部膨満)
これらの犬の子宮蓄膿症の症状が進行すると、溜まった膿で子宮が破裂して激しい腹膜炎を起こしたり、細菌が出す毒素が全身に回って腎不全や敗血症性ショック、播種性血管内凝固症候群(DIC)といった命に関わる重篤な状態に陥る危険があります。
初期症状は単なる体調不良に見えがちで、重症化してから気づくケースも少なくありません。「いつもより元気がないな」と感じたら、早めに動物病院に相談しましょう。
vet監修獣医師先生
犬の子宮蓄膿症は手術で治療する?
犬の子宮蓄膿症の治療は、手術による外科的アプローチが第一選択となります。診断は、レントゲン検査やエコー(超音波)検査で子宮の腫れや膿の貯留を確認し、同時に血液検査で白血球数の増加など全身の炎症状態を評価して総合的に判断します。
子宮蓄膿症と診断された場合、根本的な治療として、膿が溜まった子宮と卵巣を摘出する手術を緊急で行うのが一般的です。抗生剤などによる内科治療も選択肢にはありますが、完治は難しく再発率が非常に高いため、全身状態が許す限り手術が推奨されます。
初期段階で発見し、適切な手術治療を行えば予後は良好で、多くは完治が可能です。しかし、発見が遅れて多臓器不全などを併発してしまった場合は、命を落とす可能性も高くなります。
犬の子宮蓄膿症の手術費用はどれくらい?
犬の子宮蓄膿症の手術費用は、動物病院の所在地や設備、犬の体重、病状の重症度によって大きく変動しますが、目安として5万円〜30万円程度かかると考えておくとよいでしょう。夜間や休日の緊急手術、入院日数が長くなる場合、あるいは合併症の治療が必要な場合は、費用がさらに高額になる可能性があります。
vet監修獣医師先生
犬の子宮蓄膿症の術後に気をつけることは?
犬の子宮蓄膿症の手術後は、愛犬が安心して回復に専念できるよう、飼い主のきめ細やかなケアが大切です。術後7日~10日ほどは、以下のような様子が見られることがあります。
- 食欲がない、またはムラがある
- 傷口から少量の出血や浸出液がある
- 小刻みに震える
- エリザベスカラーや術後服を嫌がる、傷口を舐めようとする
- 散歩などの運動を嫌がる
これらの症状は時間と共に少しずつ回復していきますが、元気や食欲が全く戻らない、出血が多いなど、術後の経過で気になることがあれば、自己判断せずに手術を受けた動物病院にすぐに相談してください。
vet監修獣医師先生
犬の子宮蓄膿症を対策するには?
犬の子宮蓄膿症を予防するための最も確実な対策は、若いうちに避妊手術を受けることです。避妊手術で病気の発生源となる子宮と卵巣を摘出するため、子宮蓄膿症になるリスクを根本的になくすことができます。
将来的に繁殖を希望しないのであれば、早期の避妊手術が最も有効な対策と言えます。避妊手術を行う時期については、初回の発情を迎える前の生後6ヶ月前後が一般的ですが、犬種や個々の成長に合わせて、かかりつけの獣医師と相談して決めましょう。
vet監修獣医師先生
犬の子宮蓄膿症は早期発見が大切
犬の子宮蓄膿症は、放置すれば命を脅かす非常に危険な病気ですが、早期発見・早期治療によって完治させることが可能です。
この病気の早期発見のために最も大切なのは、飼い主が普段から愛犬の様子をよく観察することです。食欲や元気、飲水量、おしっこの状態、陰部からの分泌物の有無などを毎日チェックし、少しでも「いつもと違う」と感じたら、ためらわずに動物病院を受診してください。その行動が、愛犬の命を救うことに繋がります。
vet監修獣医師先生